
この記事が含む Q&A
- ADHDの薬を服用することで、どのような効果が期待できますか?
- 行動上のリスク、自己傷害、交通事故、犯罪の発生率を低減させる効果があります。
- 薬の効果は時とともに弱まることがありますか?
- はい、症状の軽い人や処方範囲の拡大により平均的な効果が薄まる傾向があります。
- ADHD治療には薬だけでなくどのような支援が必要ですか?
- 薬物療法、行動療法、環境調整を含む包括的な個別支援が重要です。
注意欠如・多動症(ADHD)という言葉は、今や多くの人に知られています。
けれども、その治療薬についての現実的な効果や、処方の広がりが社会にもたらす影響について、私たちはどれほど理解しているでしょうか。
スウェーデンで行われた約25万人を対象とした大規模研究が、その疑問に答えようとしました。
薬を飲む人が増えるにつれて、本当に効果は保たれているのか。
そもそも、その効果とは何か。
論文は、静かな問いかけを社会に投げかけています。
この研究は、スウェーデンの全国登録データを用いたものです。
対象となったのは、2006年から2020年の間にADHDの薬を服用した、4歳から64歳までの24万7,420人です。
研究チームには、スウェーデンのカロリンスカ研究所やオーストラリア、アメリカなど複数の国の専門家が参加しました。
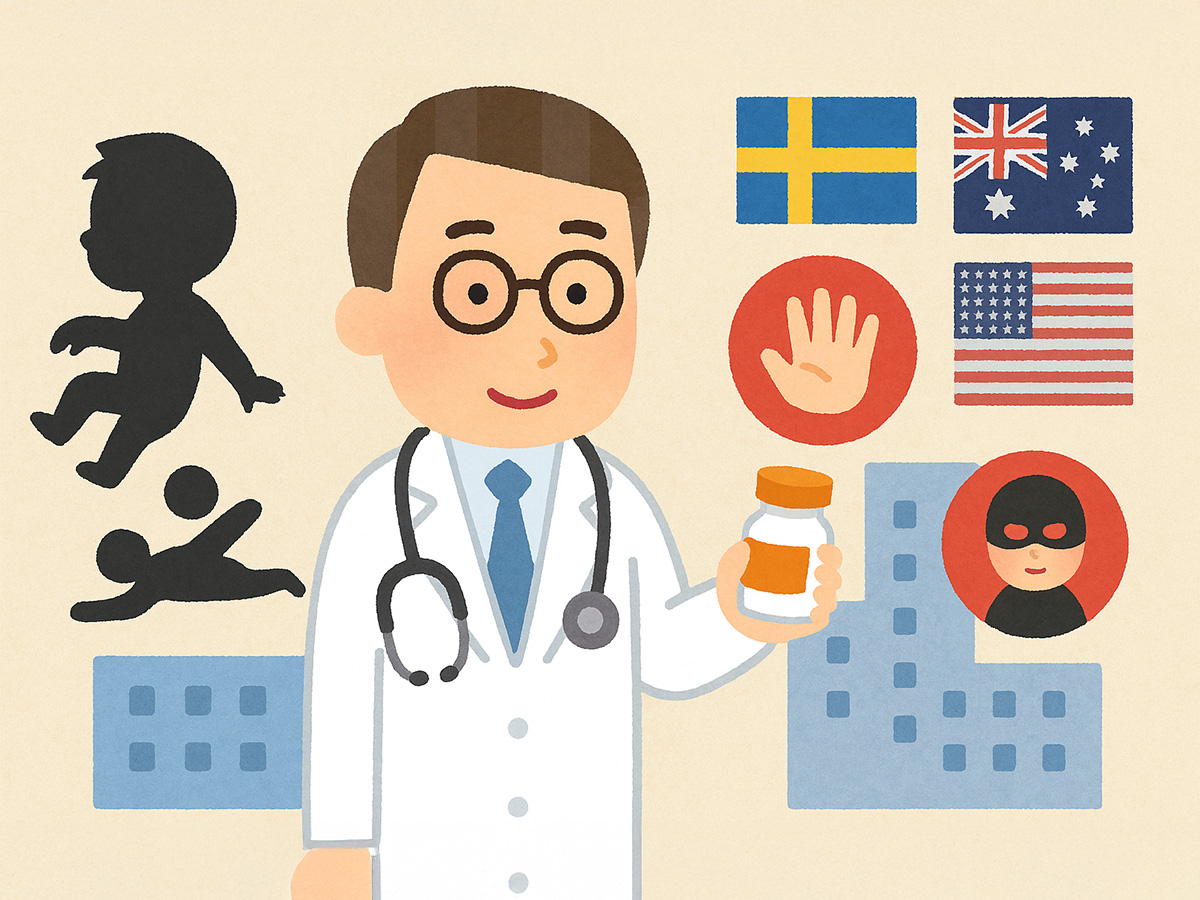
調査の中心は、ADHDの薬が現実の生活にどのような影響を与えているかという点です。
ここでいう「影響」とは、自己傷害、偶発的なけが、交通事故、犯罪行為といった深刻な現象を指しています。
これらの出来事が、薬を飲んでいる期間と飲んでいない期間で、どれだけ違っているのか。
それを、ひとりひとりの行動を追いながら分析したのが、この研究です。
研究方法には「自己対照ケースシリーズ」という手法が使われました。
これは、ひとりの人間の「薬を飲んでいた時期」と「飲んでいなかった時期」とを比べる方法です。
他人との比較ではなく、本人の中で変化を見ることで、遺伝的な特徴や社会的背景などの影響を除いて、薬の効果をより明確にしようとするものです。
調査対象となった24万7,420人のうち、女性は約4割(99,361人)、男性は約6割(148,059人)でした。
期間を3つに区切って比較すると、2006〜2010年は5万7,263人、2011〜2015年は12万7,241人、2016〜2020年には20万141人が薬を使用していました。
とくに注目すべきは、女性の割合が年々増加していることです。
スウェーデンではこの15年間で、ADHDの薬の処方が急速に増加しました。
子どもに対しては0.6%から2.8%へ、成人では0.1%から1.3%へと、ほぼ10倍に増えたのです。
この背景には、診断基準の緩和、社会的な理解の広がり、医療現場の意識の変化などがあると考えられています。
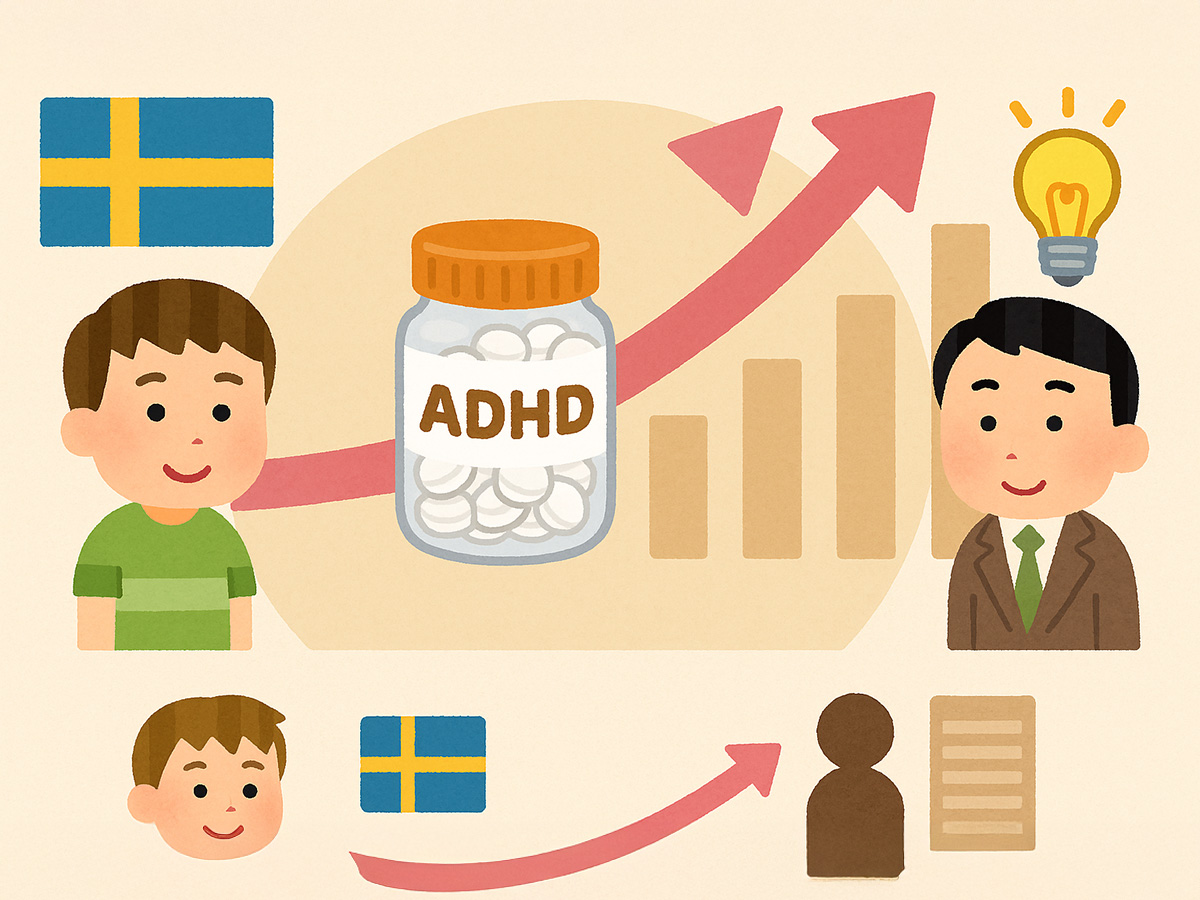
では、そのように処方が増える中で、薬の効果はどう変化したのでしょうか。
研究結果によれば、ADHDの薬を服用している期間は、自己傷害、けが、交通事故、犯罪のすべてにおいて、服用していない期間に比べて発生率が低下していました。
たとえば、交通事故では、服用中はおよそ13%〜29%もリスクが低くなっていたのです。
自己傷害に関しては、最も効果が大きかったのが2006〜2010年(リスク比0.77)、その後も効果は続いていますが、若干弱まっていることがわかりました。
偶発的なけがでは、2006〜2010年はリスク比0.87、2011〜2015年には0.90、2016〜2020年では0.93と、徐々に効果が小さくなっている傾向が見られました。
交通事故と犯罪についても同様の傾向がありました。
この「効果の弱まり」は何を意味しているのでしょうか。
研究チームは、薬を使う人の層が広がったことが一因ではないかと見ています。
つまり、以前は症状が重く、行動面に強い問題があった人に主に処方されていた薬が、次第に症状の軽い人や、行動リスクの少ない人にも使われるようになってきたのです。
その結果、薬の「平均的な」効果が薄まって見える可能性があるのです。

この点を確認するため、研究者たちは性別や年齢による分析も行いました。
男性も女性も、薬を使っているときには各リスクが低下していましたが、とくに2006〜2010年の女性ではその効果が顕著でした。
たとえば犯罪のリスクは、薬を飲んでいる期間には33%も低下していたのです。
しかし、時が経つにつれてこの差は縮まり、2020年には16%の低下にとどまりました。
これは当時、女性のADHDが見過ごされがちであり、診断された人は比較的重症だったことを反映している可能性があります。
診断の対象が広がることで、効果の平均も薄まっていく。
そんな構造が見えてきます。
また、自己傷害については、女性のほうが絶対数でも男性を上回っていました。
これは、ADHDの女性が「注意欠如型」であることが多く、内に向かう傾向が強いためと考えられています。
一方、男性では外向的な行動が目立ちやすく、けがや事故、犯罪といったリスクが高い傾向があります。
なお、研究では、薬の種類によって結果が変わるかどうかも検証されました。
もっとも多く使われている「メチルフェニデート」のみに絞った分析でも、全体の傾向はほぼ同じでした。
つまり、薬の種類というよりも、薬を使う人の特徴の変化が、効果の変化に関係していると考えられるのです。
もちろん、この研究にも限界があります。
あくまで観察研究であり、因果関係を断言することはできません。
また、薬を処方された人が実際にきちんと飲んでいたかどうかの確認まではできません。
ライフスタイルの変化や他の治療の影響も完全には除外できないでしょう。
それでもこの研究が示すのは、ADHDの薬が、行動上のリスクを確かに減らす効果を持っているという事実です。
そしてその効果が、時間とともに、処方対象の変化とともに、変わりつつあるという現実です。

ADHDの治療は、単に「薬を出せばいい」というものではありません。
薬には効果があり、副作用もあります。
個人の症状、年齢、性別、環境、そして人生の文脈に合わせた「慎重な判断」が求められるのです。
とくに最近は、ADHDの診断そのものが広がりすぎているのではないかという議論もあります。
軽度の症状でも、薬に頼るべきなのか。
他の支援策や心理的介入のほうが適している場合もあるかもしれません。
研究者たちは、今後の課題として、より個別化された治療のあり方を探る必要があると述べています。
どのような人に、どのタイミングで、どんな形の治療が適しているのか。
薬だけでなく、行動療法や環境調整なども含めた包括的な支援が求められています。
また、患者本人の声も大切です。
薬を飲んで「生きやすくなった」と感じる人もいれば、「自分らしさを失った」と感じる人もいるでしょう。
その感覚の違いこそ、治療のあり方を考える手がかりとなるはずです。
この研究は、単なる数字の羅列ではなく、私たちの社会がどのようにADHDと向き合っているのか、そしてこれからどうしていくべきなのかを問うメッセージでもあります。
薬の効果が「薄れた」と言うと、ネガティブに聞こえるかもしれません。
しかし、それは薬が無力になったのではなく、使い方と向き合い方が問われる時代に入ったということなのかもしれません。
ADHDという診断が、より多くの人の苦しみに気づく手がかりとなる一方で、治療の安易な一本化は避けるべきです。
一人ひとりの生き方に寄り添いながら、社会全体でより良い支援のあり方を探っていく。
その第一歩として、この研究は大きな意味を持っていると言えるでしょう。
(出典:JAMA Psychiatry)(画像:たーとるうぃず)
薬の効果は確かにある。ことがわかる結果です。
「生きやすくなった」/「自分らしさを失った」
表裏一体のように思います。
自分らしくあってほしいと願いますが、自傷や事故が減るならそれに勝るものはないと私は思います。
(チャーリー)




























