
この記事が含む Q&A
- 自閉症の多様性を理解するために最新の分析手法は何ですか?
- 「ジェネレーティブ ミクスチャー モデリング(GFMM)」という手法を用いています。
- 自閉症の子どもたちを4つのグループに分類した研究結果は何ですか?
- 軽度課題群、広範課題群、社会・行動課題群、発達遅滞併存群の4つに分けられました。
- 遺伝的な特徴と自閉症のグループの関係はどうなっていますか?
- 社会・行動課題群はADHDやうつのリスク遺伝子が高く、広範課題群は知的障害関連の遺伝子が多いことが判明しました。
自閉症は、人と関わることやコミュニケーションが苦手であったり、同じ行動を繰り返すことが特徴とされています。
しかし、自閉症の子どもたちは、一人ひとり異なる特徴や困りごと、得意なことがあります。
そのため、自閉症は一つの形ではなく、多様な姿があることが知られています。
この多様性の理由を明らかにすることは、自閉症の理解や支援に役立つと考えられていますが、これまでその全体像を明確に示すことは難しい課題でした。
今回紹介する研究は、この自閉症の多様性の背景にある遺伝的なプログラムを明らかにするために行われました。
この研究は、アメリカのプリンストン大学、ルイス・シグラー統合ゲノミクス研究所、フラットアイアン研究所、シモンズ財団、マウントサイナイ・アイカーン医科大学、イスラエルのベングリオン大学などの研究チームによって実施されたものです。
この研究では、自閉症の多様性を理解するために「ジェネレーティブ ミクスチャー モデリング(GFMM)」という最新の解析手法を用いました。
「ジェネレーティブ ミクスチャー モデリング(GFMM)」は、多くの項目データから似た特徴を持つグループ”を自然に見つけるための方法です。
自閉症の子どもたちの特徴は、一つずつバラバラに出ているのではなく、複数の特徴が一緒に出ていることが多くあります。
GFMMでは、例えば「言葉が遅れている」「落ち着きがない」「不安が強い」などの特徴を組み合わせて、その子がどのような特徴の集まりを持っているかを大切にしながら解析することができます。

「ジェネレーティブ(生成的)」というのは、「もしこのデータが複数のグループの組み合わせでできているとしたら、そのグループはどんな特徴を持つだろうか」という考え方でグループを見つける方法です。
実際には「この子は100%このグループ」という分け方ではなく、「このグループの特徴に80%当てはまる」など、一人ひとりの特徴を切り離さず、その子の全体像を大事にしてグループ分けを行います。
GFMMは、年齢のように数値で表す情報、はい・いいえで答える情報、段階で表す情報など、異なる種類の情報をまとめて解析できる強みがあります。
今回の研究では、このGFMMを用いることで、自閉症の子どもたちを特徴ごとに分けるのではなく、一人ひとりの特徴を総合的にとらえながら、自然にグループ分けすることが可能になりました。
研究チームは、アメリカのSPARK(スパーク)コホートという全国規模の自閉症の遺伝子・臨床データを集めたデータベースから、5,392人の自閉症の子どもと1,972人の自閉症でないきょうだいのデータを活用しました。
このデータには、社会的コミュニケーションの困難さ、反復行動、注意欠如、多動、気分や不安の症状、発達の遅れ、自傷行為などを含む239項目の情報が含まれています。

このデータをGFMMで解析した結果、自閉症の子どもたちは次の4つのグループに分けられることがわかりました。
1)「軽度課題群(Moderate challenges)」
比較的困りごとが少なく、他の自閉症の子どもよりも軽度の特徴を示すグループ。
2)「広範課題群(Broadly affected)」
多くの領域で困難さを抱え、広範な課題があるグループ。
3)「社会・行動課題群(Social/behavioral)」
社会的コミュニケーションと反復行動に強い課題があり、注意欠如や不安、破壊的行動も伴うグループ。
4)「発達遅滞併存群(Mixed ASD with DD)」
発達遅滞を伴う自閉症の特徴を持ち、言語の遅れや知的障害、運動障害が強く見られるグループ。
これらの分類は、診断結果や保護者の報告とも一致しており、各グループで共存するADHDやうつ、不安障害、言語遅滞、運動障害の有無などの傾向も異なることが示されました。
また、この分類が他のデータでも当てはまるかを確認するために、「シモンズ シンプレックス コレクション(SSC)」という別のデータベース(861人の自閉症の子ども)で検証を行った結果、同じ4つのグループが再現できることも確認されました。
次に、各グループごとの遺伝的な特徴を詳しく調べました。
「ポリジェニック スコア(PGS)」という方法で、複数の遺伝子の変異がどの程度影響しているかを解析した結果、「社会・行動課題群」ではADHDやうつ病のリスクに関連する遺伝的な特徴が高く、「広範課題群」では知的障害や発達遅滞に関連する遺伝的な特徴が高いことがわかりました。
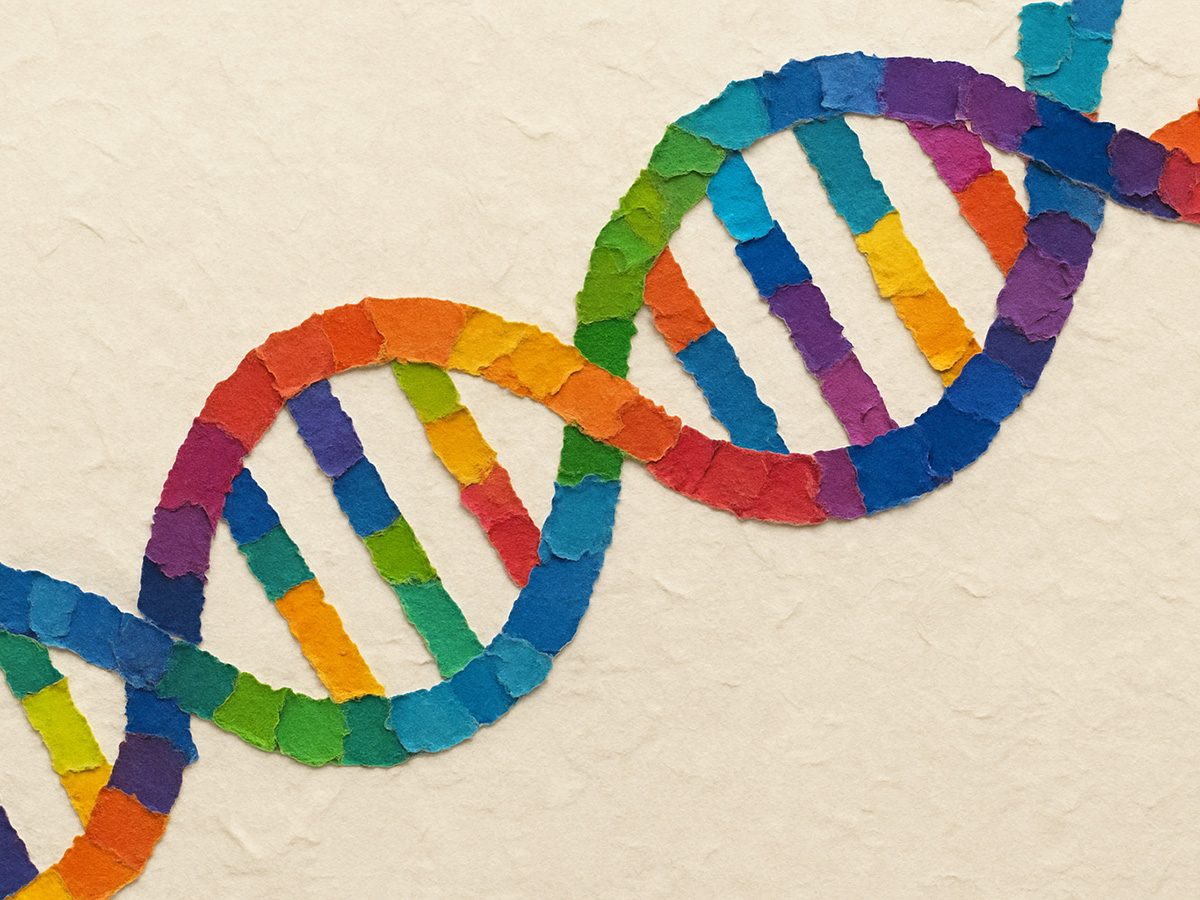
また、生まれてから突然起こる「デ ノボ変異」と、親から受け継ぐ「稀な遺伝性変異」についてもグループごとに違いがありました。
広範課題群ではデ ノボ変異が多く、発達遅滞併存群ではデ ノボ変異と稀な遺伝性変異の両方が多く見られました。
さらに、これらの変異が影響する遺伝子が脳の発達のどの時期に発現するかもグループごとに異なりました。
発達遅滞併存群では胎児期から新生児期に発現する遺伝子が影響を受けている一方で、社会・行動課題群では出生後に発現する遺伝子が影響を受けていることがわかりました。
この違いは、診断される年齢や発達のマイルストーン達成時期の違いとも一致していました。
このように今回の研究では、自閉症の子どもたちの多様な特徴と、それに対応する遺伝的プログラムの関係が具体的に示されました。
これにより、一人ひとりの特徴に合わせて具体的な支援を考えることが可能となり、自閉症の診断や支援の現場で役立つ可能性が広がります。
このような研究の進展により、自閉症の子どもたち一人ひとりが持つ個性と強みを大切にしながら、その子に合った支援を届けられる社会の実現に近づいていくことが期待されています。
(出典:Nature DOI: 10.1038/s41588-025-02224-z)(画像:たーとるうぃず)
これまでの分類は、あまりに広すぎるように思います。
このようにもっと細かく分けた方が、適切な支援につながると思います。
(チャーリー)




























