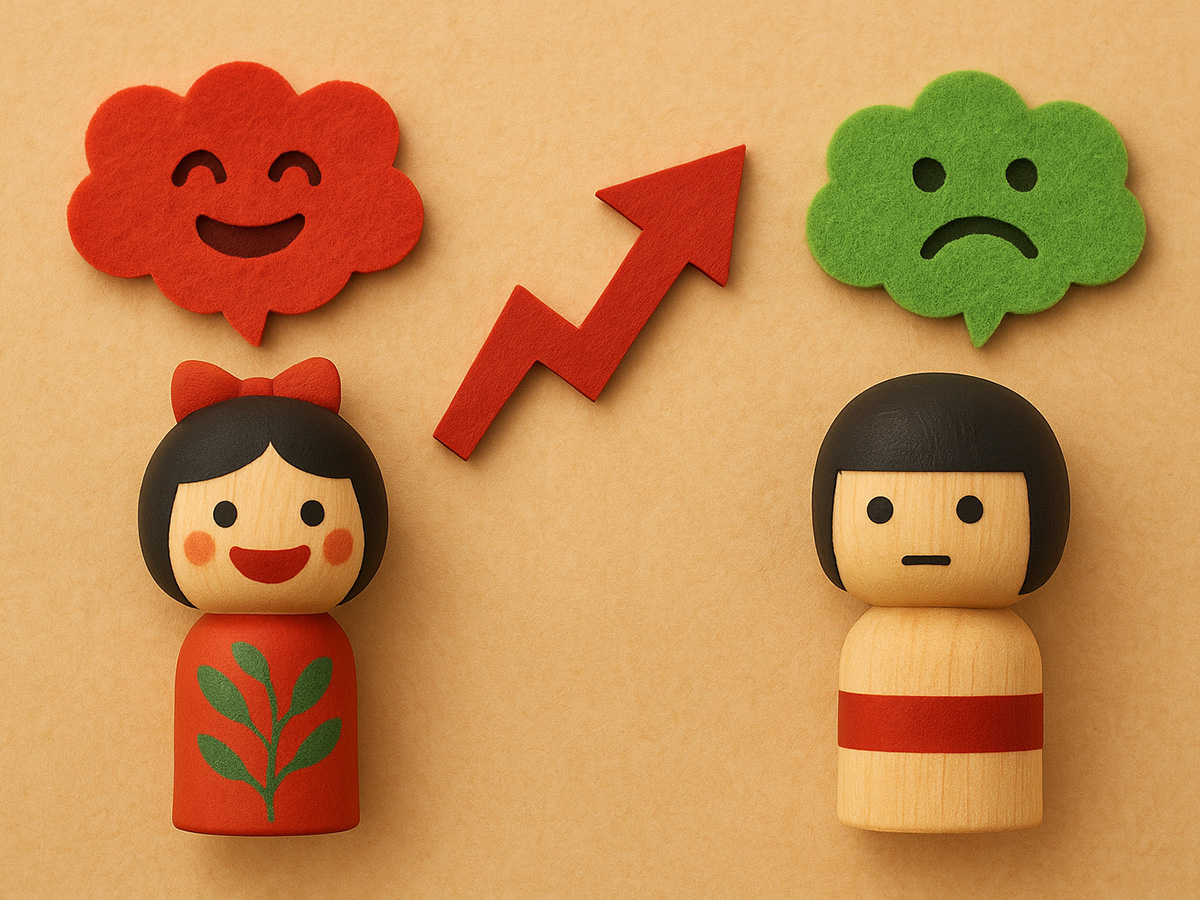
この記事が含む Q&A
- ASDの子どもはふつうの場面でも声のゆれが大きくなるのはなぜですか?
- ふつうの場面でASDの子どもの声のゆれが大きい傾向があり、感情を声で伝える練習の差が影響している可能性が示唆されています。
- 「好き」と「きらい」を話すとき、どう違いが見られましたか?
- 好き・きらいを話すとき、健常児は声の変化が最も大きいのに対し、ASDの子どもはその変化が少なく、感情を声にのせにくいことが分かりました。
- この研究から得られる支援のヒントは?
- 声の特徴を手がかりに早期支援のマーカーとして活用したり、感情をこめて話す練習を通じてコミュニケーション力を高める支援につなげられる可能性があります。
人は話すとき、ただ言葉を口にするだけではなく、声の調子や速さ、高さなどを自然に変えています。
たとえば、うれしいときには明るく高めの声、怒っているときには低く強い声になるなど、声の出し方で自分の気持ちを伝えることができます。
こうした「声の変化」は、ことばだけでは伝わらない感情を相手に届ける大切な手段となっています。
この「声の表現」は、大人だけでなく、小さな子どもにとってもとても大切です。
しかし、自閉スペクトラム症(ASD)のある子どもたちは、このような感情を声でうまく伝えることが苦手な場合が多いとされています。
たとえば、話すときに声が単調だったり、気持ちが声にあらわれにくかったりすることがよくあります。
今回の研究は、長崎大学大学院医歯薬学総合研究科、北翠会記念病院、岐阜大学工学部、静岡大学情報学部など、複数の研究機関が協力して行った共同研究です。
この研究では、5歳の子どもたちを対象に、話し声から「気持ちを表す声の変化」がどのようにあらわれるのかを調べました。
とくに、自閉スペクトラム症のある子どもと、そうでない子どもとの違いに注目しています。

研究に参加したのは、自閉スペクトラム症の診断を受けた5歳の子ども19人と、発達に特別な問題のない同じ年齢の子ども19人です。
すべての子どもたちに対して、「ふつう」「好き」「きらい」という3つの気持ちを表す場面で、言葉を話してもらい、そのときの声を録音して調べました。
「ふつう」の場面では、「ボールを投げる」「イスにすわる」といった日常の動きを描いた絵を見せて、「ボールをなげる」などの言葉を言ってもらいました。
「好き」と「きらい」の場面では、どうぶつや食べもの、おもちゃなどが描かれた絵を見せて、「キリンがすき」「ゴリラはきらい」など、自分の気持ちを言葉にしてもらいました。
研究チームは、子どもたちの話す声の「高低の変化の幅(声のゆれ)」に注目しました。
この幅が大きいと、声に抑揚があることを意味します。逆に、この幅がせまいと、声が平坦で単調になってしまいます。
結果として、「ふつう」の場面では、自閉スペクトラム症のある子どもたちの声のほうが、発達に問題のない子どもたちよりも、声のゆれが大きくなっていました。
つまり、とくに感情をこめて話す必要のない場面でも、声の高さにバラつきがあったということです。
一方、「好き」や「きらい」といった感情をこめて話す場面では、発達に問題のない子どもたちのほうが、声の変化がよりはっきりしていました。
とくに「好き」と言っているときには、声が高くなったり、抑揚がついていたりと、感情が声に表れているのがわかりました。

ところが、自閉スペクトラム症のある子どもたちは、「好き」や「きらい」を話すときも、声の高低にあまり変化が見られませんでした。
つまり、自分の気持ちを声にのせて伝えるのが苦手であることが、数字としてもはっきりと表れたのです。
さらに研究では、「好き」と言っているときの声の変化が少ない子どもほど、自閉スペクトラム症の特徴が強い傾向があることもわかりました。
これは、声に感情が出にくいということと、自閉スペクトラム症の特性の強さが関係している可能性を示しています。
この研究は、年齢を5歳にしぼって実施されました。
というのも、子どもの話し方や声の使い方は年齢によって大きく変わるため、年齢に幅があると、正確な比較ができなくなるからです。
5歳という年齢は、ちょうど「好き」「きらい」などの気持ちを表現できるようになる時期であり、実験も十分に理解できる時期だとされています。
また、使われた言葉も、3歳ごろまでに覚える基本的な単語ばかりで構成されており、子どもにとって負担が少ないように工夫されていました。
音声の分析には、録音した声をコンピュータで細かく調べる方法が使われました。
1秒間に100回の単位で声の高さを測り、最低の高さと最高の高さの差を計算して、声の変化の幅を出しました。
この方法によって、目では見えないような細かな声の違いまで正確に比べることができます。

統計的な分析の結果、「ふつう」の場面では自閉スペクトラム症のある子どもの声の変化が大きく、「好き」「きらい」では違いが見られませんでした。
ただし、発達に問題のない子どもたちのあいだでは、「好き」と話すときの声の変化が最も大きく、「ふつう」や「きらい」とははっきり違っていました。
これは、発達に問題のない子どもたちは、自分の感情に応じて声の出し方を変えることができていることを示しています。
一方で、自閉スペクトラム症のある子どもたちは、どの気持ちを話しているときでも、声の出し方に変化がなく、感情がうまく声にのっていないことがわかりました。
このような声の出し方のちがいは、日常生活でも影響を与える可能性があります。
たとえば、友だちと話しているときに気持ちが伝わらず、誤解されたり、コミュニケーションがうまくいかなかったりすることがあるかもしれません。
また、研究では、「好き」と言っているときの声の変化の少なさと、自閉スペクトラム症の特徴の強さとの間に、明確な関係があることも示されました。
つまり、声で気持ちを表すのが苦手なほど、自閉スペクトラム症の特性が強く出ている傾向があったのです。

こうした結果は、将来的に「声の使い方」を通じて、自閉スペクトラム症のある子どもたちの特性を見つけたり、支援につなげたりするための手がかりになるかもしれません。
たとえば、声の特徴をもとに、早い段階で支援が必要な子どもを見つける「声のしるし(マーカー)」として使える可能性があります。
また、感情をこめて話す練習を通じて、コミュニケーション力を高める支援にもつなげられるかもしれません。
この研究にはいくつかの限界もあります。
たとえば、参加した子どもたちの数が少なかったことや、ほとんどが男の子だったことなどです。
今後はもっと多くの子どもを対象にしたり、女の子の声の特徴もくわしく調べたりすることが求められます。
また、今回の実験では「ふつう」「好き」「きらい」という3つの気持ちにしぼって調べましたが、実際には人の感情にはもっとたくさんの種類があります。
たとえば、「うれしい」「かなしい」「こわい」「びっくりした」など、さまざまな気持ちをあらわす場面での声の使い方を調べることで、より深い理解が得られると考えられます。
声は、ことばだけでは伝えきれない「気持ち」や「こころの動き」を届ける大切な手段です。
その声をうまく使えるようになることは、自閉スペクトラム症のある子どもたちにとって、まわりとのつながりを豊かにする大きな力になるはずです。
(出典:Frontiers DOI: 10.3389/fpsyt.2025.1444675)(画像:たーとるうぃず)
困難をかかえる人を知る、理解する、効果的な支援を行う、そのためには、この違いを大きく捉える必要があります。
しかし一方で、コミュニケーションという観点からすると、この違いを大きく捉えないほうがいいだろうと私は思います。
(チャーリー)





























