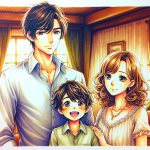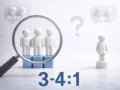この記事が含む Q&A
- ADHDの人はなぜ刺激的な音楽を好むのでしょうか?
- 脳の低覚醒状態を補い、自己調整や気分の高揚に役立てているからです。
- 音楽はADHDの人の集中力にどのように影響しますか?
- 両方とも感じ方は個人差があるものの、集中力向上を実感する人も多いです。
- なぜ「勉強中に音楽はダメ」と言われるのでしょうか?
- 伝統的な認識では、音楽が気散りの原因とされてきましたが、実際は個人差があります。
私たちは日々の生活のなかで、何気なく音楽を聴いています。
とくに最近は、スマートフォンやストリーミングサービスの普及によって、いつでもどこでも音楽を「ながら」で流せるようになりました。
料理をしながら、勉強しながら、通勤しながら。
こうした「BGM=バックグラウンド・ミュージック」は、多くの人にとって日常の一部となっています。
では、この「BGM」が私たちの気分や集中力にどんな影響を与えているのでしょうか?
そして、とくに注意欠如・多動症(ADHD)のある人たちにとっては、どのような意味を持つのでしょうか?
今回の研究は、そうした疑問に正面から取り組んだカナダの研究です。
この研究は、モントリオール大学を中心とした研究チームによって行われました。
心理学部のほか、音楽と脳の関係を専門とする複数の研究機関──たとえば国際脳・音楽・音響研究所(BRAMS)、音楽・感情・認知研究室(MUSEC)、脳と言語と音楽の研究センター(CRBLM)などが連携しています。
調査に参加したのは、カナダを中心とした17歳から30歳の若年成人434人です。
このうち、ADHD傾向が強いと自己申告した人が118人、それ以外の比較的定型的な注意傾向を持つ人が316人となっています。
すべての参加者は、聴覚に問題がなく、ほかの神経発達症や精神疾患がないことが条件とされました。
研究チームはまず、「どんなときにBGMを流しているか」「どんな音楽を選ぶか」「音楽を聴いたときに気分や集中にどんな変化があると感じるか」といったことを、詳細なアンケート形式で尋ねました。
その結果は、ADHDをもつ人とそうでない人とのあいだに、いくつもの興味深い違いがあることを示しています。

たとえば、ADHDグループの人たちは、「家事」や「運動」などの比較的頭を使わない活動(研究では「低認知活動」と分類)をするときに、BGMを流す頻度が明らかに高いことがわかりました。
さらに、「勉強」や「暗記」などの集中を要する活動(「高認知活動」)でも、ADHDグループのほうが音楽を流す傾向が強く見られました。
また、選ぶ音楽の特徴にも違いがあります。
ADHDグループでは、「テンポが速い」「刺激の強い」「歌詞がある」音楽を選ぶ傾向が強く、特に「刺激的な音楽」を好む割合がすべての活動において高くなっていました。
対して、ADHDでない人たちは、集中を要する活動では「リラックスできる」「楽器のみの」「なじみのある」音楽を選ぶ傾向が強く見られました。
興味深いのは、音楽を選ぶ「理由」にも違いがある点です。
ADHDグループの人たちは、「気持ちを高めたい」「やる気を出したい」「眠気をとばしたい」といった「覚醒レベルを上げる」目的で音楽を選んでいる傾向が強く出ていました。
これはADHDにしばしば見られる「低覚醒状態(脳の働きが低いと感じる)」への対処として、音楽が自己調整の手段になっている可能性を示唆しています。
実際、ADHDでは脳の報酬系や覚醒レベルの調整に関わる「ドーパミン系」が低下しているという研究もあり、適切な刺激が必要だという「中程度覚醒理論(MBAモデル)」とも一致しています。
BGMがこの調整役を果たしている可能性は高いといえます。

では、BGMを聴くことによって、当事者たちは自分の集中力や気分がどう変化したと感じているのでしょうか?
今回の研究では、「BGMによって集中力が上がると感じるか」「気分が落ち着くか」「ストレスは減るか」といった27の質問項目が使われました。
これらを因子分析した結果、「認知的効果(集中・記憶・作業効率など)」と「感情的効果(気分・ストレス・安心感など)」の2つのグループに分けられました。
その上で、ADHDグループと非ADHDグループのあいだで、この2つの効果の感じ方に違いがあるかどうかが検討されました。
意外なことに、「BGMが集中力に良い影響を与えると感じるかどうか」については、両グループで大きな違いは見られませんでした。
つまり、ADHDのある人もない人も、BGMが集中に与える主観的な影響は同程度だったのです。
しかし、「気分が落ち着く」「イライラが減る」といった感情面の効果については、ADHDのある人たちのほうがより強く「ポジティブな効果がある」と感じている傾向が見られました。
また、より細かく見ると、「掃除をしているとき」「料理をしているとき」などに音楽を聴く頻度が高い人ほど、「不安スコア(POMS:緊張・不安尺度)」が高いという傾向も明らかになりました。
つまり、BGMが「不安の自己調整」として用いられている可能性があるのです。

こうした結果から研究チームは、「BGMはADHDのある人たちにとって、感情や覚醒レベルの自己調整の手段となっている」と結論づけています。
とくに「刺激的な音楽」を自分で選んで聴くことで、脳の活性を高め、不安やぼんやり感を和らげる手助けになっていると考えられます。
一方で、「音楽を流すと気が散る」と感じる人も一定数存在し、それはADHDの有無にかかわらず個人差が大きいことも、今回の研究では確認されました。
そのため、音楽の活用には一律のルールではなく、「個人の感じ方」を重視する必要があります。

最後に、研究チームは次のように述べています。
「音楽は、ADHDのある若者にとって、感情の調整や覚醒の維持といった点で、薬とは異なる『セルフ・レギュレーション』の手段となっている可能性があります。
BGMの使い方や音楽の選び方には個人差が大きいため、それを尊重しつつ、より効果的な支援の一部として活用する道が開けるかもしれません」
たしかに、「勉強中に音楽を流していると集中できないからやめなさい」という言葉は、子どもの頃に多くの人が聞いたことがあるかもしれません。
しかし、ADHDのある人にとっては、それが逆効果になることもあるのです。
音楽の感じ方、使い方は、人それぞれです。
「この人はなぜいつも音楽を流しているのだろう?」と感じたとき、そこには深い理由があるかもしれません。
音楽が持つ力を、もっと多様な視点から見つめ直していくこと。それは、神経発達症という「見えにくい特性」を理解する一歩になるのではないでしょうか。
(出典:Frontiers DOI: 10.3389/fpsyg.2024.1508181)(画像:たーとるうぃず)
「勉強中に音楽を流していると集中できないからやめなさい」
それは、ADHDのある人にとっては、それが逆効果になることもある。
正しく認識してください。すごく重要です。邪魔しないでください。
(チャーリー)