
この記事が含む Q&A
- 自閉症の診断で「欠けている部分」だけでなく「強み」を重視するアセスメントとは何ですか?
- 強みに基づく神経心理学的アセスメントで、記憶力や独自の視点、細部へのこだわりなどを積極的に評価し、診断説明も肯定的な言葉で行う方法です。
- このアセスメントの参加者の反応はどうでしたか?
- 多くの参加者が楽しかった・安心できたと感じ、自己理解を深める機会になったと報告されています。
- 今後の課題と改善点は何ですか?
- 長時間の検査での疲労、環境が感覚的に合わない点、情報量の多さ、診断後の継続的支援の不足が挙げられ、資料の事前提供や複数回セッションなどの改善が提案されています。
自閉症の診断といえば、これまでは「どのように社会的に困難があるか」「行動がどれほど制限されているか」といった「欠けている部分」を明らかにすることに重点が置かれてきました。
しかし、それが本人にとって本当に役立つのかという疑問が近年強くなっています。
オーストラリアの私立精神医療機関であるザ・メルボルンクリニック(The Melbourne Clinic)の研究チームは、その常識を大きく覆す試みを行いました。
それが「強みに基づいた神経心理学的アセスメント」です。
この研究では、入院中の成人患者で新たに自閉症と診断された10人を対象に、従来の「欠損モデル」ではなく「強み」に焦点を当てた評価を行い、その体験がどのように受け止められたかを詳細に記録しました。
背景には、国際的に用いられているDSM-5やICD-11といった診断基準の問題があります。
そこでは自閉症の特徴が「持続する欠如」「制限された行動」といった否定的な言葉で記述されます。
本来なら「細部への強いこだわり」や「情報を徹底的に収集して記憶する力」は、大きな強みとして活かせる可能性がありますが、診断基準の文言では「異常な興味」として病理化されてしまうのです。
そのため、診断を受けた人は「困難さ」だけでなく「強み」までもが否定的に扱われるという二重の苦しみを味わうことになりがちでした。
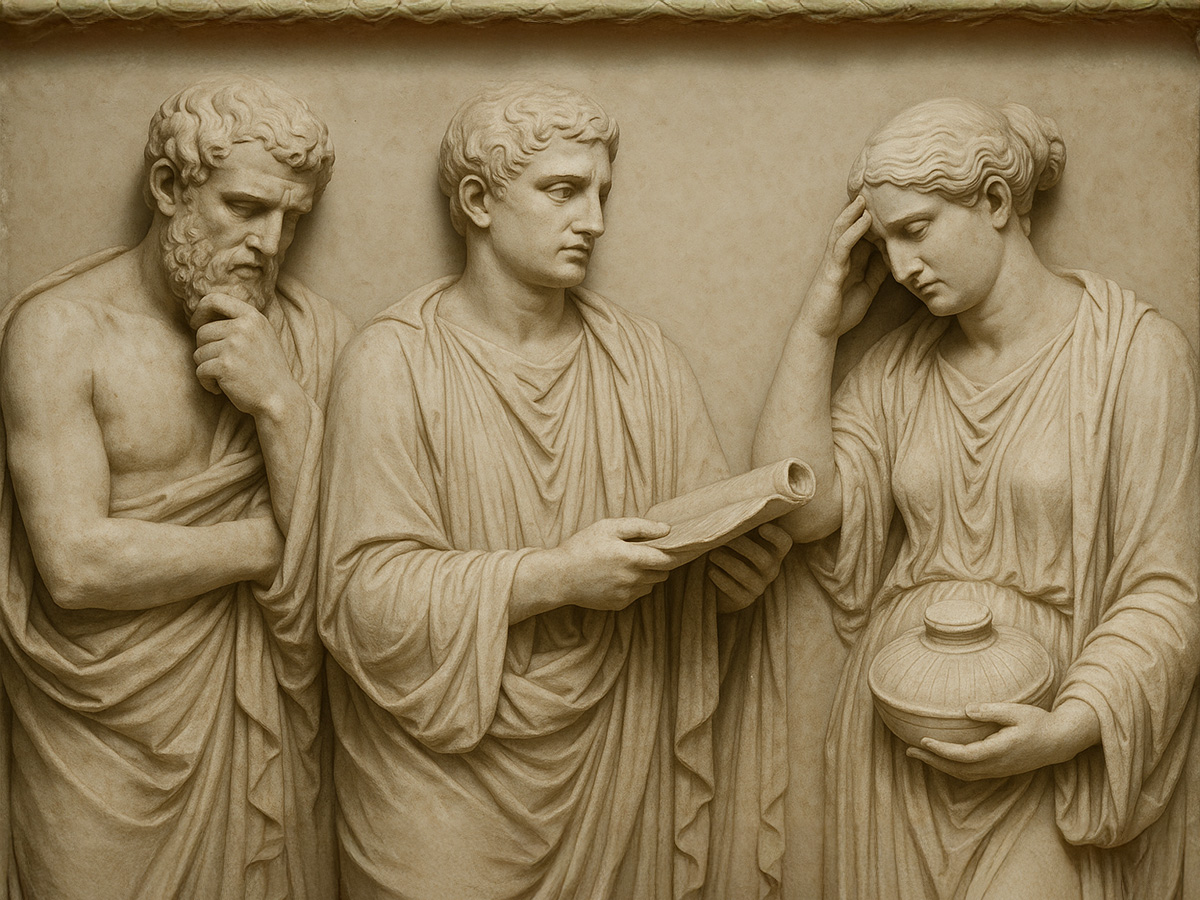
このような状況に対して、自閉症の人々や研究者が提唱してきたのが「ニューロダイバーシティ」という考え方です。
これは脳や認知の多様性を人間の自然なバリエーションとして肯定的に捉えるもので、特性を障害としてのみ定義するのではなく、その人ならではの強みや可能性を認めていこうという姿勢を持ちます。
今回の研究では、神経心理学的評価の方法そのものを「強みに基づいたもの」として設計しました。
具体的には、臨床家が検査や面接の場で、参加者の記憶力、独自の視点、細部に注意を払う力などを積極的に評価し、診断を説明する際も肯定的な言葉を用いました。
たとえば「日課に強くこだわる」という特徴について、従来の診断書では「柔軟性がなく、予定が変わると混乱する」と否定的に書かれてきましたが、この研究では「予定を立てることで安心し、生産性を高められる」と表現しました。
制度上の理由から保険申請に必要な正式な診断書では従来の否定的な表現を避けられない場合もありましたが、本人に渡されるフィードバック資料は常にニューロダイバーシティに基づいた前向きな言葉で書かれていました。
そして、その違いについても丁寧に説明する時間が設けられました。
調査に参加した10人は、平均32歳、20歳から52歳までの幅広い年代にわたり、全員が既に複数の精神的困難を抱えて入院していました。
中にはうつや不安障害、トラウマ関連症状をもつ人も多く、ADHDを併せて診断された人もいました。
それでも、この「強みに基づくアセスメント」はおおむね好意的に受け止められました。
多くの参加者は「楽しかった」「安心できた」と感想を語り、臨床家の態度を「優しく、説明がわかりやすく、非評価的」と高く評価しました。
検査の課題そのものを「刺激的で面白かった」と表現する人もおり、診断の過程が自己理解を深めるきっかけになったと述べる人もいました。
ある参加者は「自分の特性を祝福する時間のようだった」と語っています。

この研究で明らかになったのは、診断が本人にとって「自分を見直す旅」になり得るということです。
診断を受けて安心感を得た人もいれば、「もっと早く知っていれば」と悔しさを感じた人もいました。
いずれにせよ、自閉症という言葉を自分に当てはめることで、過去の経験を新たな視点で整理し直し、理解できるようになったと多くの人が語りました。
診断後には「同じ自閉症の人と話すことが助けになった」「性差について説明を受けたことで納得できた」といった声もありました。
一方で、改善点も見えてきました。
長時間の検査で疲労を感じた、照明や音など環境が感覚的に合わなかった、主治医からの診断後のサポートが十分でなかった、という指摘もありました。
フィードバックの場面では「情報が多すぎて一度では理解できない」「もっとシンプルで視覚的な資料が欲しい」という意見が寄せられました。
さらに「退院が迫っていて追加のフィードバックセッションが受けられなかった」という声もあり、今後は複数回のセッションを標準に組み込む必要性が示されました。
また、診断後の継続的な支援が不足していることも課題として浮かび上がりました。
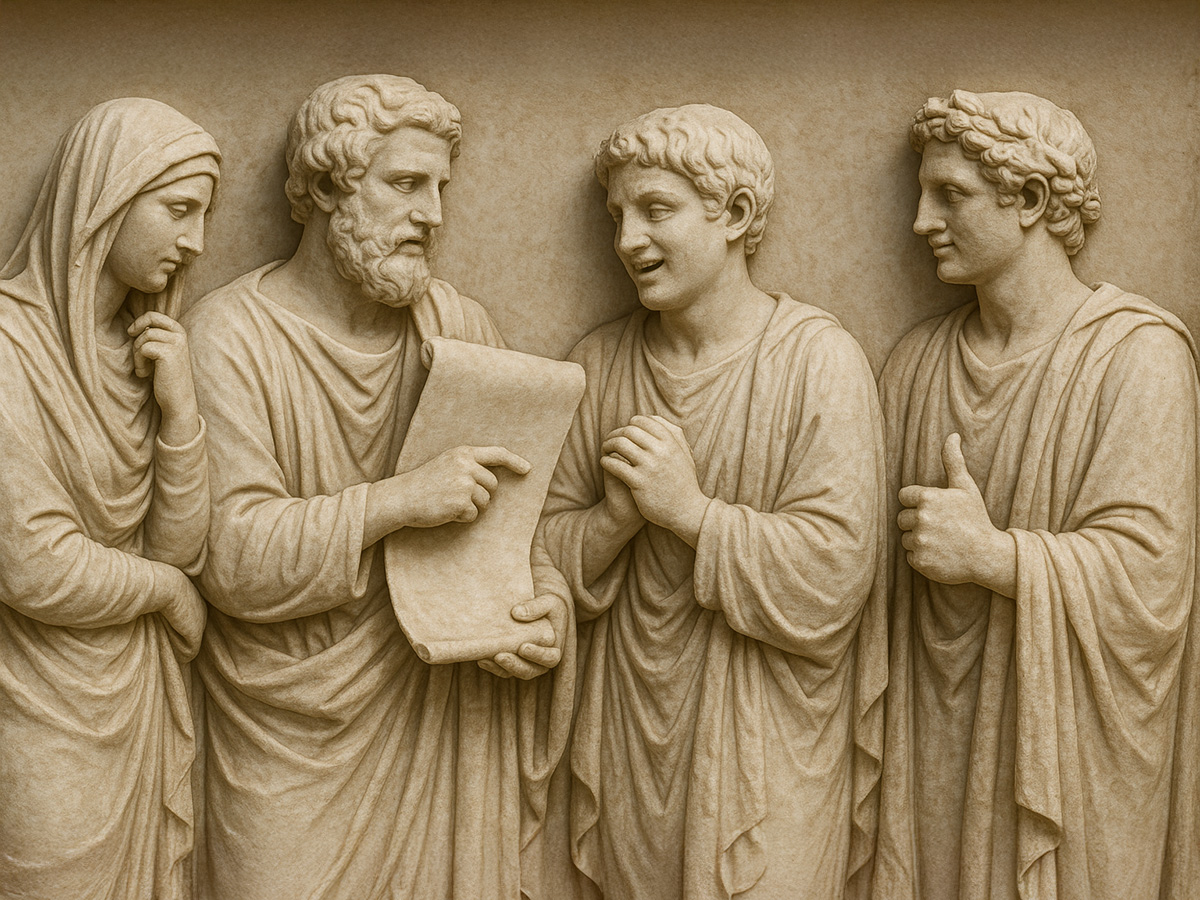
研究チームは、こうした参加者の声をもとに、今後の改善策を具体的に提案しています。
たとえば、事前にわかりやすい説明資料を配布すること、感覚的な配慮を徹底すること、疲労や注意力に応じてセッションを調整すること、そして診断後には必ず追加の支援や教育的なグループ活動につなげることなどです。
ニューロダイバーシティの考え方を共有し、強みを正しく評価することが、本人の自己肯定感や将来への見通しに直結することが示されました。
この研究は、従来の「できないこと探し」の診断から「強みを見つける診断」への大きな転換点を示しています。
診断は単なるラベル付けではなく、自分を理解し、新しい一歩を踏み出すきっかけになるのです。
ザ・メルボルンクリニックの取り組みは、今後の自閉症診断のあり方に重要な示唆を与えています。
もしこうした方法が広がれば、多くの人が「自分はこのままでよい」と感じられる診断を受けられるようになるでしょう。
(出典:Journal of Autism and Developmental Disorders DOI: 10.1007/s10803-025-06967-w)(画像:たーとるうぃず)
コップの中にある水を見て、
「半分しかない」
「半分もある」
事実は一つでも、理解は何通りもあります。
そして、ポジティブに捉えることが、幸せを感じる、幸せになる行動へつながります。
であれば、「強み」と捉えて、大事にし伸ばしていくべきだと私は思います。
(チャーリー)





























