
この記事が含む Q&A
- 自閉症の成人は「直感的な見覚え」よりも「どこで、どんなふうに見たか」という具体的な思い出し方を頼る傾向があるのでしょうか?
- はい、研究ではその傾向が認められ、時間をかけて詳しく思い出す方法を用いることが多いと示されています。
- 定型発達の成人はまず直感的な見覚えを使い、そのあとで細部を確認する二段階の戦略を取るとされていますが、具体的にはどういう順序ですか?
- まず直感で「ある/ない」を判断し、次に細部を照合して確かめます。
- 学習や支援の現場で効果が期待される工夫は何ですか?
- 意味を持たせて覚える概念的学習と、見た目の特徴を丁寧に観察する知覚的学習を組み合わせると、後の思い出しがしやすくなる可能性があります。
自閉症の人は、物を覚えているかどうかを確かめるときに、少し独特なやり方をしているかもしれません。
ドイツやポルトガル、スペインの大学や研究機関のチームは、「思い出すときに脳の中でどんなことが起きているのか」を詳しく調べました。
その結果、
自閉症の成人は「なんとなく見覚えがある」という直感的な手がかりよりも、「どこで、どんなふうに見たのか」という具体的な思い出し方に頼っていることがわかりました。
一方で、定型発達(自閉症でない人)の成人は、まずは直感的に「見たことがあるかないか」を素早く判断し、そのあとで細かい部分を確認する傾向がありました。
興味深いのは、どちらのやり方でも最終的な正確さは大きく変わらなかったという点です。
違っていたのは、同じ答えにたどり着くまでの“道筋”でした。
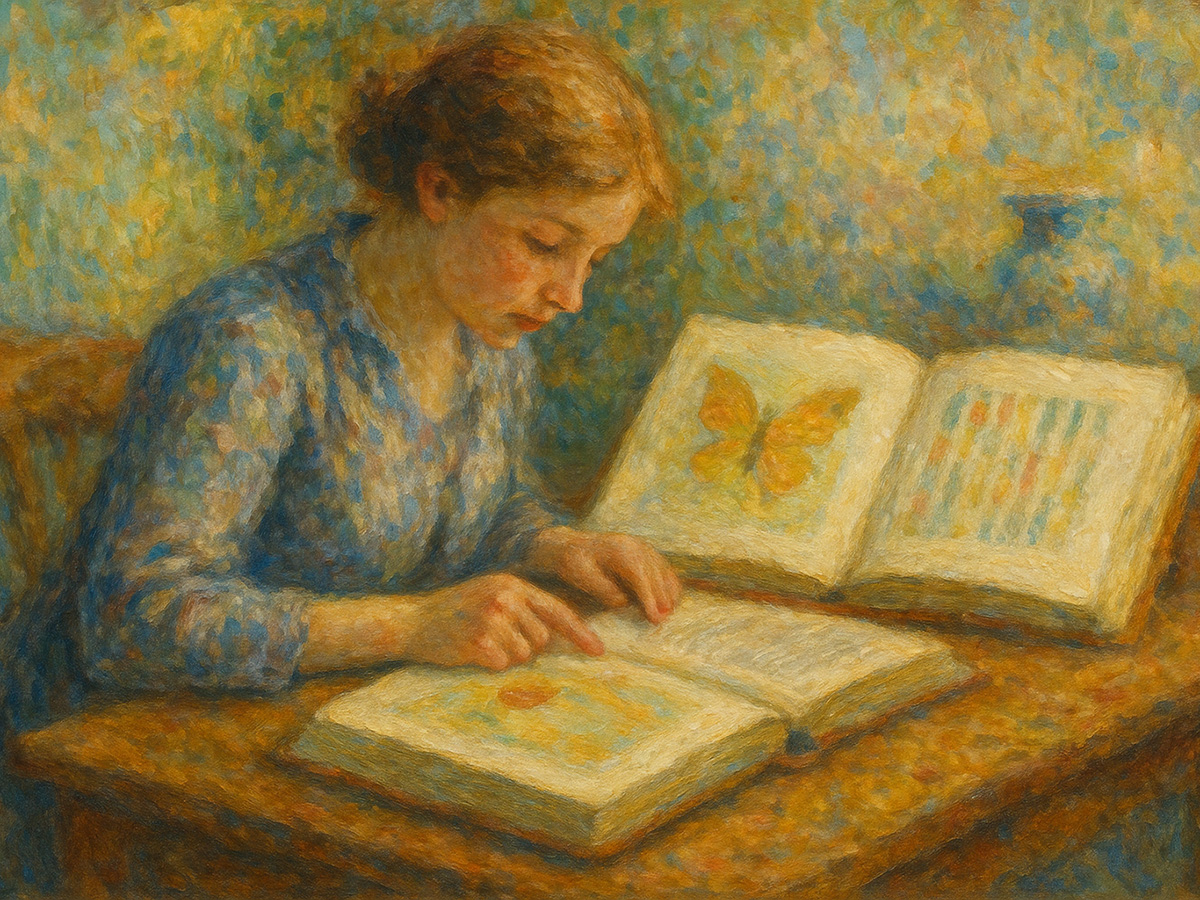
この研究の方法はとても丁寧に設計されていました。
まず、参加者は成人男性で、自閉症の診断があるグループと、そうでない定型発達のグループに分けられました。
研究者たちは参加者に日常で見かけるような物の写真を見せました。
たとえば、鳥や道具など、誰でも知っている身近な物です。
ただし工夫があり、同じ種類の中でも「よくある典型的な物(例えばスズメのような鳥)」と「少しめずらしい非典型的な物(例えばダチョウのような鳥)」を混ぜました。
これは、人間の記憶において「当たり前の物」と「予想外の物」とで覚えやすさが違うことが知られているためです。
学習段階では、参加者に二通りの課題が与えられました。
ひとつは「意味を考えて覚える」方法で、たとえば「これはどの種類に分類できるか」といった問いに答えながら物を見るやり方です。
これを研究では「概念的な学習」と呼びます。
もうひとつは「見た目に注目して覚える」方法で、「線が何本あるか」「色はいくつあるか」といった細部に注意を向けながら見るやり方です。
これを「知覚的な学習」と呼びます。
意味を考えるか、形や色のような見た目に注目するか、その違いが後の記憶にどう影響するのかを確かめるためでした。
学習が終わったあと、しばらく時間を置いてからテストが行われました。
参加者には、新しい写真と、先ほど学習した写真がランダムに提示され、「これは前に見たことがあるか」を答えてもらいました。
これを「旧新判断」といいます。
単に「はい」「いいえ」と答えるだけではなく、さらに「はっきり思い出せる(リメンバー)」「見覚えがある(ノウ)」「多分そうだと思う(ゲス)」という主観的な判断も続けて答えてもらいました。
ここで使われたリメンバー、ノウ、ゲスは記憶研究でよく使われる方法で、人が「どんな感覚で思い出しているのか」を細かく区別するための言葉です。
さらに、脳の活動を調べるために脳波を測定しました。
これは頭に小さな電極をつけ、脳の中で流れる電気の動きをミリ秒単位で記録する方法です。
研究者たちは特に「刺激を見てから300〜500ミリ秒」「500〜800ミリ秒」「900〜1500ミリ秒」という時間帯に注目しました。
それぞれが異なる記憶の過程と結びついていると考えられており、最初の300〜500ミリ秒は直感的な「親近感」、次の500〜800ミリ秒は「具体的な思い出し」、そして900〜1500ミリ秒は「答えを確認するための見直し」に関係があるとされています。

こうして得られた結果には、大きく三つの特徴がありました。
第一に、めずらしい物(非典型)ほど覚えやすく、意味を考えながら覚えたとき(概念的な学習)のほうが成績が良いことがわかりました。
これは「予想外の物は記憶に残りやすい」「意味づけして覚えると取り出しやすい」という人間の一般的な記憶の特徴と一致します。
第二に、自閉症でない成人は「直感的な見覚え」を早い段階で使い、そのあとに「細かい部分を確認する作業」を追加する戦略をとっていました。
つまり「まずは直感で答える」→「あとで確かめる」という二段階の方法です。
第三に、自閉症の成人はその逆で、最初から「丁寧に思い出す」方法を使っていました。
直感的な判断にはあまり頼らず、細かい部分を思い出すことを優先しているのです。
そのため、反応時間は少し長くなりますが、決して思い出せないのではなく、「時間をかけて確かめながら思い出している」という特徴だと考えられます。
この違いは、勉強や支援の場面にも大きな意味があります。
自閉症の人は、急がされるよりも、落ち着いて時間をかけて思い出すほうが力を発揮しやすい可能性があります。
学習の段階でも「意味を持たせて覚える」やり方や「見た目を丁寧に観察する」やり方をうまく取り入れると、後で思い出しやすくなると考えられます。
また、テストや評価の場面でも「一瞬で答えなければならない問題」ばかりではなく、「思い出す時間をかけてもよい問題」を混ぜることで、公平に力を見ることができるかもしれません。
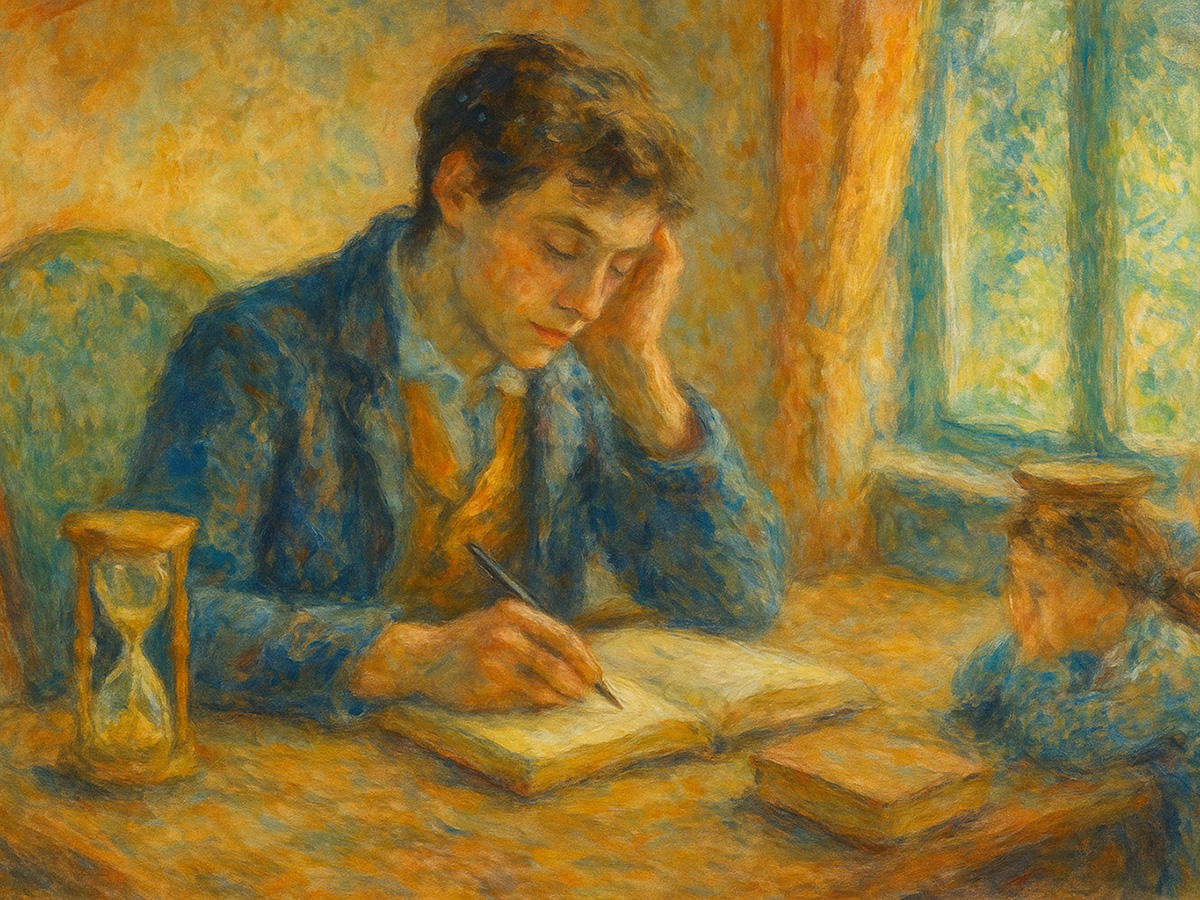
もちろん、この研究には限界もあります。
参加者は男性の成人に絞られており、女性や子どもでも同じ結果になるかどうかはまだわかりません。
また、一部の脳波の結果は「傾向」が見られた段階にとどまっており、より大きな人数での検証が必要です。
それでも、「自閉症の人も定型発達の人も、最終的には同じように正確に覚えている。ただし、そのために使っているやり方が違う」という点は明確に示されました。
違いは欠点ではなく「別の戦略」だと示すこの研究は、学びや生活を支えるうえで大切なヒントを与えてくれるものです。
(出典:Nature scientific reports DOI: 10.1038/s41598-025-19086-4)(画像:たーとるうぃず)
「違うから」こそ、記憶においても頼りにできるときもあるでしょう。
(チャーリー)





























