
この記事が含む Q&A
- 早産とASDにはどんな関係があるのですか?
- 早産はASDの診断される確率を2〜4倍高くし、週数が短いほど影響が大きいが、原因というより重さを増す環境要因として説明されています。
- 遺伝と早産の関係はどのように説明されていますか?
- ASDの人の早産と正期産を比べてもデノボ変異の数には大きな差はないが、早産のASD児では神経発達関連遺伝子の変化が多く見られ、性別が影響する場合もあります。
- 早期支援の実践的なポイントは何ですか?
- 出生時の遺伝情報を用いた健康チェックを進め、早期に環境を整える支援を行うことでASDの早期発見と介入につながる可能性があります。
自閉スペクトラム症(ASD)は、生まれつきの脳の発達の違いによって、周囲とのやりとりやことばの使い方、興味の持ち方などに特徴があらわれる発達のあり方です。
人によってその表れ方はさまざまで、困りごとが少ない人もいれば、日常生活に大きな支援が必要な人もいます。
また、ASDの人の多くは、注意の集中が続きにくい、眠りにくい、体の動かし方がぎこちないなど、いくつかの違いをあわせもつことがあります。
ASDの原因はひとつではありません。
研究では、親から受け継ぐ体の設計図のちがい、つまり「遺伝的な要因」が大きな役割をもっていることが分かっています。
その割合は全体の8〜9割にもなると考えられています。
ただし、遺伝だけで決まるわけではなく、「生まれる前や生まれるときの環境」も関係していることが知られています。
その中でもとくに強く関係しているのが「早産」です。
早産とは、妊娠37週より前に生まれることをいいます。
これまでの調査では、早産の子どもがASDと診断される確率は、正期産(37週以降)で生まれた子どもに比べておよそ2〜4倍高いと報告されています。
しかも、より早く生まれたほどその確率は高くなります。
しかし、なぜそうなるのか、その理由ははっきりしていません。
生まれる週数が短いことが脳の発達に影響を与えるのか、それとももともとの遺伝的な体質が関係しているのか。
あるいはその両方なのか。これまでの研究では、その境界があいまいなままでした。
スウェーデンのカロリンスカ研究所のチームは、この問題を詳しく調べるために、アメリカの大規模な自閉症研究データ「SPARK」と「Simons Simplex Collection」という2つの資料を使いました。
合わせて7万8千人以上のデータを解析し、そのうち遺伝子の情報が得られたのは約1万2千人でした。
つまり、ASDの特徴と、遺伝、そして早産という3つの要素を同時に分析した、これまでで最大級の研究のひとつです。
研究ではまず、ASDをもつ早産の人と、同じくASDだが正期産で生まれた人を比べました。
その結果、早産で生まれたASDの人は、正期産のASDの人よりも、医療的な問題を多く抱えていることがわかりました。
発達、行動、感情、成長、食事、睡眠、神経系、感覚(視覚や聴覚)など、9つの分野で調べたところ、すべての項目で早産の人の方が高い割合で問題を経験していました。
とくに、生まれつきの体の小ささや、成長の遅れなどが目立ちました。
また、ひとりの人が複数の困りごとを同時にもつ割合(多重の併存症)も高く、5種類以上の診断をもつケースが正期産のASDの人よりも明らかに多くなっていました。
つまり、早産で生まれたASDの人ほど、症状が重く、いくつもの分野に影響が出やすいということです。

次に、早産の中でも週数ごとの違いを調べました。妊娠28週より前に生まれる「極早産」、31週までの「超早産」、33週までの「中等度早産」、そして36週までの「後期早産」という分類です。
結果ははっきりしていました。
週数が短いほど、発達や感覚の問題が多く、成績や発達検査のスコアも低くなっていました。
とくに「体の動かし方の協調性」や「社会的なやりとりのスムーズさ」「くり返し行動の強さ」「知的な発達」の面でその差が顕著でした。
一方で、同じ早産でも、ASDのある人とない人を比べると、ASDのある人のほうがずっと多くの困りごとを抱えていました。
発達に関する問題をもつ割合は72%にのぼり、5種類以上の診断をもつ確率は7倍に達しました。
これらの結果は、ASDと早産の両方が重なることで、より重い影響が出ることを示しています。
ここで研究チームは疑問を持ちました。「遺伝の違い」がこの重さの差を生んでいるのではないか、と。
そこで彼らは遺伝子の中身を詳しく比較しました。
遺伝子の中には、まれに親からは受け継がれず「突然変異」として新しく現れる部分があります。
これを「デ・ノボ変異」と呼びます。
こうした変異が脳の働きに関わる遺伝子に起きると、ASDのような発達の違いにつながることがあります。
しかし調べてみると、ASDである早産の人と正期産の人のあいだで、この「突然変異」の数には大きな差がありませんでした。
つまり、「ASDの人が早産だからといって、特別に遺伝子の変化が多いわけではない」ということです。
ところが、ASDをもつ早産の人と、ASDではない早産の人を比べると、前者では神経の発達に関わる遺伝子に変化が多く見つかりました。
これは「早産の中でASDになるかどうか」は、やはり遺伝の一部が影響している可能性を示しています。
また、「ポリジェニックリスクスコア(PRS)」という、たくさんの遺伝子のわずかな違いを足し合わせて計算した「ASDになりやすさの指標」も調べました。
その結果、早産かどうかでPRSの平均値にはほとんど差がありませんでした。
つまり、遺伝的なASDのなりやすさ自体は、早産によって増えるわけではないということです。

ただし、ここに「性別」を加えると話が変わりました。
男の子で、しかもこのPRSが高い早産児は、ASDと診断される確率が非常に高かったのです。
モデルの計算では、その確率は最大でおよそ90%に達しました。
これは、「生まれつきのリスク(遺伝)」「生まれる時期(早産)」「性別」という3つの要因が重なったときに、ASDがよりはっきりとあらわれやすくなることを示しています。
研究チームはさらに、出生の時点で得られる情報だけから、ASDになる可能性をどの程度予測できるかも試しました。
使ったのは「機械学習」という方法で、コンピュータに大量のデータを学ばせ、パターンを見つける技術です。
性別、生まれた週数、出生時の合併症、酸素不足の有無、そして遺伝情報を組み合わせて、ASDかどうかを分類するモデルを作りました。
このモデルは完全な正確さではありませんが、69%の確率で正しい結果を出しました。
とくに「性別」「遺伝的リスク」「遺伝子の変化の強さ」が最も影響の大きい要素でした。
男の子で、生まれる週が短く、出生時に呼吸のトラブルがあり、遺伝的な変化が多い場合には、ASDになる確率が高まるという傾向が見られました。
この研究の大きな発見は、「早産そのものがASDの原因ではないが、ASDの症状を重くし、併存症を増やす環境的な要因になっている」という点です。
遺伝的な要素が同じでも、早く生まれることで脳の発達に影響が出やすくなり、結果としてASDの特性が強く表れるのです。
とくに妊娠後期は脳の神経が急速に増える時期であり、その前に生まれることは、脳の左右差や神経回路の形成に影響する可能性があります。
新生児の時点での脳の発達の差が、後の発達の特徴としてあらわれるのかもしれません。
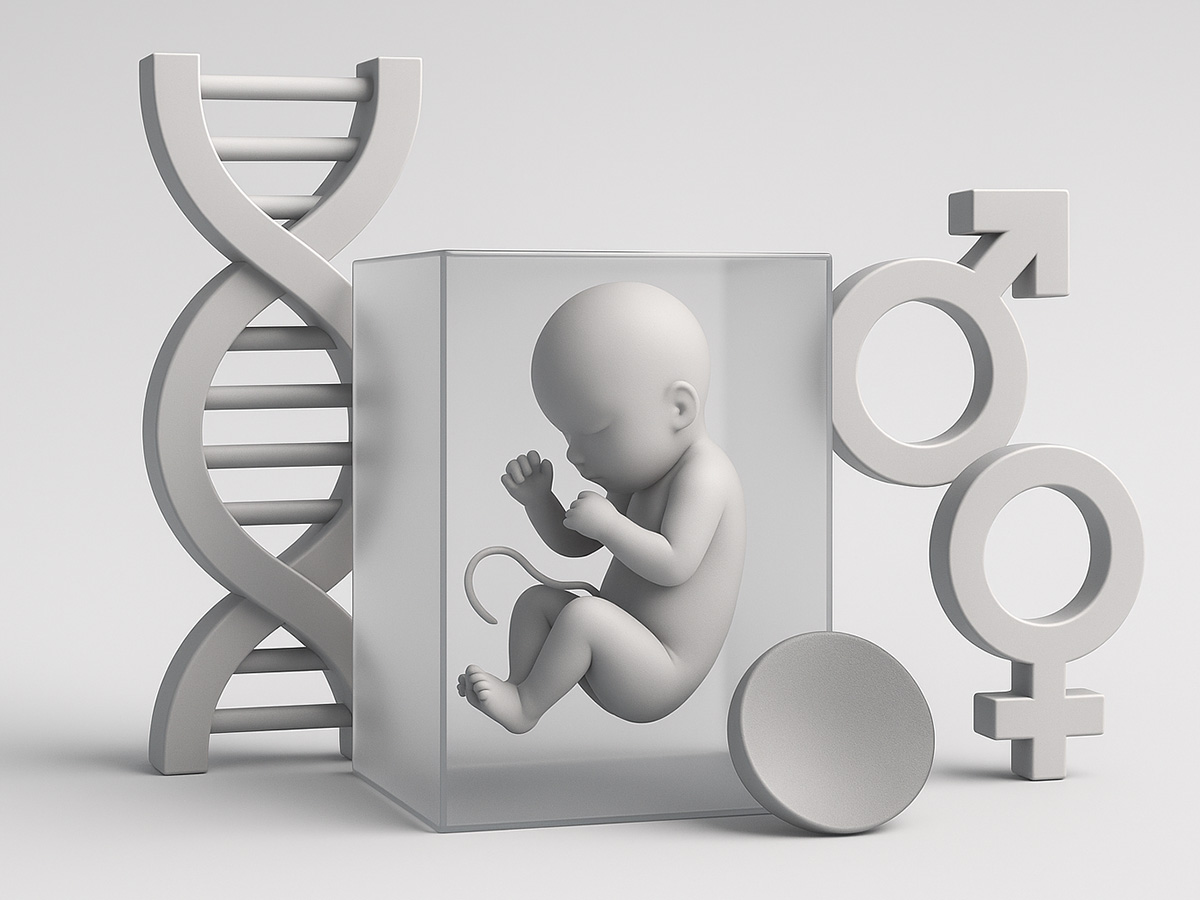
研究チームはまた、「出生直後から遺伝情報を取り入れた健康チェックを行うこと」が今後の重要な課題になると述べています。ASDは通常、1〜2歳以降の行動観察によって診断されますが、もし出生時の情報である程度のリスクを推定できれば、支援をずっと早く始めることができます。
早期に環境を整えることが、発達に良い影響をもたらすことは多くの研究で確かめられています。
この研究にはいくつかの限界もあります。
解析の対象となったデータはASDに特化したものであり、比較対象となる非ASDの人たちは主に兄弟姉妹でした。
そのため、遺伝的な違いが少なく見えている可能性があります。
また、母親の体の遺伝的要因は調べられていません。
母親側の遺伝も早産には関わることが知られているため、今後は両方をあわせた研究が必要です。
さらに、極めて早い週で生まれた人のデータが少なかったため、この部分の理解はまだ途中です。
それでも、この研究は非常に大きな意味を持ちます。
ASDを「遺伝か環境か」で分けて考えるのではなく、「両方がどのように重なって影響するのか」を初めて大規模に示したのです。
ASDの遺伝的な要素は、早産でも変わらない。
しかし、早産という出来事がASDの出方を変え、症状を重くしやすい。そして男の子では、その影響がより強くあらわれる。
研究チームはこう結論づけています。
「早産で生まれた子どもたちの健康チェックには、遺伝の情報も取り入れるべきです。
それによって、ASDの早期発見と支援の手がかりが得られるでしょう」
(出典:Genom Medicine DOI: 10.1186/s13073-025-01552-3)(画像:たーとるうぃず)
かかえる困難の軽減につながる早期支援につながることを願っています。
(チャーリー)





























