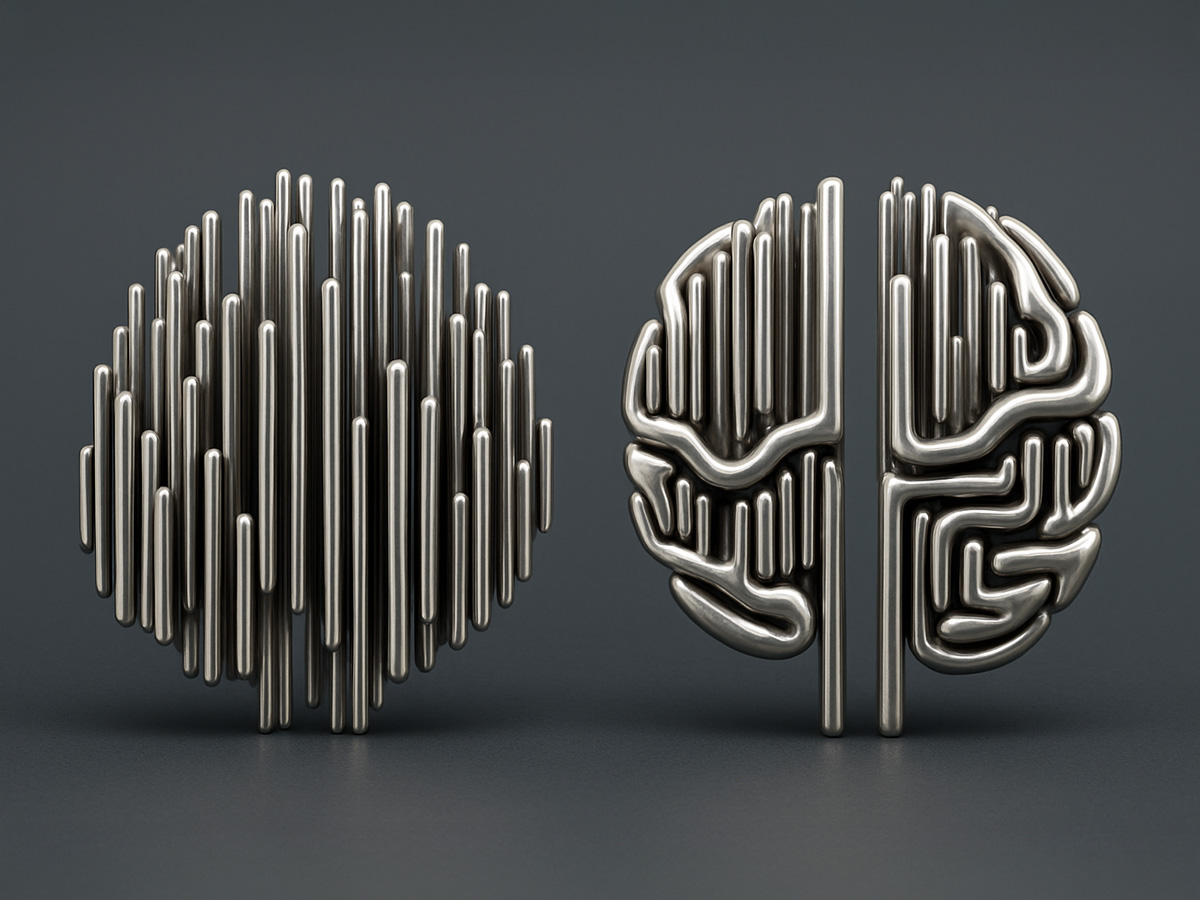
この記事が含む Q&A
- 自閉スペクトラム症(ASD)の脳の特徴は何によって分類できるのですか?
- 脳の構造的な特徴と「ASDらしさスコア」に基づいてサブグループに分けられます。
- ASDの異なるサブグループはどのような脳の違いがありますか?
- ASD-High群は脳梁膨大部の体積が小さく、皮質の厚みや面積も狭い傾向があります。
- 脳の構造の違いは支援方法にどのような影響を与える可能性がありますか?
- 構造的変化が顕著なタイプには認知トレーニング、軽度なタイプには環境調整や社会スキル支援が適していると考えられます。
自閉スペクトラム症の子どもや大人たちは、日常生活の中でさまざまな困難に直面しています。
しかしその一方で、脳の中で何が起きているのかという問いに対しては、これまでに多くの研究がなされてきましたが、明確な答えは得られていません。
なぜなら、自閉スペクトラム症(ASD)の特徴は人によって大きく異なり、それが脳の構造にもさまざまな違いとして現れるためです。
今回の研究は、最新の国際共同研究による成果です。
この研究では、アメリカと中国という異なる文化圏における2つの大規模なASD脳画像データベースを活用し、自閉スペクトラム症の人たちの脳形態を詳しく調べました。
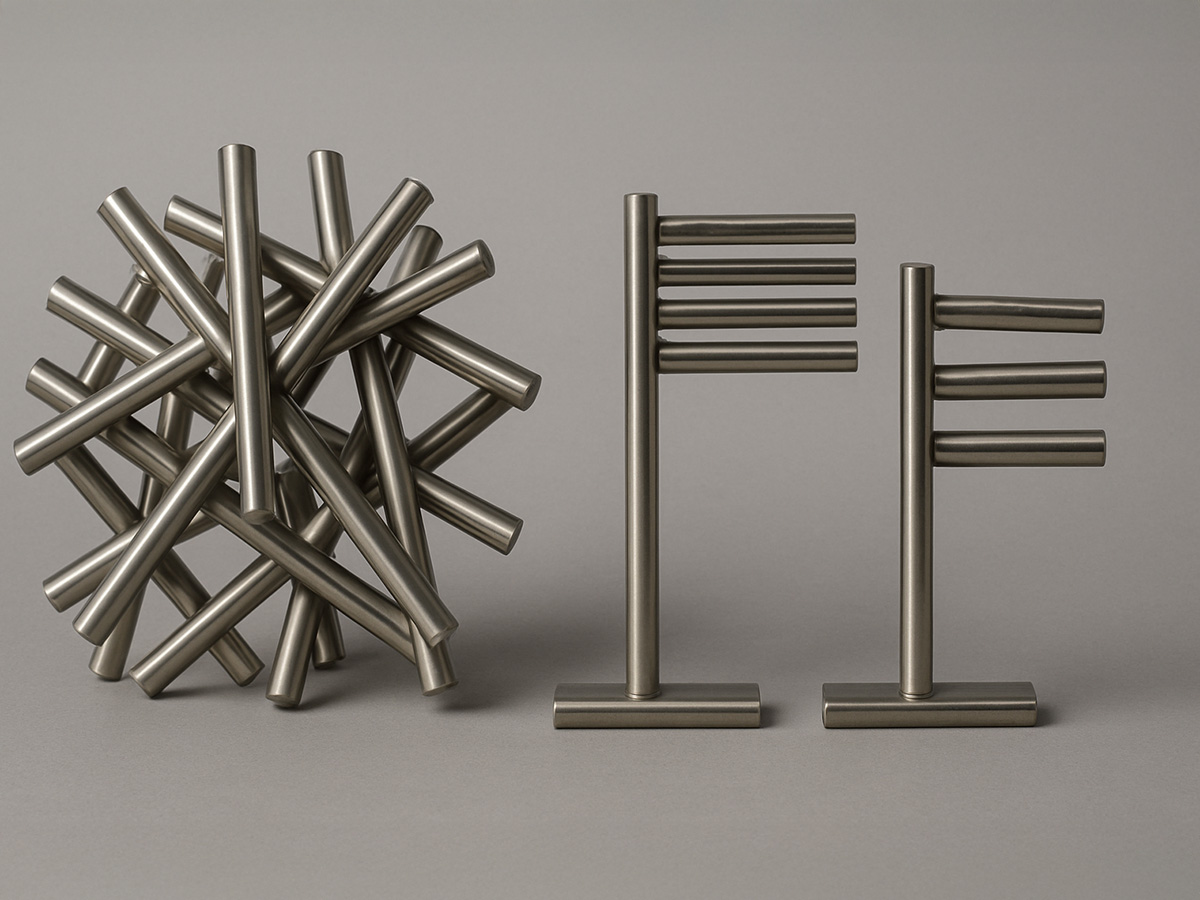
その結果、ASDは単一の脳構造的な特徴によって説明されるのではなく、複数の異なる脳の特徴パターンを持つ「サブグループ」に分かれる可能性があることがわかってきたのです。
研究に使われたデータは、ENIGMA-ASDとCHARGE-Autismという2つのコンソーシアムから得られたもので、合計2,400人以上のASD当事者と、3,300人以上の非ASDの比較対象者の脳画像が含まれています。
年齢層は4歳から64歳までと幅広く、MRI(磁気共鳴画像法)によって測定された脳の体積、厚み、面積などのデータをもとに分析が行われました。
研究チームは、機械学習を活用してこれらの脳画像から「個人ごとのASDらしさスコア(ASD-Likelihood Score)」を算出しました。
このスコアは、ある人の脳の形がどれくらいASD的な特徴を持っているかを示すもので、スコアが高いほどASDに特有の脳パターンに近いと判断されます。
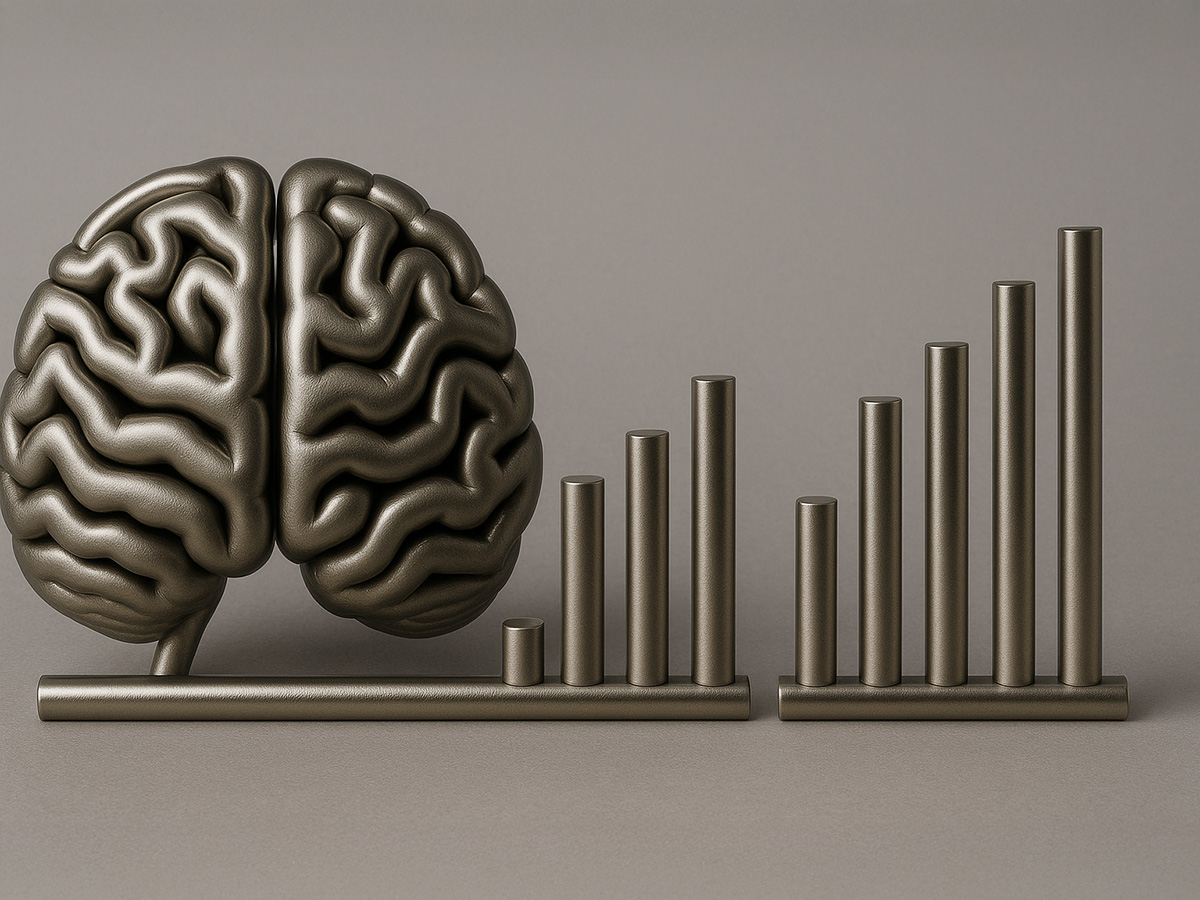
このスコアに基づいて、ASD当事者を2つのサブグループに分けました。
ひとつは「ASD-Low群」、もうひとつは「ASD-High群」です。
これら2つのグループは、ASDの診断は共通していますが、脳の形には大きな違いが見られました。
ASD-High群は、脳の中でも「脳梁膨大部(イストマス・シンギュレート)」という領域の体積がとくに小さい傾向がありました。
この領域は、自己意識や社会的情報の処理に関係すると考えられており、社会的なやりとりや感情の理解に困難を抱えるASDの特性との関連が注目されます。さらにこのグループでは、全体として脳の皮質(コルテックス)の厚みが薄く、面積が小さい傾向も見られました。
一方、ASD-Low群では、こうした著しい脳の特徴は見られませんでした。これは、同じASDと診断されていても、脳の構造的な「ASDらしさ」には大きな個人差があることを意味します。
また、ASD-High群では、脳のさまざまな領域同士の構造的なつながり方(これを「構造的共変動」といいます)にも、非ASD群とは異なるパターンが見られました。
とくに、前頭葉や頭頂葉といった高次の認知にかかわる領域間の共変動が減少しており、情報の統合処理に影響がある可能性が示唆されます。
さらに興味深いのは、ASD-High群の人たちは、自閉スペクトラム症の重症度を示す行動的な指標とも強く関連していたという点です。
たとえば、社会的な反応の少なさや、こだわり行動の強さといったスコアが高い傾向にありました。
これに対して、ASD-Low群ではそうした傾向は弱く、行動面でも比較的穏やかな特徴を示していました。
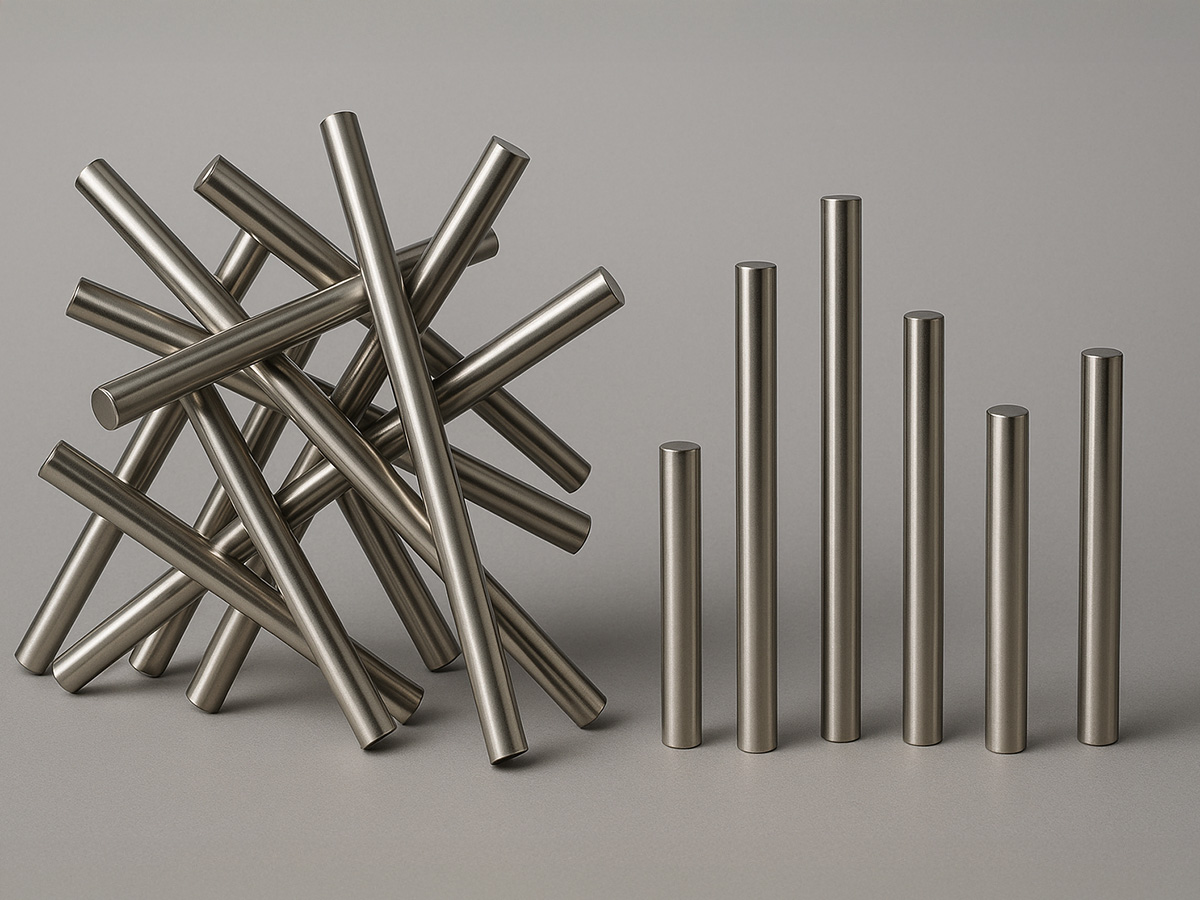
このように、ASDという診断ラベルの背後には、脳の構造における「異なるタイプ」が存在する可能性があることが明らかになったのです。
研究チームは、これを「神経形態的サブタイプ(Neuroanatomical Subtypes)」と呼んでいます。
今回の研究は、アメリカと中国という異なる文化背景においても、こうしたサブタイプの存在が共通して観察されたという点でも重要です。つまり、ASDの多様性は文化や環境によってのみ説明されるのではなく、脳そのものの構造にも深く根ざした現象だといえるのです。
また、年齢にともなう脳の変化についても注目すべき結果がありました。とくにASD-High群では、脳の面積や厚みの減少が青年期から中年期にかけて急速に進む傾向がありました。このことは、年齢とともにASDの困難が強まったり、逆に弱まったりする現象の背後に、脳の発達や変化が関係している可能性を示唆しています。
一方で、ASD-Low群ではこのような急激な変化は見られず、年齢にともなう脳の構造変化はより緩やかでした。これは、ASDの中でも特に支援の必要度が異なるグループがあることを意味するかもしれません。
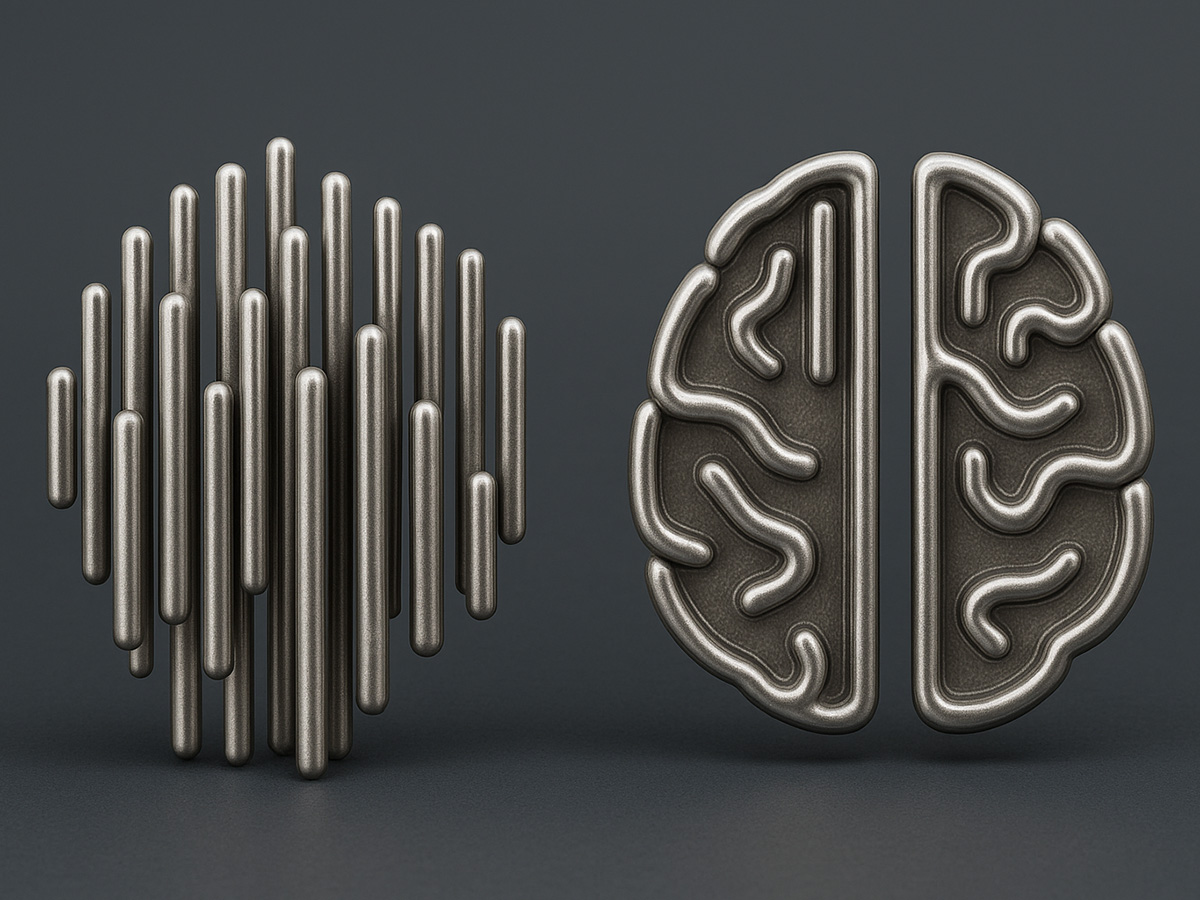
研究者たちは、この知見をもとに、将来的にはASDの診断や支援方法がより「個別化」されていく可能性があると述べています。
たとえば、ASD-High群のように顕著な脳の構造的変化が見られる人には、認知トレーニングや神経可塑性に着目したアプローチが効果的かもしれません。
一方、ASD-Low群のように行動面では困難があっても、脳の形に大きな特徴が見られない人に対しては、環境調整や社会的スキルの学習などの支援がより適している可能性があります。
また、こうした分類は、治療薬の研究においても重要な意味を持ちます。
あるサブタイプには薬の効果があるが、別のタイプでは効果がないといった差異が存在する可能性があるからです。
ASDのバイオマーカー開発においても、こうしたサブタイプの理解は大きな手がかりとなるでしょう。
本研究の成果は、自閉スペクトラム症が「ひとつのかたち」ではなく、「さまざまなかたち」を持つ脳のあり方の集まりであるという理解を、より明確なかたちで支持するものです。
そしてそれは、「その人らしさ」に寄り添う支援のあり方を見直すきっかけにもなるかもしれません。
「ASDらしさ」は、外から見える行動だけではなく、内側の脳のかたちにもいろいろなバリエーションがあるのです。
研究はまだ始まったばかりですが、この多様性を尊重したアプローチが、よりよい支援と理解の道をひらいていくことが期待されています。
(出典:Nature DOI: 10.1038/s42003-025-08573-z)(画像:たーとるうぃず)
広い範囲で捉えている、現在の自閉スペクトラム症での困難をより効率よく軽減していくためには、こうした細分化は求められるものでしょう。
(チャーリー)





























