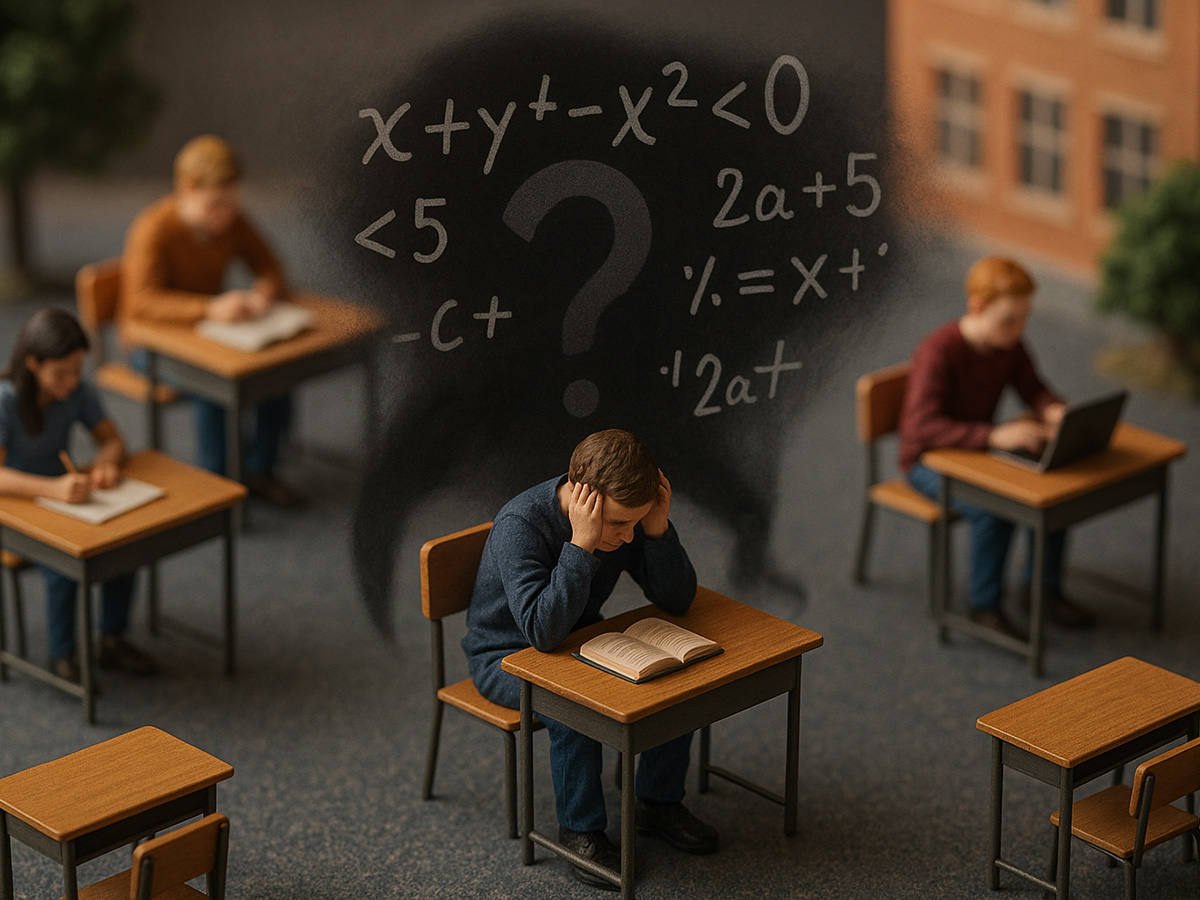
この記事が含む Q&A
- 発達障害のある学生は、数学・統計の不安だけでなく身体・心・テスト・社会場面・他人からの否定的な見られ方への不安など、多面的な不安と自己効力感の低さを感じやすいのでしょうか?
- はい、学びに関わるさまざまな場面で強い不安を抱え、自己効力感が低い傾向が見られます。
- 発達障害のある学生とCRTの得点には差がほとんどなく、不安が高くても「考える力自体」は変わらないということでしょうか?
- はい、論理的思考力(CRT)は発達障害の有無に関係なくほぼ同等で、不安の強さが能力を決めるわけではありません。
- 大学が取り組むべき支援として、どのような対策が挙げられていますか?
- 安心して間違いを認められる雰囲気作り、評価や提出方法の選択肢、予測しやすい予定と説明、質問しやすい導線、小さな成功の積み重ねによる自信育成です。
自閉症やADHD、ディスレクシア、ディスプラクシアなどの「発達障害(ニューロダイバージェンス)」をもつ大学生たちは、学びの場で強い不安を感じることが少なくありません。
とくに数学や統計に関する課題では、「自分は苦手かもしれない」「失敗したらどうしよう」という思いが先に立ち、不安が学びを難しくしてしまいます。
今回の研究は、イギリスのラフバラ大学を中心として、イギリス・オーストラリアなど複数の大学の研究チームが共同で行いました。
対象となったのは、大学で統計の授業を受ける学生たち。
大規模国際データ「SMARVUS(スマーヴァス)」のなかから、この研究の対象にふさわしい学生が選ばれました。
調査はオンライン形式で行われ、合計12,000人以上の回答から、性別・年齢・教育レベル・国が一致するよう慎重に調整したうえで、発達障害などの診断がある704人と、診断のない679人が比較されました。
つまり「公平に比べる」ための工夫がされています。
学生たちは、数学や統計の不安、テスト不安、社会的な不安、「他人から否定的に見られること」への恐れ、不確実な状況への不安など、多面的な質問に答えました。
さらに、直観に流されず論理的に考える力を測る「CRT(コグニティブ・リフレクション・テスト)」にも取り組みました。
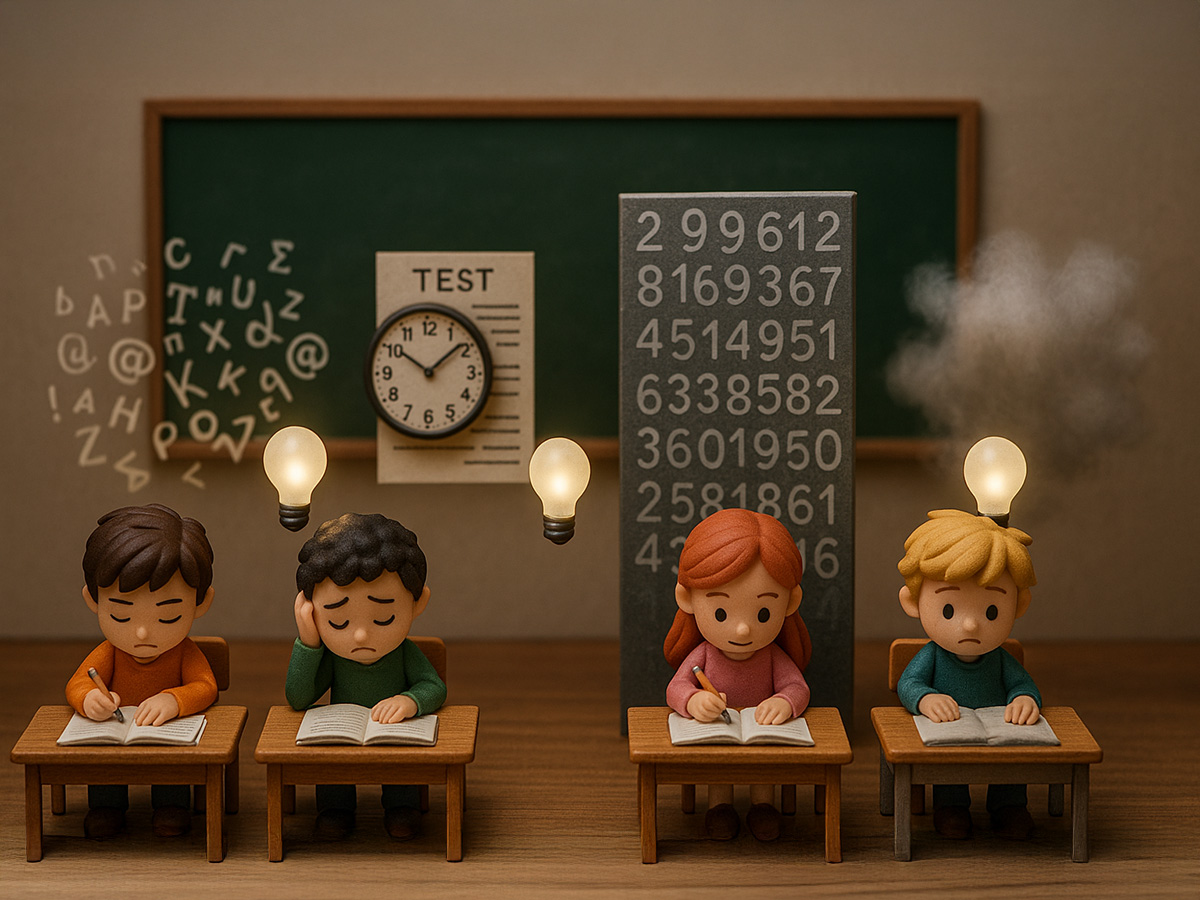
その結果、発達障害のある学生たちは、ほぼすべての不安が高いことがわかりました。
数学や統計への不安だけでなく、身体や心に感じる不安、テストへの不安、社会場面での不安など、学びに関わるあらゆる場面で強いプレッシャーを感じていました。
また自己効力感(「自分はできる」という感覚)が低く、苦手意識が膨らみやすい傾向も示されました。
それでも、論理的思考力そのもの(CRTの得点)には、定型発達の学生との違いはほとんどありませんでした。
つまり、「不安は強いけれど、考える力は変わらない」。
苦手に見える場面でも、その裏に潜む能力自体は、しっかりと存在しているのです。
また、発達障害のタイプ別にみると、不安の現れ方には違いがありました。
ディスレクシアでは身体・心理的不安が強い一方で、CRTの成績が良いケースもありました。
ディスレクシアは、読み書きの処理に特異的な困難がある特性で、知的能力とは関係がありません。
文字を読むのに時間がかかったり、似た文字を区別しづらいなどの困りごとが出ることがあります。
ADHDではテスト不安がとても高く、自信を持ちにくい傾向が見られました。
ディスカルキュリア(数学の学習症)では、数学と統計の不安が突出していました。
自閉症とディスプラクシアでは、「先が見えない状況」が特に強い不安につながっていました。
ディスプラクシアは身体の動きを計画したり調整したりすることが難しくなる特性で、「不器用」と誤解されやすいことがあります。
研究チームは、こうした不安が積み重なると、注意力が奪われ、柔軟に考える力が使いづらくなると説明します。
つまり、力がないわけではなく、発揮できない状況がつくられてしまっているのです。

では、大学はどうすべきでしょうか。
研究者たちは、不安への配慮こそが鍵だと指摘します。
・間違いを許容する、安心できる授業の空気
・選択できる評価や提出方法
・予測しやすい予定と説明
・質問しやすい動線
・小さな成功の積み重ねで自信を育てる支援
こうした工夫が、不安の壁を下げ、能力を発揮しやすくします。
研究者は伝えます。
「発達障害があるからといって、考える力が弱いわけではない」
「不安こそが、学びを阻む最大の敵になり得る」
ちがいを弱さと決めつけず、安心の土台を整えること。
それが、未来を形づくる学生たちの力を引き出す一歩になるのです。
(出典:Nature Scientific Reports DOI: 10.1038/s41598-025-21504-6)(画像:たーとるうぃず)
大学も企業と同じで、求められるのは
「心理的安全性」
それぞれの人が、それぞれの能力を発揮するために、複数人からなる「組織」には一番求められることですね。
(チャーリー)





























