
この記事が含む Q&A
- 模倣の評価にはどのような新しい技術が使われているのですか?
- アイトラッカーと深度カメラを活用し、視線や動作の詳細なデータを数値化しています。
- 自閉スペクトラム症の子どもたちの模倣の苦手な点は何ですか?
- 意味のないジェスチャーの模倣や、手の動きの正確さ・頻度が低いことが挙げられます。
- この研究の将来的な応用について、どのような可能性がありますか?
- 個々の子どもの得意・苦手に合わせた支援や教育プログラムの開発に役立つことです。
自閉スペクトラム症のある子どもたちにとって、「まねる力」、つまり「模倣」はとても重要です。
模倣は、言葉やジェスチャー、そして表情などを学ぶための基本となるスキルです。これがうまくできないと、他の人との関わりがうまくいかなかったり、日常生活で新しいことを学ぶことが難しくなったりします。
これまでの研究で、自閉スペクトラム症のある子どもたちは、定型発達の子どもたちと比べて模倣が苦手な傾向があるとされてきました。
しかし、その「どこが」「どのように」苦手なのかを、きちんと細かく測る方法はあまりありませんでした。
多くの検査は「まねできたか、できなかったか」といった、ざっくりした評価にとどまっていたのです。
そうした課題に取り組んだのが、中国の研究チームによる今回の新しい研究です。
この研究チームは、華中師範大学(Central China Normal University)の人工知能教育研究所と、遼城大学、カシュガル大学、広西師範大学の研究者たちで構成されています。
彼らは人工知能と教育の融合を専門としており、自閉スペクトラム症のある子どもたちの支援に役立つ評価方法や介入手法を開発することを目指しています。
この研究では、模倣能力をもっと細かく、そして正確に測るために、コンピュータやカメラを活用した「コンピュータ支援型の評価方法」を提案しています。
この方法では、子どもがどこを見ているか(視線の動き)や、どう体を動かしてまねしているか(運動のデータ)などを詳しく記録し、数値として評価します。
研究には、自閉スペクトラム症と診断された25人の子どもと、同じ年齢で定型発達の25人の子どもが参加しました。
年齢はおおよそ5歳から6歳半のあいだで、知的能力についてもグループ間で大きな差がないように選ばれました。
すべての子どもは、60〜78か月のあいだで、知能検査ではIQ70以上のスコアを出していました。

子どもたちは、パソコンの画面に映し出される12本の短いビデオを見て、その中の動作をまねするという課題に取り組みました。
ビデオの中では、若い女性が「お花のにおいをかぐ」「飛行機を飛ばす」といった「意味のある行動」や、「右手を頭の上に上げる」「右手を左肩に置く」といった「意味のないジェスチャー」を実演しました。
子どもたちはそのビデオを見て、同じように動作をまねするよう指示されました。
研究チームは、子どもたちがどれだけまねできたかを「頻度」と「正確さ」の2つの観点から評価しました。
たとえば、12個の動作のうちいくつをまねしようとしたか(頻度)や、それがどれだけ正確だったか(正確さ)です。
加えて、どこを見ていたか(視線)や、手の動きの長さ・スピード・方向などもすべて記録し、動作の細かなパターンも分析しました。
こうした詳しい分析を行うために、目の動きを測る「アイトラッカー」と、動作を3Dで記録する「深度カメラ(Kinect)」が使われました。
アイトラッカーでは、子どもがビデオの中の「顔」や「手の動き」にどれだけ注目していたかがわかります。
一方、深度カメラでは、子どもの手の動きがビデオの中の動作とどれくらい似ていたかが数値で比較できます。
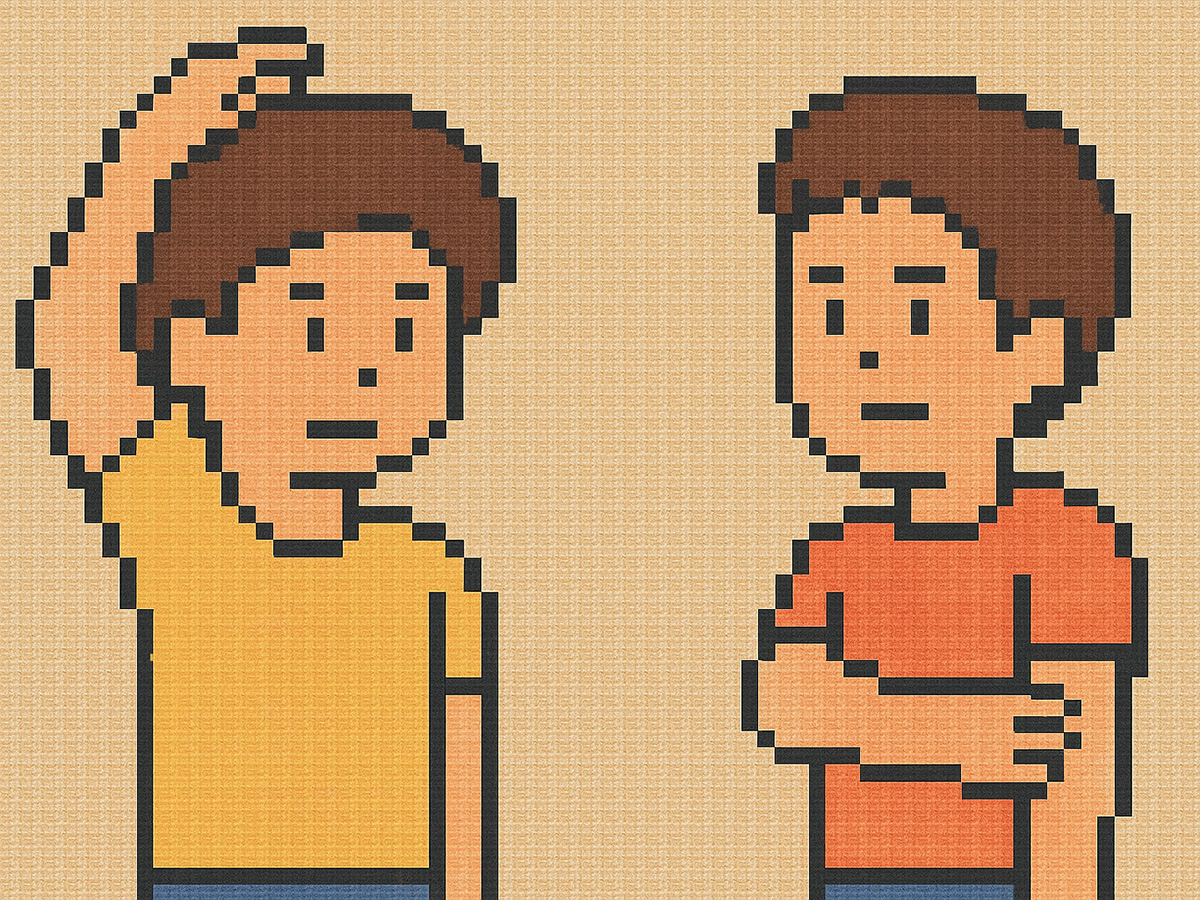
その結果、定型発達の子どもたちと比べて、自閉スペクトラム症の子どもたちは「意味のないジェスチャー」の模倣が苦手であることが明らかになりました。
具体的には、模倣しようとする回数(頻度)も少なく、また模倣の正確さも低かったのです。
さらに、視線のデータを見ると、自閉スペクトラム症の子どもたちは、定型発達の子どもたちよりも「顔の部分」を見る時間が圧倒的に短いことがわかりました。
これは、「人の表情」や「感情」への関心の低さとも関係していると考えられます。また、「手の動き」への注目も、課題の内容によっては少なくなる傾向がありました。
体の動きについても、自閉スペクトラム症の子どもたちは、動作の「長さ」や「スピード」「振れ幅」が大きくズレていたことが明らかになりました。
たとえば、同じ動きをしているつもりでも、動かしすぎていたり、スピードが速すぎたり、動作が極端に小さかったりする傾向が見られました。
とくに面白いのは、「意味のある行動」では、このようなズレがあっても、全体的な模倣の正確さには大きな差が出にくかったという点です。
つまり、花をかぐ、飛行機を飛ばすといった具体的な行動は、物の形や動作のイメージが手がかりになるため、自閉スペクトラム症の子どもでも比較的うまくまねできるのです。
その結果、「意味のないジェスチャー」を使った模倣課題では、自閉スペクトラム症の子どもかどうかについて、84%という高い分類の正確さ(精度)が得られました。
これは、従来の方法では達成できなかったレベルの精度であり、研究チームは「今後の診断や教育支援に役立つ可能性がある」と述べています。
一方、「意味のある行動」を使った課題では、分類の精度は70%以下にとどまりました。
これは、先ほど述べたように、物があることで手がかりが多くなり、模倣の差が見えにくくなるためだと考えられます。
つまり、「どれだけ正確にまねできたか」を見るだけでは、本当に困っている子どもを見つけ出すことが難しい場合があるということです。
このように、視線や動作のデータを細かく分析することで、これまで見過ごされていた「模倣のスタイルの違い」が浮かび上がってきました。
たとえば、「動かすスピードが極端に速い」「振れ幅が小さい」「視線がほとんど顔に向かない」といった特徴は、模倣の質に大きく影響しているのです。
実際、この研究の結果は、他の研究とも一致しています。
たとえば、同じように視線や動作のパターンを分析した研究では、自閉スペクトラム症の子どもたちが模倣する際に「どうやってまねしているか」が重要だとされており、「できたかどうか」だけを見る従来の方法では見落としてしまうことがあると指摘されています。
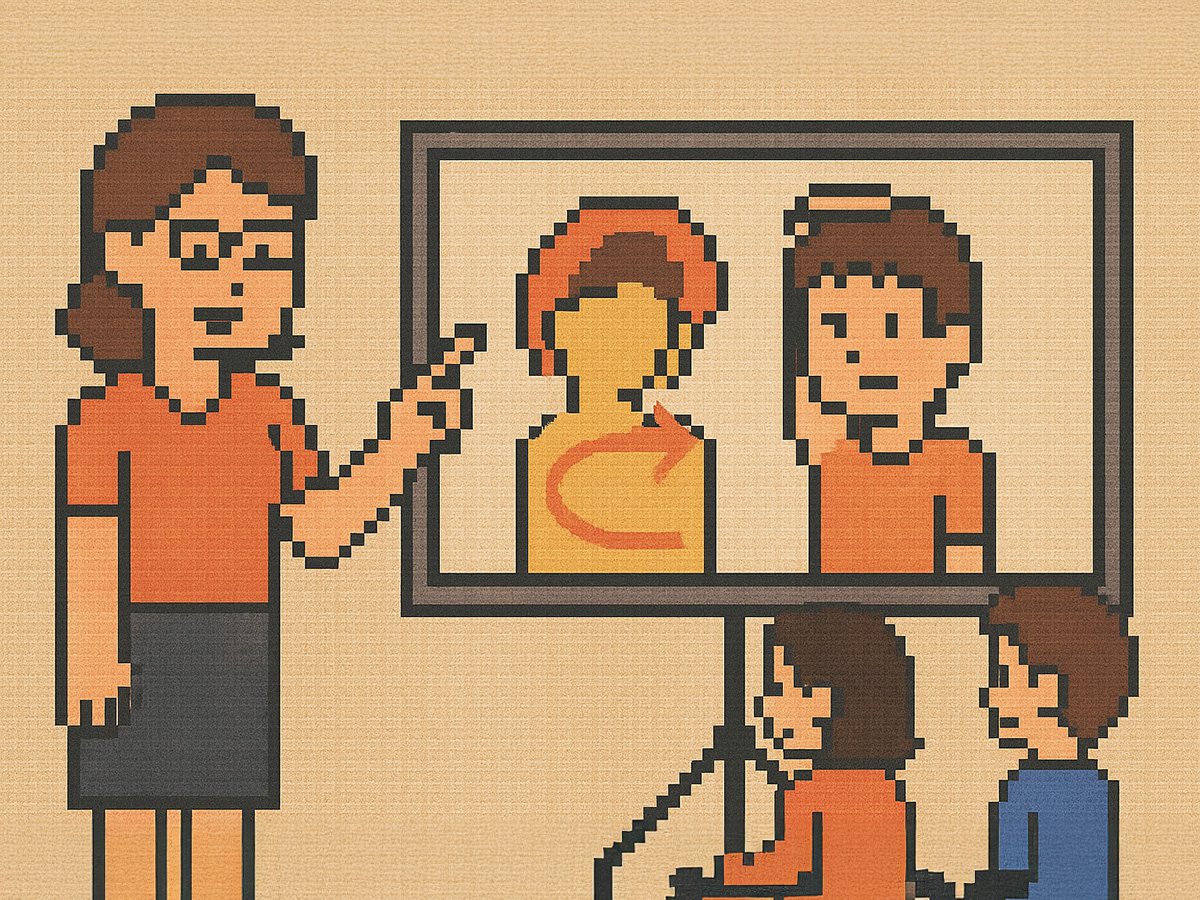
さらに興味深いのは、この研究が将来的な「個別支援」にもつながる可能性があるという点です。
子どもによって視線の傾向や動作のズレ方は異なり、どこが得意で、どこが苦手かも違います。
そうした「個人ごとの違い」を数値で把握できれば、その子に合った教育プログラムや療育方法を考える手助けになるのです。
たとえば、顔を見る時間が短い子どもには、表情を強調した教材を使ったり、動作のズレが大きい子どもには、ゆっくりとした動きを繰り返す教材を使ったりすることで、より効果的な支援ができるようになるかもしれません。
実際、研究チームは「将来的には、このようなデータを使ってパーソナライズされた支援システムを開発したい」としています。
ただし、研究にはいくつかの限界もあります。
まず、参加者の人数が50人と少なかったことです。
これは新型コロナウイルスの影響で、実験の参加者を集めるのが難しかったためです。
今後は、もっと多くの子どもたちに参加してもらい、さらに正確な分析が必要とされています。
また、今回の研究では年齢やIQはそろえてありましたが、発達段階(たとえば、言葉の発達段階など)が完全に一致していたわけではありません。
こうした違いも、模倣の能力に影響を与える可能性があるため、今後の研究では発達段階をより細かく揃えた比較が望まれます。
それでも、今回の研究が示したのは、「模倣の評価は、もっと細かく、もっと個別にできる」ということです。
視線の動きや体の動きという「プロセス」に注目することで、これまで見えてこなかった子どもたちの困難や可能性が浮かび上がってきます。
このような方法は、教育の場面でも大きな意味を持ちます。
たとえば、模倣を通じた学びが多い幼児期に、こうした分析を取り入れることで、より早く、より適切な支援につなげることができるかもしれません。
模倣は、ただ「まねをする」だけではなく、他者とつながり、社会の中で学ぶための大切なステップなのです。
この研究は、その模倣を細かく見ていくことで、子どもたち一人ひとりの学び方や支援のヒントを探る新しい一歩となりました。
今後、より多くの子どもたちへの応用や、個別支援との連携が期待されています。
研究チームは「今後は、この評価方法を活用して、個々の子どもに合った教材や支援プログラムを開発していきたい」と述べています。
たとえば、ビデオの中の先生が笑顔で教える教材は、自閉スペクトラム症の子どもたちにとって学びやすくなるかもしれません。
実際、過去の研究では、先生が笑顔を見せることで学習効果が上がるという結果も出ています。
こうした「精密な評価」によって、子どもたちの未来の可能性を広げていくことができるのです。
(出典:Nature DOI: 10.1057/s41599-025-05068-4)(画像:たーとるうぃず)
うちの子は小さな頃、2歳ころでしょうか、テレビを見て、「ハッスル、ハッスル」と手を曲げ前後にゆらして、真似ていたことを思い出しました。(意味があるのかないのか???)
それが、最後の言葉らしきもので、それから言葉はなくなり、真似することもなくなりましたけれど。
そんなことを思い出しました。
(チャーリー)





























