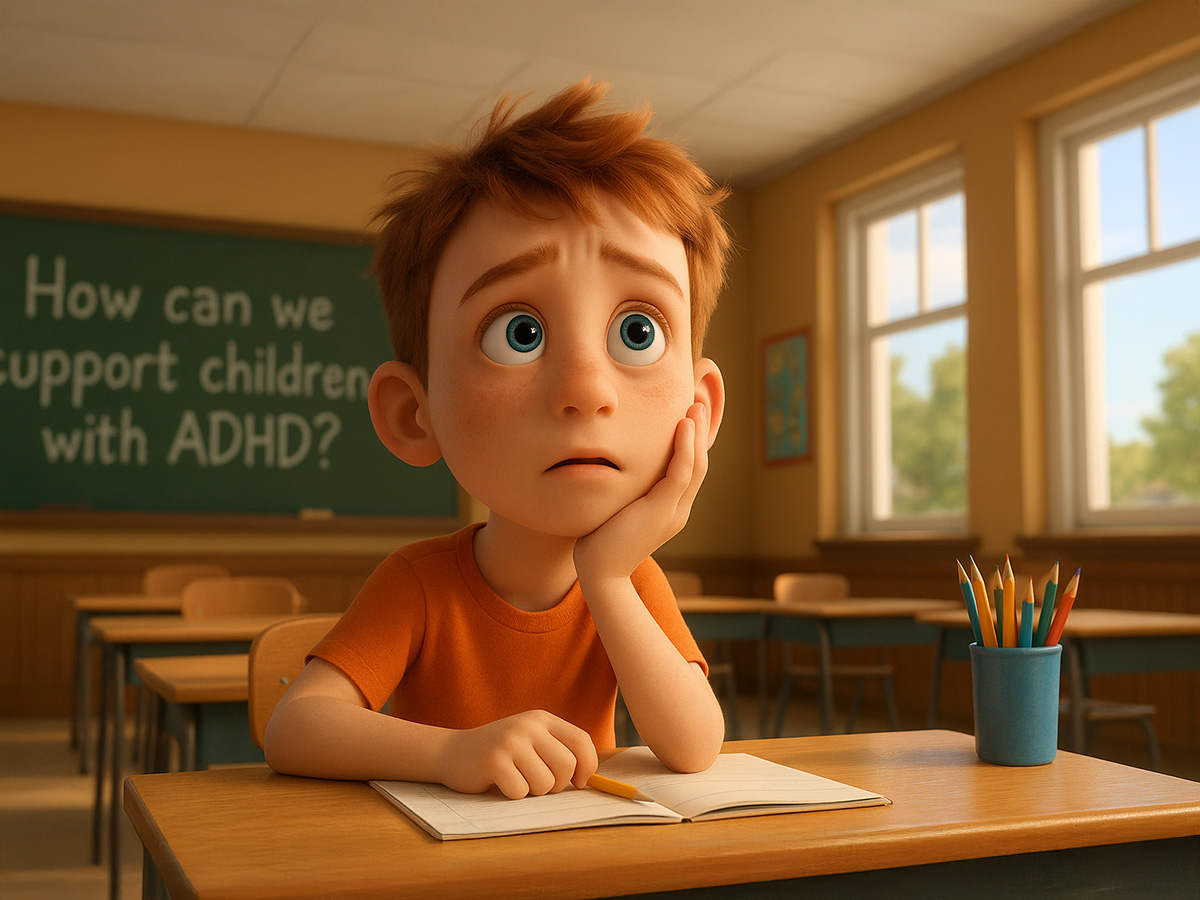
この記事が含む Q&A
- ADHDの学校での支援は子どもの症状や行動にどの程度効果がありますか?
- まず「不注意」や「学業の向上」、社会的スキルに改善が見られ、困りごと全体に効果的です。
- どんな具体的な支援方法が学校で効果的とされていますか?
- 応用トレーニングや自己モニタリング、ソーシャルスキル練習、行動記録などが有効です。
- 支援の効果はどの年齢層や評価者によって異なりますか?
- 小学生の方が中高生より効果が大きく、外部の観察者はより高い改善を感じやすい傾向があります。
注意欠如・多動症(ADHD)の子どもたちを学校で支援するにはどうすればよいのでしょうか。
最近、ADHDをもつ子どもが増えてきたことから、学校での支援の大切さがますます注目されています。
でも、学校で行われてきた支援が、どれくらい効果があったのか、全体としてはっきりとは分かっていませんでした。
そこで、イギリスのヨーク大学の研究チームが、新しい研究を行いました。
1980年から2024年までの間に行われた、ADHDの子どもを対象にした「学校での支援」に関するランダム化比較試験(RCT)を集めて、その効果をまとめて調べたのです。
この研究では、ADHDの特徴である「不注意」や「多動・衝動性」といった症状だけでなく、「学業の成績」「友だちとの関係」「反抗的な行動」など、ADHDにともなって起こりやすい困りごとについても調べました。
ADHDとは、子どもに多く見られる発達の特性の一つです。
世界では約8%の子どもがADHDだと言われています。ADHDには大きく分けて2つの特徴があります。
一つは「不注意」といって、集中が続かなかったり、順番通りに行動したりするのが苦手なこと。
もう一つは「多動・衝動性」といって、落ち着きがなかったり、思いついたらすぐに行動してしまったりすることです。

ADHDの子どもは、学校生活の中で困りごとが多くなりがちです。
たとえば、友だちとうまく遊べなかったり、授業に集中できなかったり、先生とぶつかってしまったりします。
さらに、ADHDの子どもは、不安やうつ、自閉スペクトラム症など、ほかの発達的な特性もいっしょにもっていることが多く、困りごとは複雑になりやすいです。
今回の研究では、学校という場所での支援が、どのくらい役に立つのかを調べました。
過去にも同じような研究がありましたが、バラバラで分かりにくく、本当に効果があるのかはっきりしませんでした。
しかも、「ランダムに子どもを2つのグループに分けて、比較する」という信頼性の高い方法(ランダム化比較試験)だけにしぼった調査は、今回が初めてです。
研究チームは、教育や心理、医学の専門的なデータベースから、合計で11,479件の研究を探し出しました。
その中から、条件に合う26件の研究を選び、そのうち22件は、実際の効果の大きさを数字で計算できたので、メタ分析に使いました。
参加した子どもは、全部で2,100人以上にのぼります。

この研究でわかったのは、次のようなことです。
まず、「ADHDの症状全体(不注意と多動・衝動性をあわせたもの)」について、支援を受けた子どもは、受けていない子どもよりも、症状が軽くなっていました。
次に、「不注意」については、さらに少し大きな改善がありました。
一方で、「多動・衝動性」については、あまり効果は見られませんでした。
また、「学業の成績」は明らかに向上しており、「友だちづきあいなどの社会的なスキル」も良くなっていました。
「反抗的・攻撃的な行動」などの問題も、支援を受けた子どもでは減っていました。
つまり、学校での支援は、「不注意」「学習の困りごと」「人間関係」「反抗的な行動」などには役に立っていることがわかりました。
ただし、「多動・衝動性」については、あまり変化がなかったため、今後もっと工夫が必要だと考えられます。
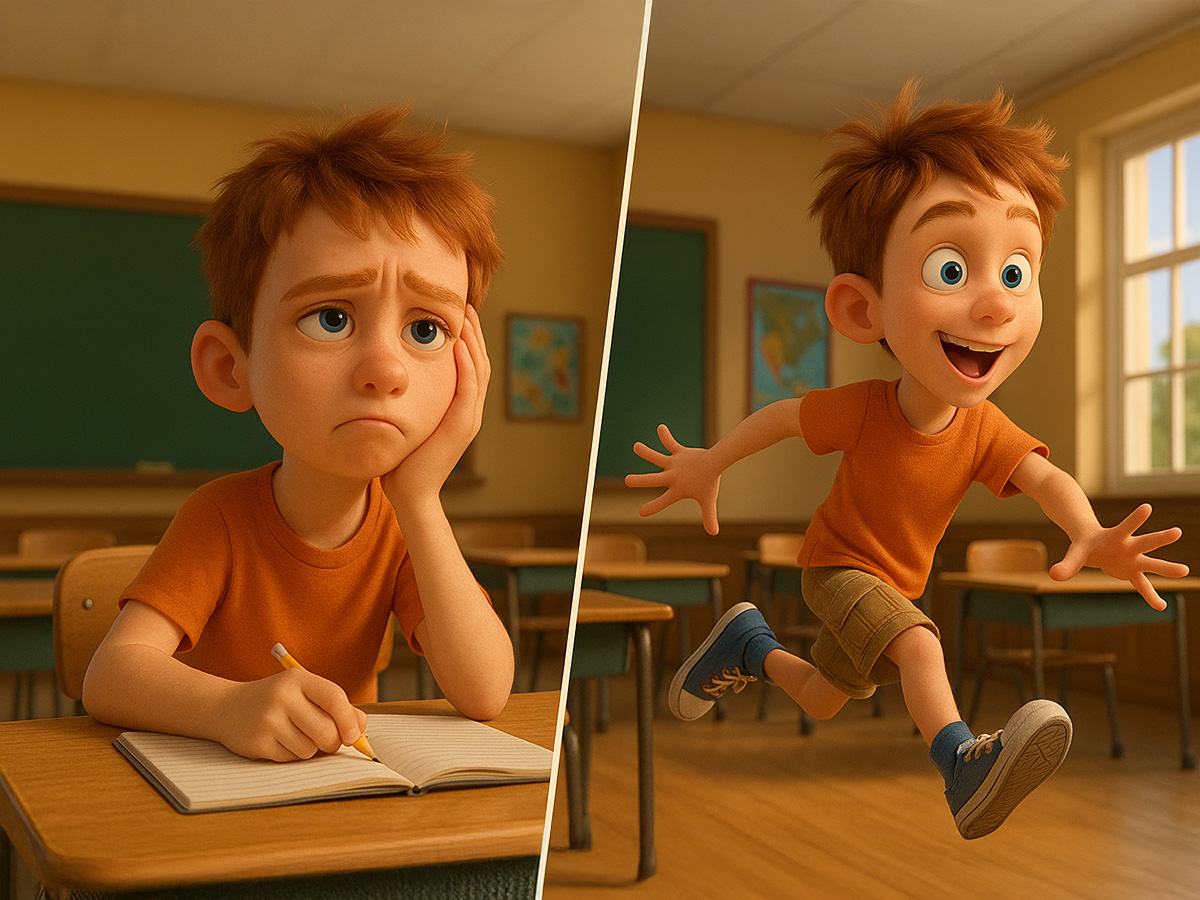
さらに、どの学年の子どもかによっても効果が違いました。
小学校の子どもたちに対する支援のほうが、中学生・高校生への支援よりも、効果が大きくなる傾向がありました。
また、誰が効果を評価したかによっても結果が異なりました。
たとえば、「不注意」の改善については、子ども自身よりも先生や保護者のほうが「変化は小さい」と感じていました。
一方で、観察者(外から子どもの様子を見た人)は、もっと大きな変化があったと感じていました。
研究チームは、結果を正しく見るために注意が必要だとも言っています。
たとえば、「どちらのグループかを知っている先生」が評価をすると、無意識にバイアス(かたより)が入ってしまうかもしれません。
また、うまくいかなかった結果が公表されないことで、全体的に効果があるように見える「出版バイアス」もあるかもしれないとしています。
では、実際に学校ではどんな支援が行われていたのでしょうか。
調査された研究では、さまざまな方法が使われていました。たとえば、
* 「作業記憶」や「注意力」をきたえるトレーニング
* 「自分の行動をチェックする」自己モニタリング
* 「友だちとのやりとりの練習」ソーシャルスキルトレーニング
* 学習のしかたを変える「課題の工夫」
* 「ごほうび」でやる気を高める行動強化
* 家庭との連携や保護者へのサポート
* 毎日の行動を記録する「デイリーレポートカード」
支援は、学校の先生やスクールカウンセラーなどが行うことが多く、保護者と協力して進められることもありました。

また、支援にかける時間もさまざまで、短いものでは25分、長いものでは360時間もありました。
平均すると、子ども一人あたり約39時間の支援が行われていたことになります。
この研究は、「学校での支援がどれくらい役に立つのか」について、信頼できるデータをまとめて示してくれました。
ADHDの子どもたちは、学校生活の中でさまざまな困難を感じています。
でも、今回の研究は、「学校だからこそできること」がたくさんあることを示してくれたのです。
もちろん、まだまだ課題はありますが、学校という場が、ADHDの子どもたちにとって「困る場所」ではなく、「助けられる場所」「成長できる場所」になるために、今回の研究は大きなヒントをくれるものでした。
(出典:frontiers DOI: 10.3389/fpsyg.2025.1611145)(画像:たーとるうぃず)
学校だから起きてしまう、不必要な困難、問題ができるだけなくなって、「学校だからこそできること」を子どもたちがたくさん受け取れるようになることを、心から期待しています。
「ふつう」になれない私、ADHD女子高生の学校での闘い。研究
(チャーリー)




























