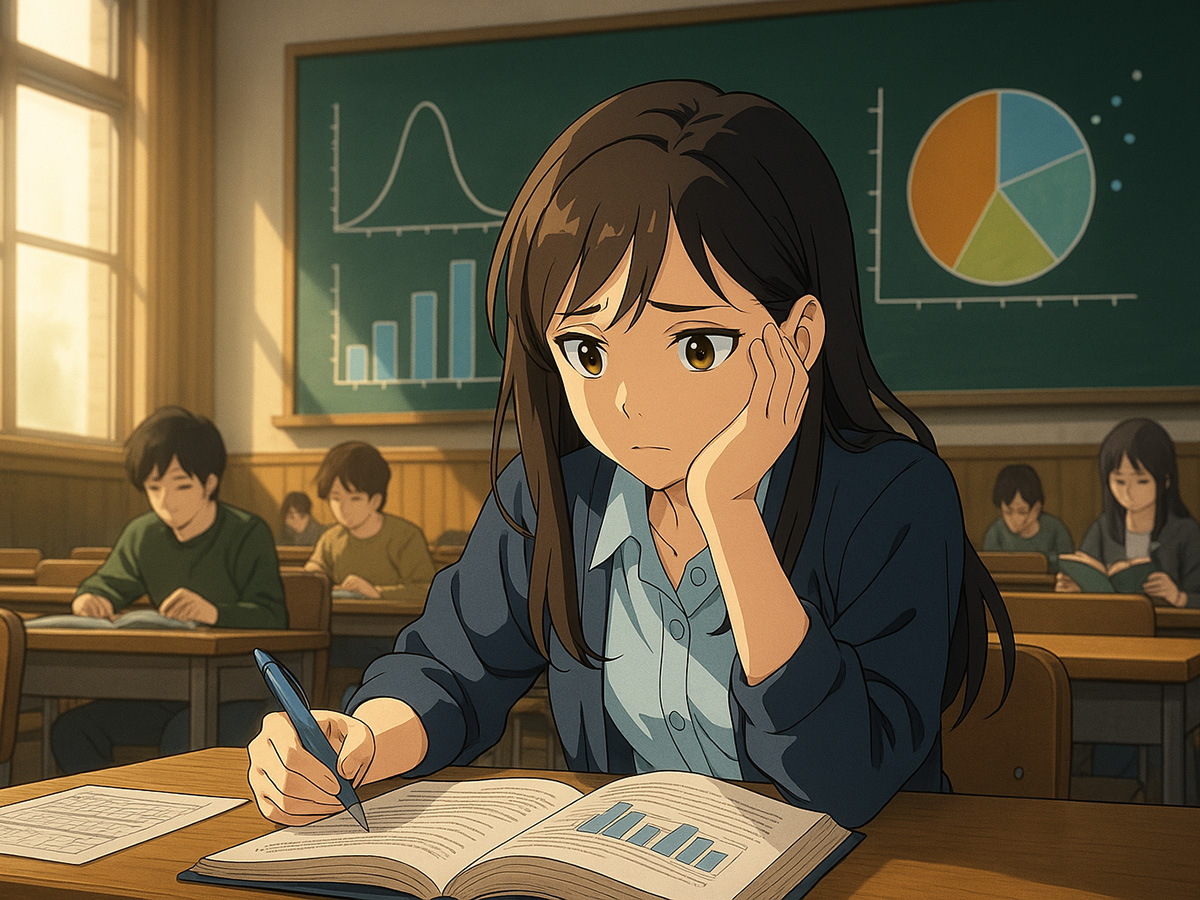
この記事が含む Q&A
- ADHDの学生は統計リテラシーの学習で不安を感じやすいのはなぜですか?
- ADHD傾向の学生は授業・試験での不安が高く、統計に対する態度も否定的になりやすいと報告されています。
- 診断の有無にかかわらず統計リテラシーの点数に差はありましたか?
- いいえ、3グループ間で統計リテラシーの成績に有意差はありませんでした。
- 学習支援としてどのような対策が有効と提案されていますか?
- マインドフルネスやリラクゼーション、統計の将来価値の理解促進、練習機会の充実、自己申告のみの学生の診断・支援アクセス拡大が提案されています。
大学や大学院で学ぶ多くの学生にとって、「統計」は避けて通れない科目のひとつです。
データを読み解き、意味のある判断を行うための「統計リテラシー(統計的読み書き能力)」は、あらゆる分野で重要になっています。
グラフや表、研究結果などの数値情報を批判的に理解し、活用できる力は、研究者や専門職だけでなく、社会生活を送るうえでも必要です。
しかし、多くの学生が統計に苦手意識を持ち、学習に不安や抵抗感を感じています。
とくに、ADHD(注意欠如・多動症)の学生にとっては、こうした状況がより深刻になることが知られています。
ADHDは、不注意、多動性、衝動性といった症状を特徴とする神経発達症であり、成人期まで続くこともめずらしくありません。
大学・大学院などの高等教育では、2〜8%程度の学生がADHDとされていますが、研究によっては15%以上と推定されることもあります。
ただし、実際には正式に診断を受けていない学生も多く、支援や配慮を受けられないまま学び続けている場合があります。
診断の有無によって、試験時間延長や追加の学習サポートといった学内の配慮が受けられるかどうかが決まるため、未診断の学生は不利な立場に置かれることになります。
今回の研究では、ADHDと統計リテラシーの関係を明らかにするために、3つのグループの学生を比較しました。
ひとつは正式にADHDと診断されている学生、もうひとつは自分にADHDの傾向があると感じているが診断は受けていない学生、そしてADHDの傾向がない学生です。
合計405人(診断あり80人、自己申告あり74人、非ADHD251人)が参加しました。
全員が基礎的な統計の授業を修了しており、理論と統計ソフトの活用を含む内容を学んでいました。

まず、統計に関する不安(統計不安)を測定しました。
これは、授業や試験で統計を扱うときの不安、統計結果を解釈する際の不安、そして教員や他の学生に質問することへの不安の3つの側面から評価しました。
さらに、統計に対する態度も測定しました。
統計が役立つと感じるか、自分に統計を扱う力があると感じるか、統計の教員への苦手意識があるか、といった要素です。
そして、統計リテラシーは、研究者が作成した10問の課題で測定しました。
これには、表やグラフの読み取り、パーセンテージや頻度の理解、統計的有意差や仮説検定の基礎知識などが含まれていました。
分析の結果、統計不安は、診断ありグループ(平均3.15)と未診断グループ(3.12)が、非ADHDグループ(2.64)よりも有意に高くなっていました。
態度についても、非ADHDグループ(3.33)の方が、診断あり(3.06)や未診断(3.03)より有意に肯定的でした。
つまり、ADHD傾向がある学生は、診断の有無にかかわらず、統計に対して不安が強く、態度も否定的になりやすいことが分かりました。
しかし、意外なことに、統計リテラシーの成績には3グループ間で有意な差はありませんでした。
非ADHDグループの平均は6.57点、未診断グループは5.81点、診断ありグループは5.66点で、統計的に有意な違いはなかったのです。
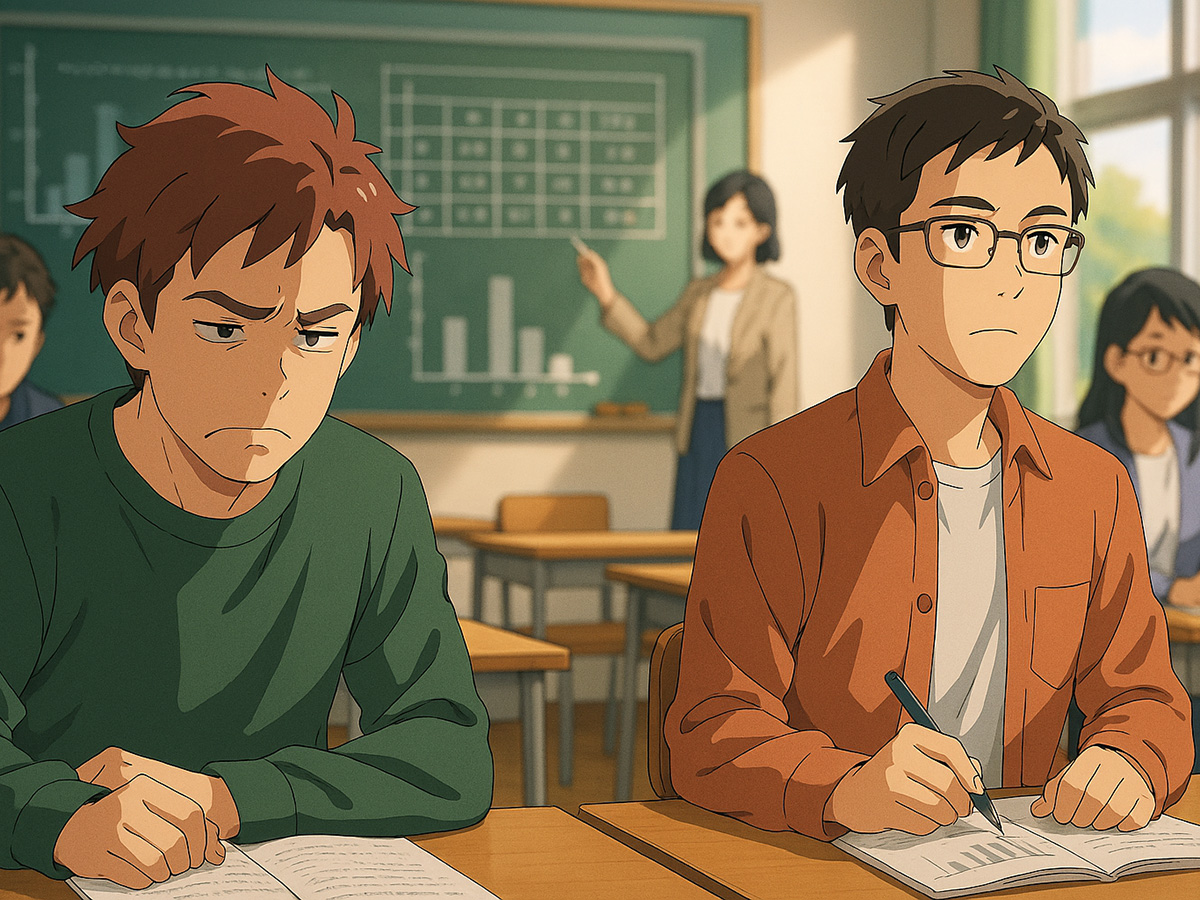
これは、「ADHDの学生は数学や統計が苦手で成績も低い」という一般的な思い込みに反する結果です。
むしろ、ADHD傾向の学生は、不安や否定的な態度を抱えながらも、実際の能力は非ADHDの学生と同等である可能性が示されました。
統計リテラシーを予測する要因を分析したところ、もっとも影響が大きかったのは「統計に対する態度」と「学位レベル(大学院か学部か)」でした。
統計に肯定的な態度を持つ学生、そして大学院生の方が高い得点を取っていました。
一方で、ADHDの有無や統計不安の高さは、他の要因を統制した場合には有意な予測因子ではありませんでした。
つまり、統計リテラシーに直接関係するのはADHDの診断そのものではなく、「その科目にどう向き合っているか」と「どの学習段階にいるか」だったのです。
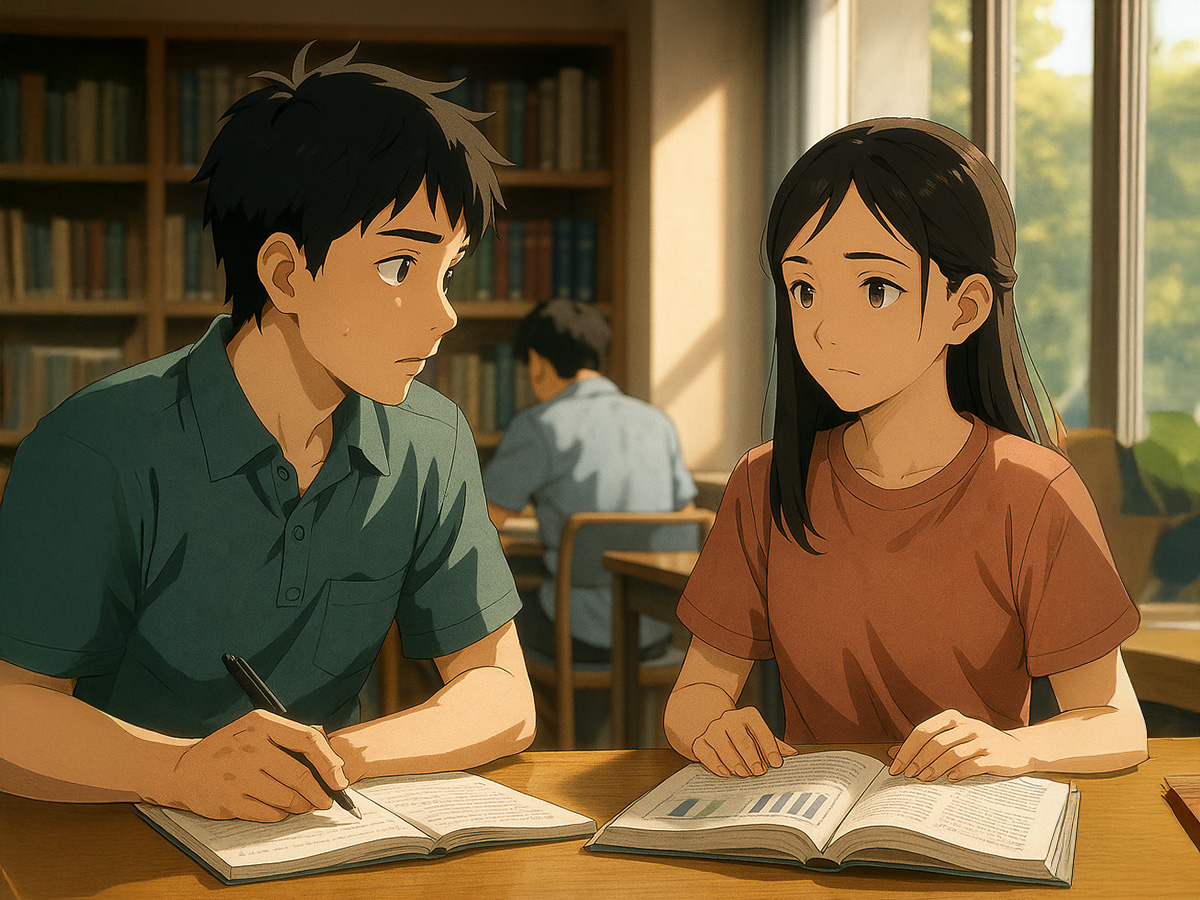
この結果から、重要な指摘がされています。
診断ありの学生は学内の支援を受けられることが多い一方、未診断の学生は同じような困難を抱えていても支援がない「二重の不利」を背負っています。
それでも成績が同等であるのは、高い適応力や代替戦略を使っている可能性があると考えられます。
ただし、その分、心理的負担やストレスは大きいはずで、長期的には健康や学習意欲に影響を及ぼすおそれがあります。
研究者らはこのような学生への支援を拡大する必要があると強調しています。
診断の有無にかかわらず、症状や困難がある学生には、統計に対する不安を軽減し、肯定的な態度を育てる取り組みが重要です。
具体的には、マインドフルネスやリラクゼーション、テスト不安対策などのストレスマネジメント、統計が将来に役立つという意識づけ、自信を持って取り組める練習機会の提供などが提案されています。
また、自己申告のみの学生にも支援や診断へのアクセスを広げることが、教育の公平性を高める鍵になるとしています。
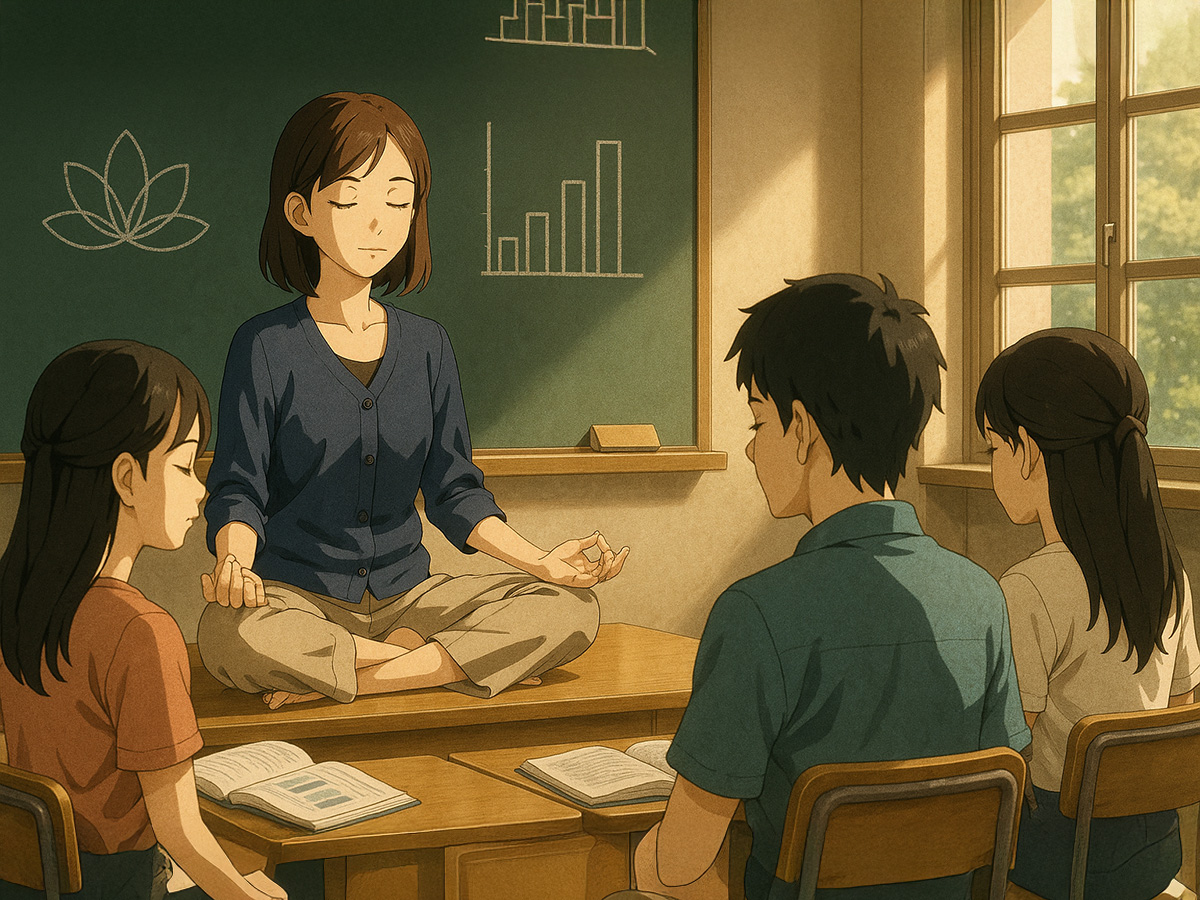
この研究は横断的な調査であるため、因果関係までは明らかにできません。
また、自己申告による診断や症状評価に基づいていること、オンラインでの課題実施による外部支援の可能性、統計リテラシー課題の問題数が少ないことなどの制限があります。
しかし、ADHD傾向のある学生が、感情的な困難を抱えながらも学力面では対等に渡り合えるという結果は、従来の固定観念を揺さぶる重要な発見です。
そして、学習意欲や態度を改善することが、学力の向上や不安の軽減につながる可能性があるという示唆は、教育現場での支援方法を考えるうえで大きな意味を持ちます。
(出典:Frontiers DOI: 10.3389/fpsyt.2025.1585601)(画像:たーとるうぃず)
面白い研究ですね。
苦手意識はあっても、実はそんなことはない。
統計に限らず、たくさんありそうですね。
「嫌われた」―ADHDの見えにくい特性、拒絶過敏性(RSD)
(チャーリー)




























