
この記事が含む Q&A
- 自閉症と関係があるとされる脳の細胞は何ですか?
- 層2/3 ITニューロンと呼ばれる特定の神経細胞が関係しているとされ、言語理解や社会的判断に関与すると説明されています。
- 本研究が示した、ヒトと他の霊長類での細胞の進化の違いと自閉症遺伝子の働きの関係はどういう点ですか?
- 層2/3 ITニューロンは他種に比べて速く変化し、その方向は自閉症に関わる遺伝子の働きを弱める方向であったとされます。
- この研究は自閉症の理解や支援にどんな示唆を与えますか?
- 自閉症は進化の過程で得られた知能・社会性の土台の一部として捉えられ、特性をどう生かすかを考える視点を与えるとされています。
人間がどのようにして今の姿になったのかという問いは、昔から多くの人を惹きつけてきました。
脳が大きくなり、言葉を使い、社会をつくり、文化を築いてきた人間。
その歩みは、単純に「脳が大きくなった」ということだけでは説明できません。
脳をかたちづくる細胞がどのように働き、どのように変わってきたのか。その積み重ねこそが、人間らしさを生み出してきたと考えられます。
その一方で、進化の中で得られた変化が、特有の困難や特性をもたらしている可能性もあります。
もし自閉症がその一例だとしたらどうでしょうか。
英スタンフォード大学の生物学部が中心となって行った最新の研究は、その可能性を示しています。
研究チームは人の脳で最も数が多い神経細胞に注目しました。
そして、その細胞が人間だけ特別に速い進化を遂げており、その変化が自閉症の特性と関係していることを明らかにしたのです。
脳には無数の細胞が存在しますが、大きく分けると情報を伝える神経細胞と、それを支える細胞があります。
その中でも特に重要なのが「層2/3 ITニューロン」と呼ばれる細胞です。
これは大脳皮質の第2層と第3層にあり、脳の領域同士をつなぎ合わせて情報をやり取りします。
言葉を理解したり、他人の気持ちを想像したり、社会的な判断を行うときに中心となる細胞で、脳の中で「会話役」を担っていると考えるとわかりやすいでしょう。
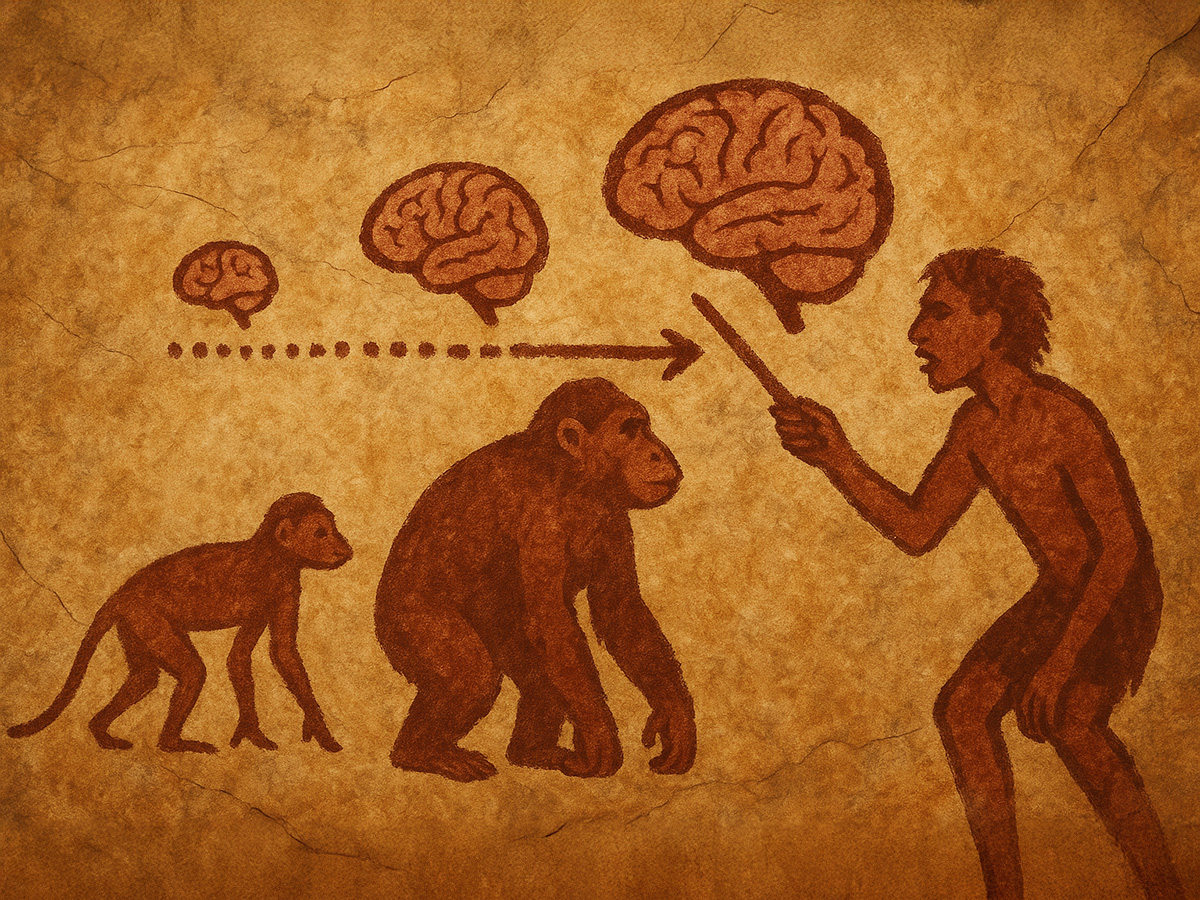
研究者たちはヒトやチンパンジー、ゴリラなど複数の霊長類の脳を比べました。
その結果、ある基本的な法則が見えてきました。
それは「数が多い細胞ほど進化のスピードが遅く、変化しにくい」というものです。
数が多い細胞で急な変化が起きると脳全体に影響が広がってしまうため、自然と守られてきたのだろうと考えられます。
ところが、ヒトの層2/3 ITニューロンだけはその法則から外れていました。
この細胞はチンパンジーやゴリラと比べて驚くほど速いペースで変化していたのです。
そして、その変化の方向には特徴がありました。
それは「自閉症に関係する遺伝子の働きを弱める」という方向でした。
自閉症に関わる多くの遺伝子は、ほんの少し働きが減るだけでも影響が出やすいことが知られています。
ヒトでは、そもそもの基準値が他の動物よりも低く設定されていました。
そのため、ちょっとした揺らぎでも限界を超えやすく、自閉症の特性が現れやすいのではないかと考えられます。
この仮説を確かめるために、研究チームはヒトとチンパンジーの細胞を混ぜて育てる実験モデルをつくりました。
その結果でもヒトの遺伝子はチンパンジーより低く働いていることが再現されました。
つまりこれは環境の違いによるものではなく、遺伝子そのものに組み込まれた特徴だといえます。
さらに詳しい解析の結果、多くの遺伝子が少しずつ同じ方向に進む「多遺伝子性の正の選択」が起きている可能性も示されました。
人類が進化する中で、この細胞の働きを弱めることに何らかのメリットがあったのかもしれません。
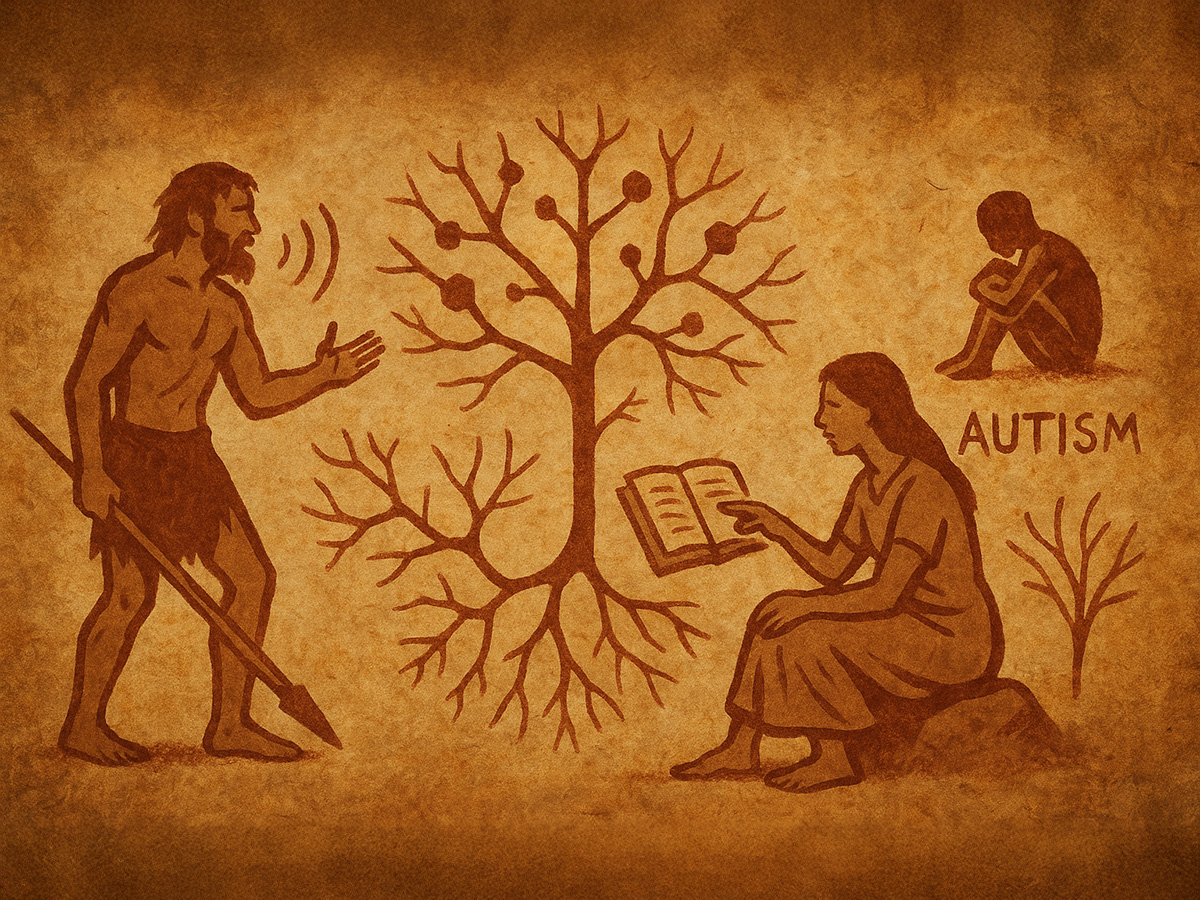
そのメリットとは何でしょうか。
研究チームは明言していませんが、言語の発達や学習能力の拡張に関わっていた可能性があります。
脳の中で会話役を担う細胞の働きが微妙に調整されたことで、人間はより複雑な社会や文化を築けるようになったのかもしれません。
しかし同時に、その調整はリスクを生みました。
自閉症に関わる遺伝子の働きが下がっていたために、わずかな変化でも特性が現れやすくなったのです。
つまり、自閉症の多さは人間が進化する中で獲得した知能や社会性の裏側にあるものだとも言えます。
具体的な分子の例として、シナプスを支えるタンパク質DLG4(PSD-95)があげられます。
神経のつなぎ目で情報をやり取りするうえで欠かせないこのタンパク質は、自閉症研究で繰り返し注目されてきましたが、ヒトではチンパンジーよりも少なくなっていました。
これは進化の中で「標準値」が変わった証拠です。
この研究は、自閉症の原因をひとつに決めつけるものではありません。
自閉症は遺伝と環境が複雑に重なり合って生まれます。
ただし今回の結果は、ヒトという種の進化の中で「特性が出やすい土台」がすでに用意されていた可能性を示しています。
だからといって、自閉症を「進化の失敗」と捉える必要はありません。
むしろ、人間の知能や社会性を支えた進化の中で生まれた特性と考えることができます。
進化の流れの中で弱さと強さが表裏一体で存在しているのです。

自閉症のお子さんを育てている保護者にとって、この研究は新しい視点を与えてくれます。
お子さんの特性は「人類の進化の流れ」の中で形づくられてきたものなのです。
だからこそ、「なぜ自分の子がそうなのか」と悩むよりも、「その特性をどう生かすか」に目を向けてよいのです。
自閉症の子どもが示すこだわりや繊細さは、進化の中で人類が複雑な社会を築くうえで必要な資質とつながっているのかもしれません。
直感に頼らず、じっくりと考えてから行動する姿勢や、細部にまで注意を払う力。
これらは現代社会においても大きな強みになる場面が少なくありません。
今回の研究は、自閉症の理解を広げるだけでなく、人類がどのように発展してきたかを考える手がかりにもなります。
進化の結果として生まれた多様性を否定するのではなく、大切にしながら支援の工夫を積み重ねていく。
そこに未来への希望があります。
自閉症の当事者や家族、支援者だけでなく、人類の進化に関心をもつすべての人にとって、この研究は「人間らしさ」の意味を問い直すきっかけとなるでしょう。
ヒトの脳が進化する中で生まれた調整が、社会を豊かにし、同時に多様性を育んできた。
そのことを理解することは、誰もが安心して自分らしく生きられる未来につながります。
(出典:Molecular Biology and Evolution DOI:10.1093/molbev/msaf189)(画像:たーとるうぃず)
「自閉症の子どもが示すこだわりや繊細さは、進化の中で人類が複雑な社会を築くうえで必要な資質とつながっているのかもしれません。」
その通りだと私は思います。
(チャーリー)





























