
この記事が含む Q&A
- 自閉症の脳では、グルタミン酸とGABAのバランスが関係していると示されていますか?
- はい、グルタミン酸とGABAの働きのバランスが関係していることが示されています。
- ケタミンを用いた実験は、自閉症の脳状態を再現することや興奮と抑制のバランスを崩すことを示していますか?
- はい、ケタミンは自閉症の脳活動パターンに似た状態を再現し、興奮と抑制のバランスを崩すことが観察されました。
- 本研究の限界にはどのような点が挙げられますか?
- 知的障害を持つ自閉症を除外、健康な男性のみ、集団平均に基づく解析で個人差が反映されにくい点などが挙げられます。
自閉症の人の脳では、休んでいるときの活動に特徴的な変化があることが、長年の研究から少しずつ明らかになってきました。
今回、ドイツ・ユリッヒ研究センター、マックスプランク人間認知・脳科学研究所、オークランド大学、カーディフ大学などが参加した国際共同研究チームによる調査で、その脳の活動の違いが「神経伝達物質」と呼ばれる脳内の化学物質と深く関係していることが示されました。
そして、その変化はある薬の作用によっても再現されることがわかりました。
これにより、自閉症の人の脳で何が起きているのかを理解する新しい手がかりが見えてきました。
神経伝達物質とは、神経細胞同士がやりとりするときに使う化学のメッセージのようなものです。
人が考えたり感じたり動いたりできるのは、無数の神経細胞がメッセージを送り合うからです。
なかでも重要なのが「グルタミン酸」と「GABA(ギャバ)」です。
グルタミン酸は神経を「働かせる方向」に動かす一方で、GABAは神経を「おさえる方向」に働かせます。

このふたつのバランスを「興奮と抑制のバランス(E/Iバランス)」と呼びます。
このバランスが崩れると、脳の情報のやりとりがうまくいかなくなります。
自閉症では、このバランスの乱れが大きな役割を果たしているのではないかと考えられてきました。
研究チームは、国際的に集められた二つの大規模な脳画像データベースを解析しました。
ABIDE1とABIDE2と呼ばれるもので、合わせて約800人の自閉症の人と同じくらいの数の発達に特性のない人のデータが含まれています。
年齢は子どもから大人まで幅広く、ただし知的障害のある人は対象から除かれました。
解析に使ったのは「安静時fMRI」と呼ばれる検査です。これは何も課題をせずにじっとしているときの脳の活動を調べる方法です。
研究者たちは「LCOR(局所的な同期性)」という指標を用いました。
これは、ある場所の脳の動きが周囲とどのくらい一緒に動いているかを示すものです。
たとえるなら「地域の人たちが同じリズムで足並みをそろえているかどうか」を見るようなものです。
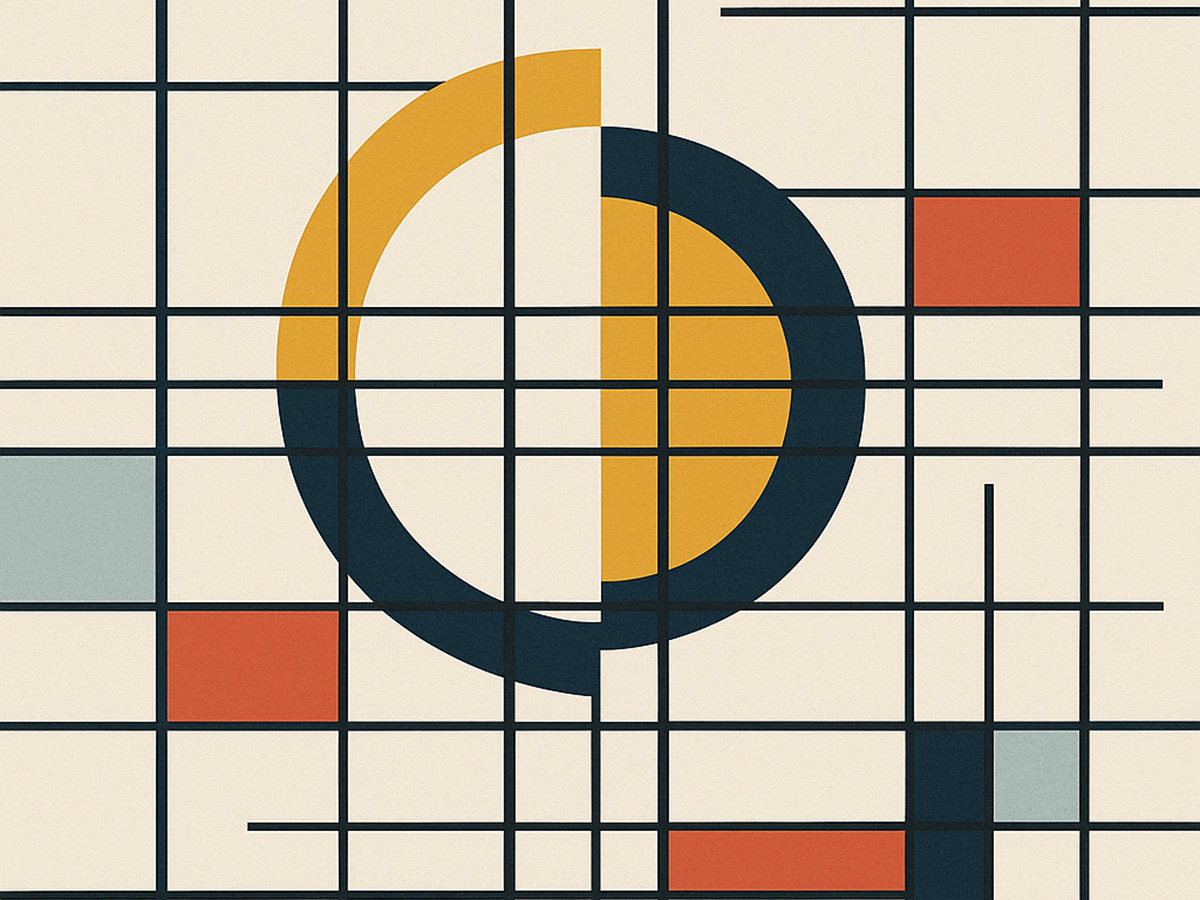
結果はとても一貫していました。
自閉症の人では、「デフォルトモードネットワーク(DMN)」と呼ばれる領域を中心に、周りと足並みをそろえる力が下がっていたのです。
DMNは、自分について考えたり、他人の気持ちを想像したりする時に働くネットワークです。
自閉症の人が「自分の気持ちや考えをまとめるのが難しい」「人の気持ちを理解するのに時間がかかる」といった特徴を持つとき、そこにはこのネットワークの動きの違いが関係している可能性があります。
次に研究者たちは、この脳の変化が神経伝達物質のどの分布と重なっているのかを調べました。
使われたのは、健康な人に対して撮られた分子イメージングのデータです。
すると、自閉症の脳活動の低下は、グルタミン酸を受け取る受容体(NMDA受容体やmGluR5)、GABAを受け取るGABAa受容体、そしてドーパミンやアセチルコリンといった物質を扱う仕組みとも関連していることがわかりました。
ドーパミンはやる気や運動、アセチルコリンは注意や学習にかかわる物質です。
つまり、自閉症に見られる脳の活動の違いは、一つの物質の異常ではなく、複数のシステムが広くかかわっているということです。

さらに研究者たちは、薬を使って人工的に脳のバランスを変えたときの変化を比べました。
使われた薬の一つは「ケタミン」です。
これはNMDA受容体をブロックし、脳の興奮と抑制のバランスを崩す働きをします。
もう一つは「ミダゾラム」という薬で、GABAの働きを強めて抑制を増やす方向に作用します。
27人の健康な男性を対象に、ケタミン、ミダゾラム、そして薬を使わないプラセボの3条件を順番を変えて受けてもらい、その脳の状態を測定しました。
すると驚くべきことに、ケタミンを投与したときの脳の活動のパターンが、自閉症の人に見られるものとよく似ていました。
自閉症で活動が下がっていた場所で、ケタミンも同じように活動を下げていたのです。
反対に、ミダゾラムの効果は自閉症のパターンとは一致しませんでした。
むしろ、自閉症で活動が増えていた領域をさらに強める方向に働いていました。
このことは重要な意味を持ちます。
ケタミンが作り出した脳の状態は、自閉症の人の脳の状態を再現していたのです。
これは、自閉症における脳の違いが神経伝達物質のバランスの乱れと関係していることを、直接示す証拠となります。
一方で、ケタミンは自閉症の症状を改善する薬にはなりません。
実際に行われた臨床試験でも、ケタミンは効果を示しませんでした。
それどころか、健康な人にケタミンを投与すると、社会的な理解の課題が難しくなり、幻覚のような症状が出ることも報告されています。
つまり、治療の方向性を考えるときには、ケタミンとは逆の方向に作用する薬が求められるということになります。
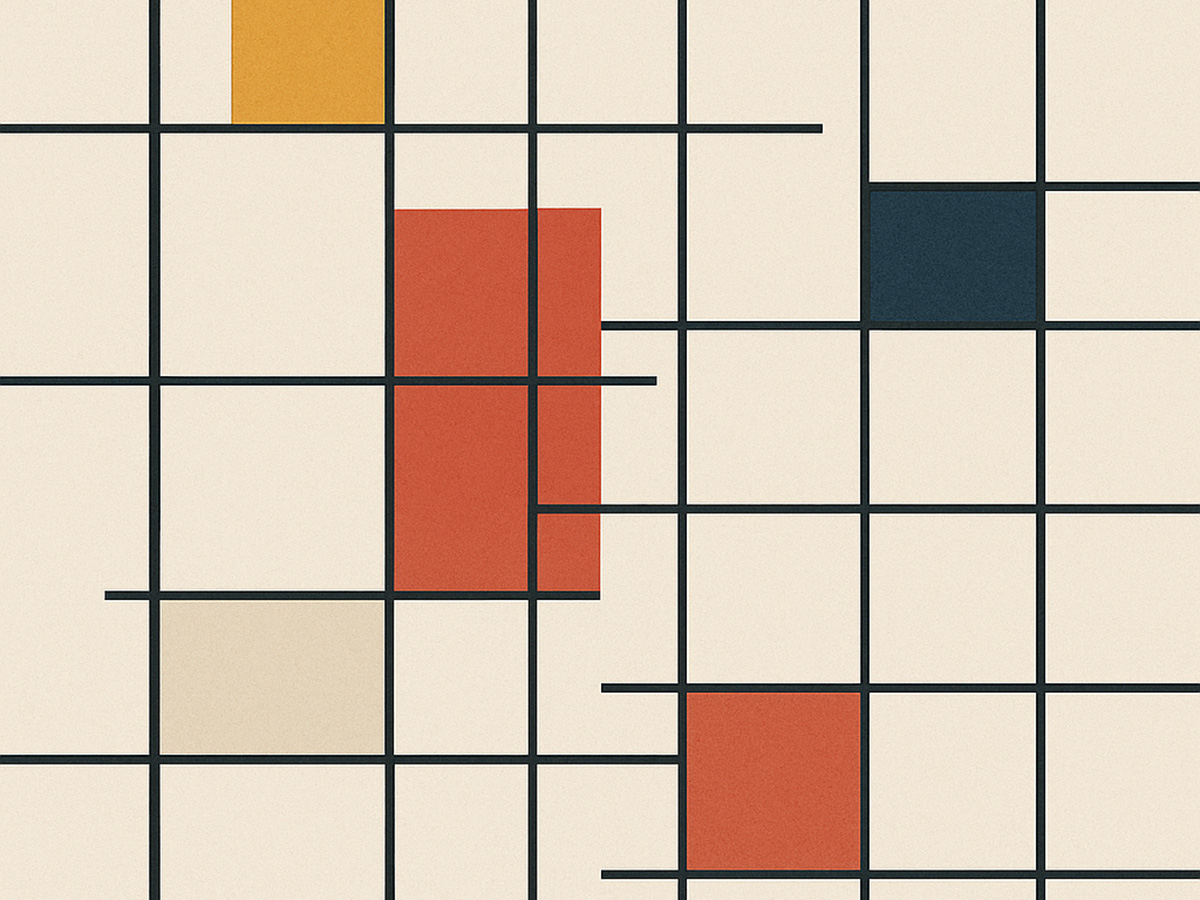
ただし、今回の研究でも、自閉症の症状の重さと脳活動の変化を直接結びつけることはできませんでした。
ADOSという診断指標で測られる「ことばのやりとり」「社会的相互作用」「くり返し行動」のスコアと脳活動との関連を調べましたが、一部に弱い関連が出ても統計的に厳密にすると消えてしまいました。
つまり、今回の結果は自閉症全体の特徴を示しており、個々の人の症状を説明するものではありません。
この研究の限界もあります。
対象は知的障害のある自閉症者を含んでいないこと、薬の実験は健康な男性だけで行われたこと、そして解析は集団全体の平均に基づいていることです。
そのため、自閉症の多様なタイプや個人差をすべて反映しているわけではありません。
しかし、二つの大規模データセットで再現性のある結果が得られたことは、とても信頼性の高い成果といえます。
自閉症は一人ひとり違いが大きいとよく言われます。
それでも共通して見えてきた脳の活動の特徴があり、それが神経伝達物質の広範なかかわりと結びついていることが今回明らかになりました。
今後は、自閉症のなかのタイプごとに違う脳の特徴を見極め、それに応じた支援や治療を考えていくことが期待されます。
(出典:nature communications DOI: 10.1038/s41467-025-63857-6)(画像:たーとるうぃず)
自閉症の子の脳では「グルタミン酸やGABAなど、神経のスイッチを入れたり切ったりする物質のバランス」が広い範囲で違っているということです。
自閉症は、脳の中の仕組みに根ざしているという強い裏付けになる研究結果です。
(チャーリー)




























