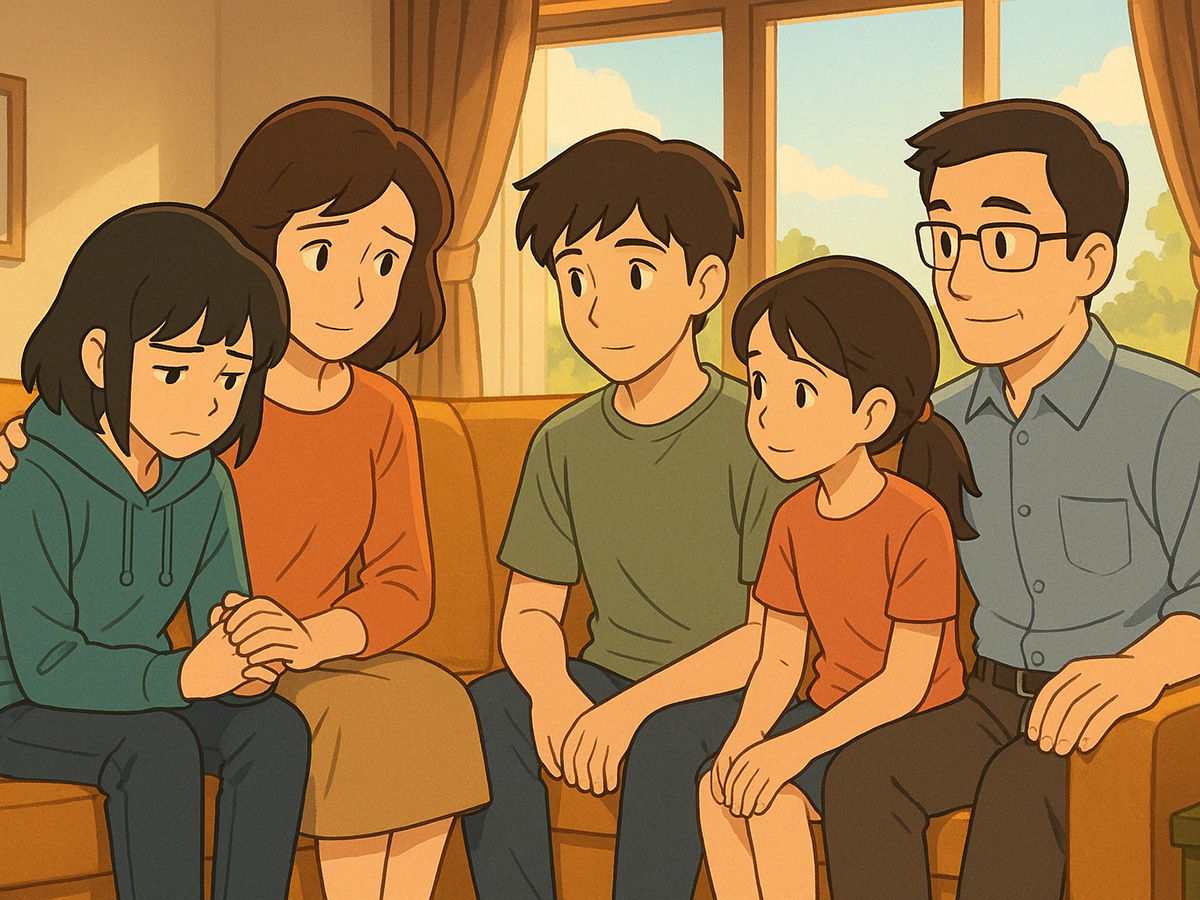
この記事が含む Q&A
- 思春期の自閉症の子どもを持つ家族がレジリエンスを高めるには?
- 意図的なつながりを保ち感情を共有する工夫や、家族ミーティング、個別の時間づくりなどが有効で、回復力を誇る子ども自身の声も重要です。
- 行動の難しさが家族関係へ与える影響と対処は?
- 自傷や不安、過刺激などの課題は支援不足や誤解から生じることが多く、相互理解と粘り強さを高める工夫が求められます。
- 支援の必要性と社会的理解はどのように関係する?
- レスパイトやストレス低減の仕組み、社会全体の理解が家族の余力回復と健やかな関係づくりに重要です。
自閉症のある思春期の子どもとその家族が、日常の中でどのように関係を築き、困難に向き合い、そして強さを見いだしているのかを明らかにする研究が行われました。
この研究は、豪オーストラリアン・カトリック大学子ども保護研究所が、オーストラリアのキャンベラに住む18の家族、合計40人を対象に、半構造化インタビューを通じて質的に分析したものです。
参加したのは母親、父親、きょうだい、そして自閉症の思春期の子ども本人です。
従来の研究が幼少期や成人期に焦点を当てることが多かったのに対し、この研究は思春期という特別な時期における家族の経験を深く掘り下げています。
家族の語りから浮かび上がったのは、5つの主要なテーマでした。
第一は「意図的なつながりとレジリエンス」です。
多くの家族は、強い結びつきを保つために意識的に努力していました。
たとえば、一緒に思い出を共有したり、感情を言葉にして表現することを大切にしたりする姿勢が見られました。
ある母親は「気持ちを正直に伝えることは、抑え込むよりも長期的には力になる」と語りました。
また、自閉症の思春期の子ども自身も「自分は立ち直るのが早い、すぐに気持ちを切り替えられる」と自分の回復力を誇りにしていました。
こうしたレジリエンスの感覚は、家族全体の安定に寄与していることがわかります。
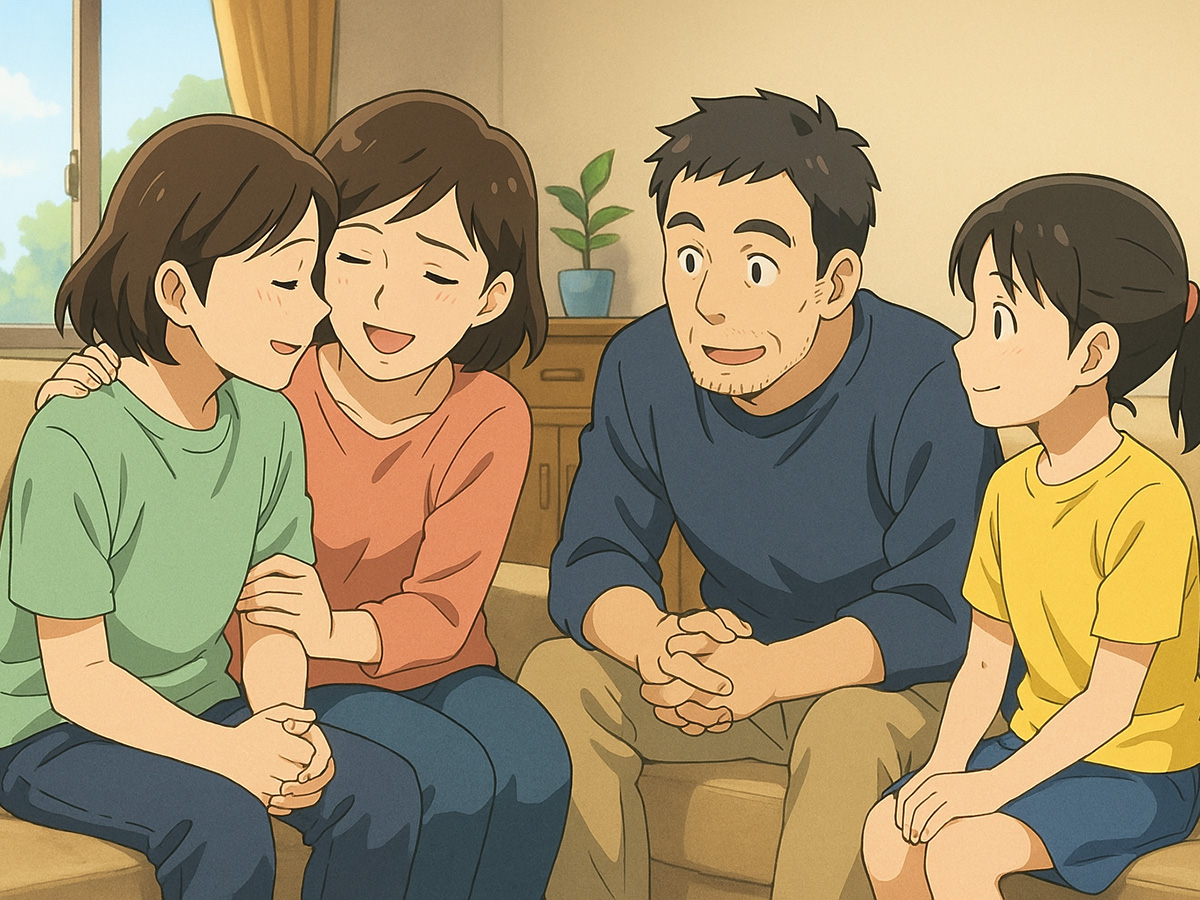
第二のテーマは「行動や感情の難しさが関係に与える張力」です。
家族の多くは、自傷、不安、過刺激、怒り、感情の理解の難しさといった課題を挙げました。
こうした行動はしばしば「わざと」ではなく、支援の不足や誤解から生じるものでした。
親やきょうだいにとっては大きなストレス源となり、家庭内の緊張を高める要因にもなっていました。
しかし同時に、家族はそれを乗り越える方法を模索し、相互理解や粘り強さを高めていきました。
父親の一人は「忍耐や理解を学び、自分はよりよい父親になれた」と語っています。
第三は「支援負荷とレスパイト(休息)の必要性」です。
継続的な介護やサポートが求められるなかで、家族は疲弊しやすくなります。
十分な休息や一時的に支援を代わってもらえる仕組みがないと、余裕を失い、関係にさらなる摩擦が生じることが明らかになりました。
とくに母親たちは「家族全体が少しでも休める時間が必要だ」と訴えていました。
レスパイトの不足は、子ども本人だけでなく、きょうだい関係や夫婦関係にも影響していました。
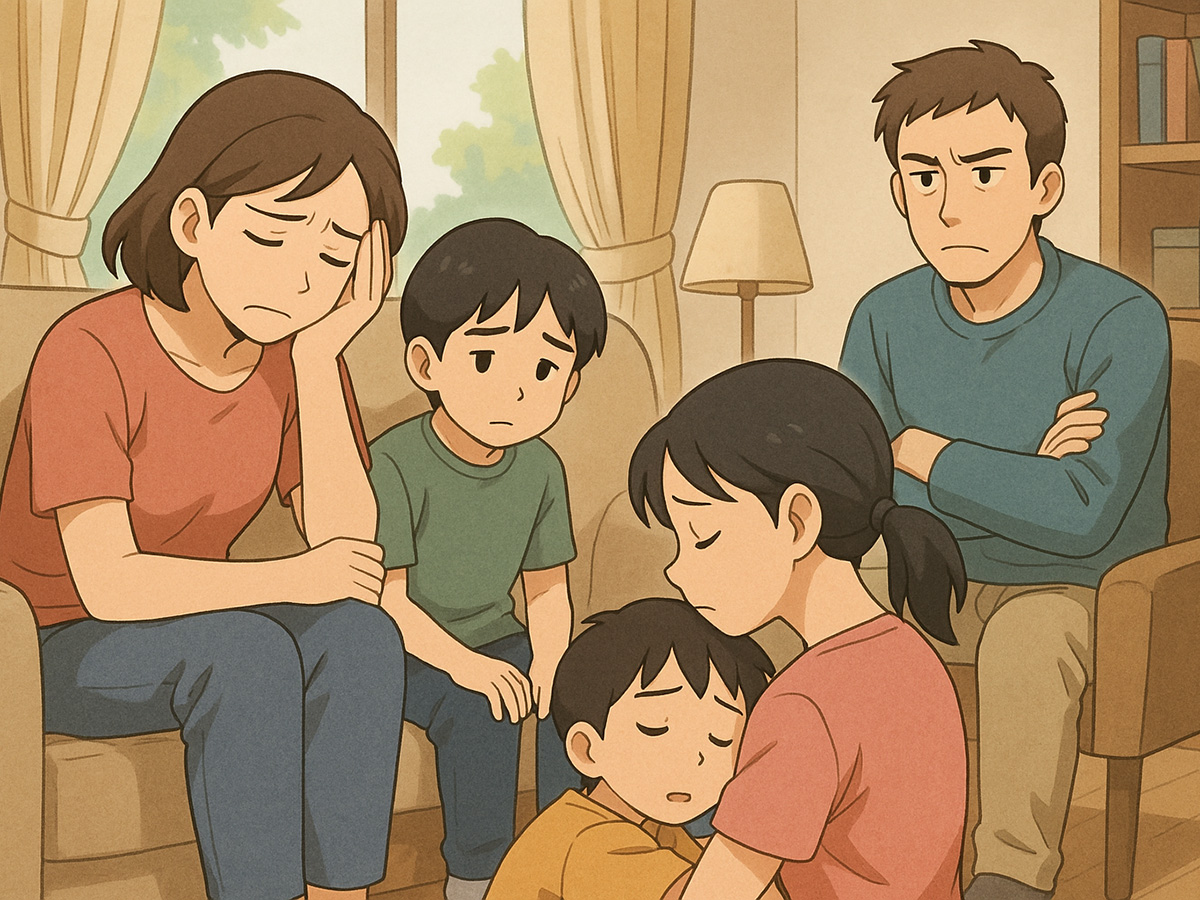
第四は「自閉症が家族の日常を形づくる中心要素になること」です。
予定の立て方や外出先の選択、誰と交流するかといった家族の暮らしの細部が、自閉症の特性を軸に組織されていました。
たとえば「静かな場所を優先して選ぶ」「人混みを避ける」など、日々の判断が家族の関係性を変えていくのです。
このプロセスの中で、家族は柔軟に適応しようとしましたが、同時に「自分たちの日常はほかの家庭と違う」という意識も強まりました。
第五は「ふつう/多様性という自己像の揺らぎ」です。
ある家族は「私たちはごく普通の家庭だ」と捉えていましたが、別の家族は「私たちは神経多様な家族であることを誇りに思う」と自己定義していました。
いずれの立場も、それぞれの家族が偏見や誤解に向き合うなかで形成されたものです。
家族は、自分たちのあり方を社会の中でどう位置づけるかを模索し続けていました。
この点で、家族が外部からの偏見に対してバッファ(緩衝材)を持つことの重要性が示されました。
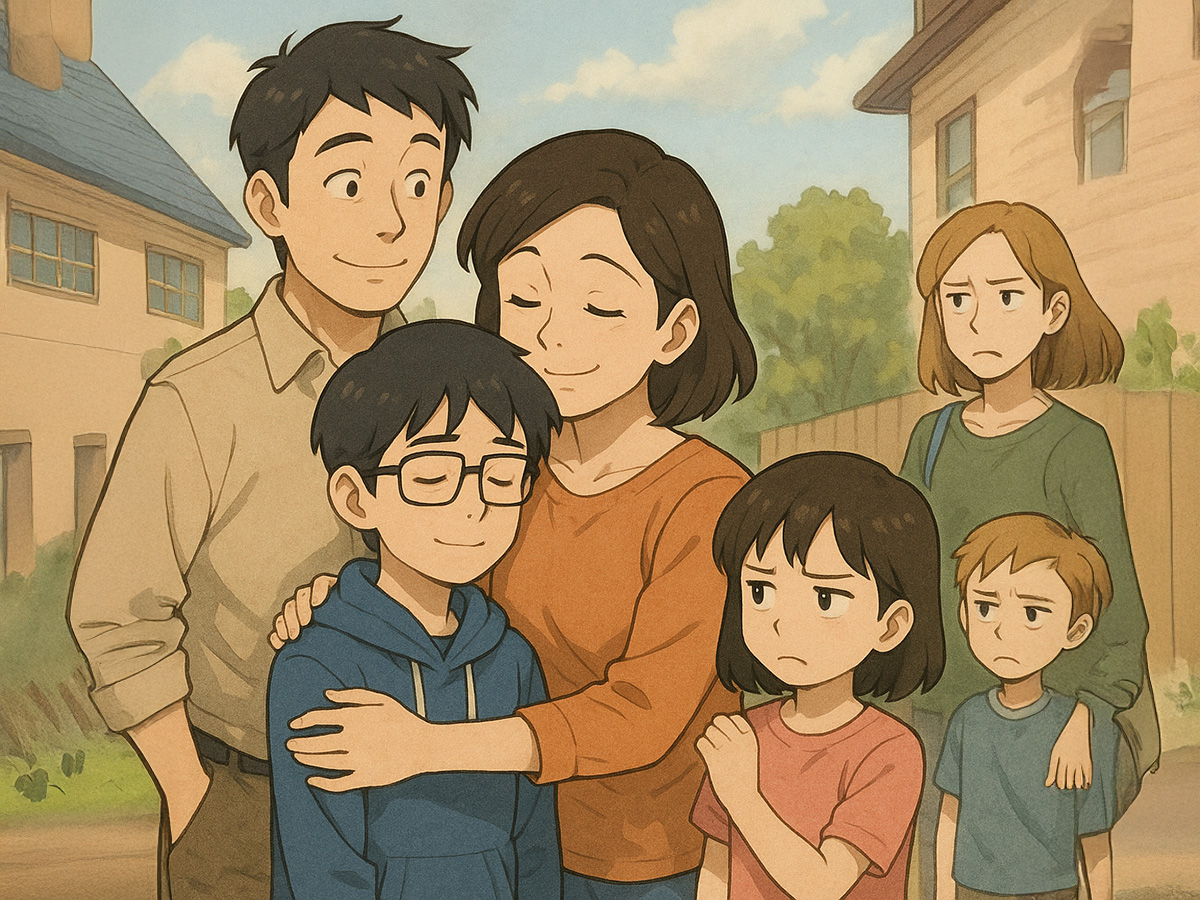
研究はまた、家族が見出した多様な実践的工夫も記録しました。
たとえば、週1回の「家族ミーティング」を行い、「よかったこと」「困ったこと」「来週のルーティン」を確認する家庭。
冷蔵庫に「感情の温度計」を貼り、数値が上がったら“クールダウン場所”に移動するという合図を活用する家庭。
きょうだいの一人ひとりと短時間でも個別の時間を持つ工夫をする家庭。
これらはいずれも、日常の中で安心感とつながりを保つための仕組みとして有効に機能していました。
この研究は、社会的アイデンティティ理論を枠組みにして、家族がどのように「自分たちはどんな存在か」を語るのかに注目しました。
その結果、家族が自閉症を「ネガティブなラベル」としてではなく、「自分たちを形づくる一部」として捉えることで、前向きな結びつきやレジリエンスを高められることが示されました。
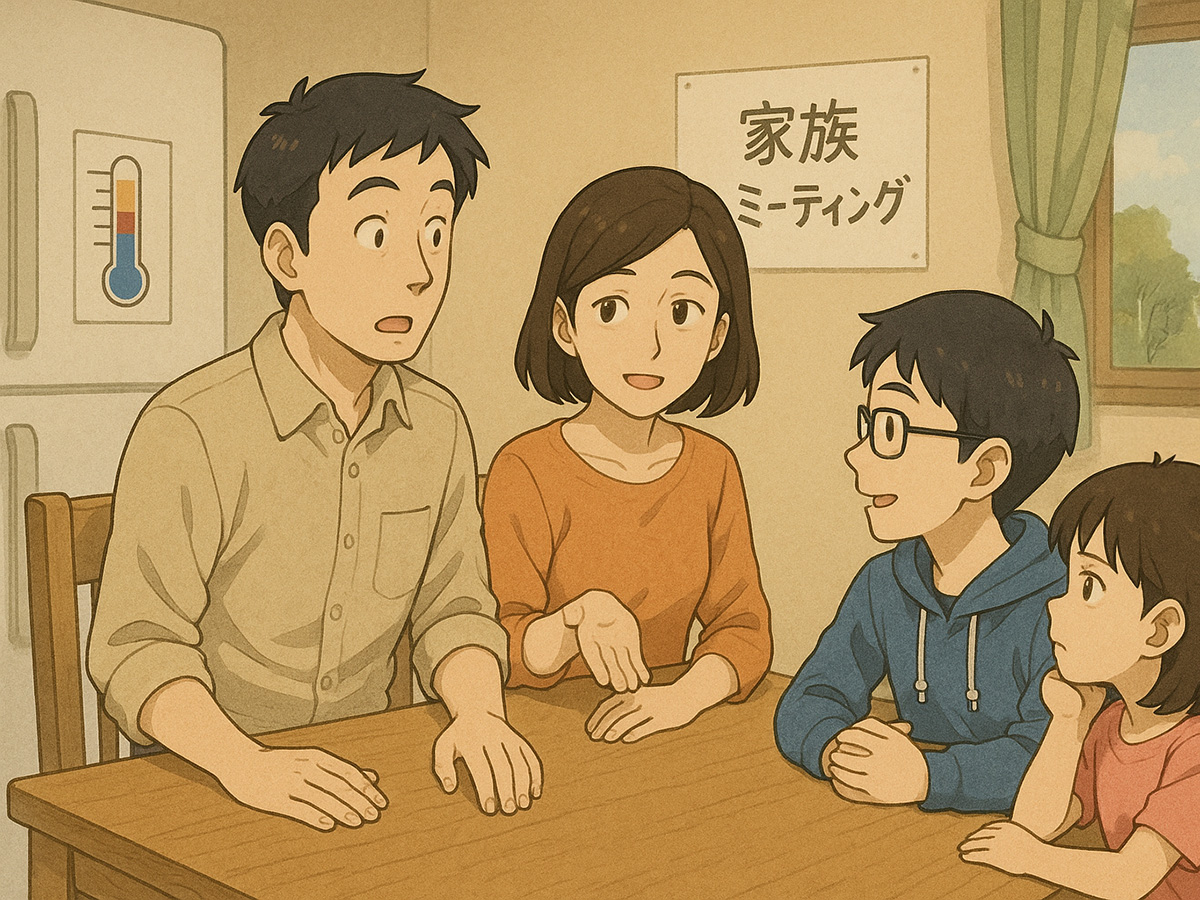
家族にとって大切なのは「全員がいつも仲良くすること」ではなく、「互いの違いをどうやって交渉し合うか」だと理解している家庭も多くありました。
この研究の結論は明確です。
自閉症は確かに家族関係に大きな挑戦をもたらします。
しかし、家族はその挑戦に押しつぶされるのではなく、むしろ工夫や粘り強さを通じて、より強く、より結びついた存在になっていけるのです。
その過程で必要とされるのは、社会全体からの理解と支援です。
心理教育やペアレントトレーニング、確実なレスパイト、地域でのピアサポート、マインドフルネスなどのストレス低減の仕組みは、家族が余力を取り戻し、より健やかな関係を築くために重要だと指摘されました。
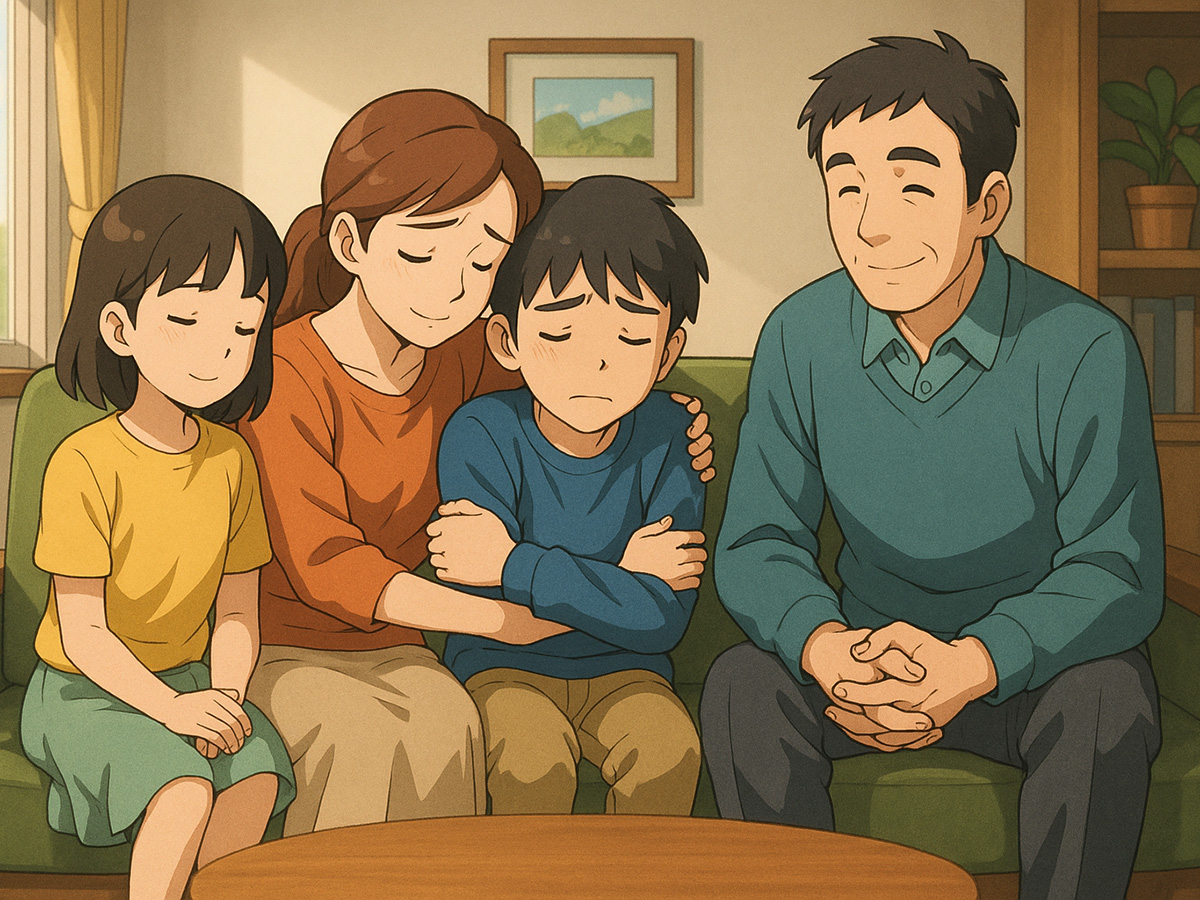
この研究には限界もあります。
参加者がオーストラリアの特定地域に限定されていること、人数が限られていること、分析が主に研究者一人によって進められたことなどです。
それでも、自閉症の思春期の子ども自身の声を含め、家族全体の関係を多角的に描き出した点は大きな意義があります。
最終的に、この研究が示したのは「家族は挑戦を抱えながらも、そこから強さを引き出せる」ということでした。
自閉症が家族に与える影響は大きいものの、それを通じて得られる新しい形の結びつきもまた存在するのです。
この知見は、同じような状況にある家庭にとって希望となり、また支援者や教育者にとっても、より家族全体に目を向けた支援を考える手がかりになるでしょう。
(出典:Journal of Autism and Developmental Disorders DOI: 10.1007/s10803-025-07034-0)(画像:たーとるうぃず)
うちの場合は、とくに意識することもなく、無事に幸せに過ごしてこれました。
ありがたい限りです。
(チャーリー)





























