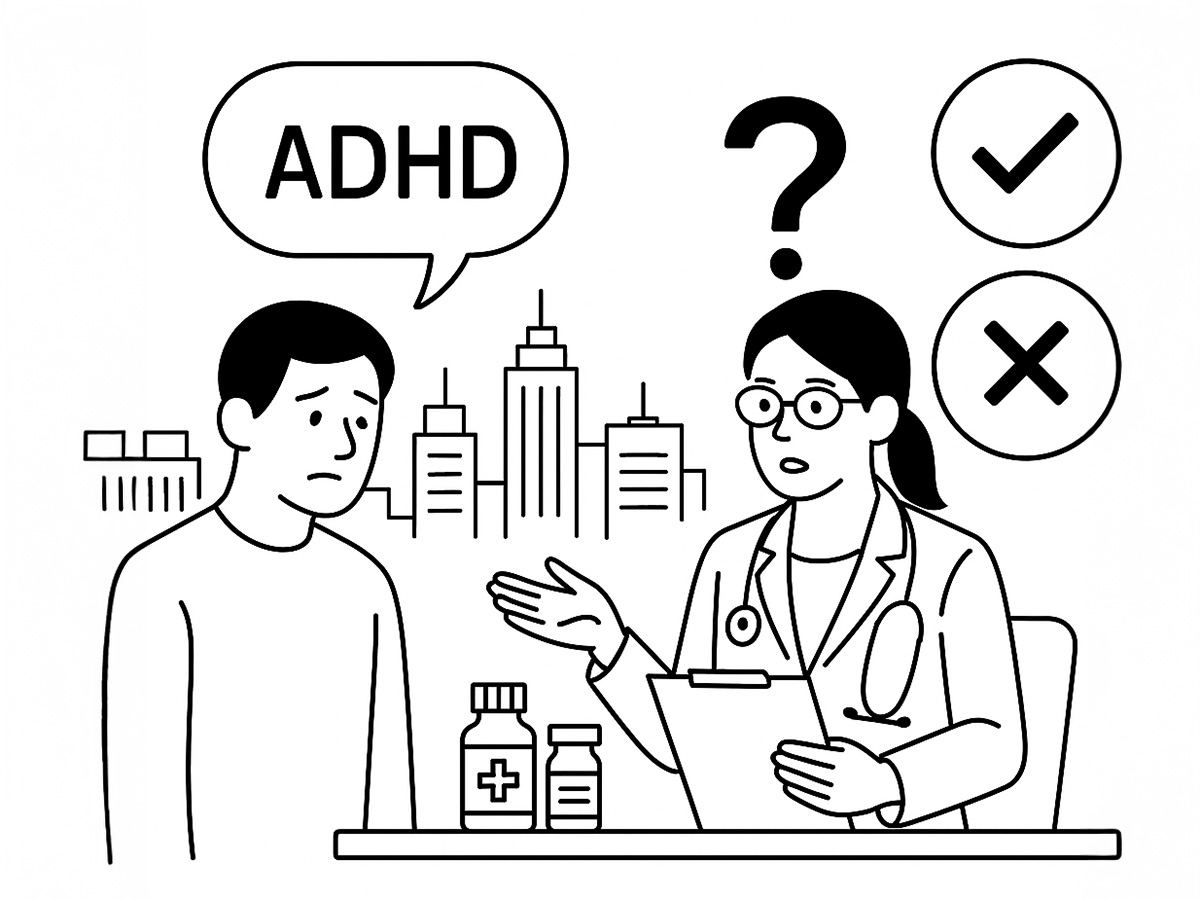
この記事が含む Q&A
- 診断が急増している背景にはどんな要因があるのですか?
- DSM-5-TRの基準変更や診断の手続きの不十分さ、自己申告の偏り、スマホ依存などが挙げられます。
- 診断を行う際に重要なあるべき手順は何ですか?
- 子どもの頃からの経過と複数場面の困難の確認、他の原因の除外、第三者情報の活用が推奨されます。
- ハイパーフォーカスを診断の根拠とすべきでない理由は何ですか?
- ハイパーフォーカスは診断基準そのものではなく、根拠にはならないためです。
子どもが「集中できない」「落ち着かない」と感じたとき、多くの親は「もしかしてADHDではないか」と心配になります。
学校や家庭での困りごとが続けば、支援の必要性を考えるのは当然のことです。
大人になってからも同じように「自分はADHDではないか」と悩む人が増えています。
いまアメリカでは、大人の注意欠如・多動性障害(ADHD)の診断が急速に増えています。
その結果、メチルフェニデートやアンフェタミンといった刺激薬の処方も急増し、薬が不足する事態まで起きています。
この現象に対して「診断が本当に必要な人に行われているのか、それとも行きすぎているのか」という議論が盛んになっています。
この問題について整理を行ったのが、ユタ大学スペンサー・フォックス・エクルズ医学部 と インターマウンテン・ヘルス に所属する研究者による解説論文です。アメリカの医療現場を背景にしていますが、その指摘は、日本で暮らすADHDの当事者や子どもの親、学校や地域で支援に関わる人々にとっても学ぶところが多くあります。
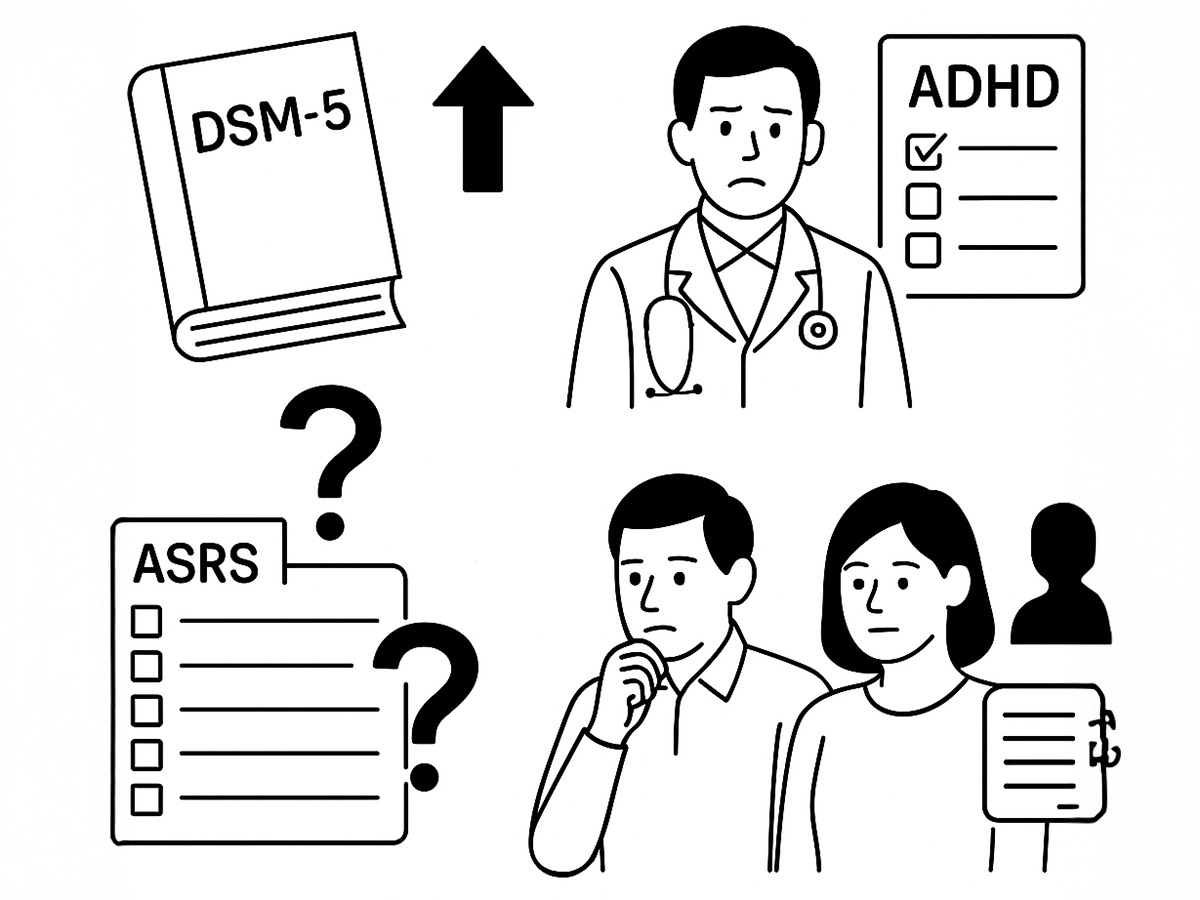
診断が急増している背景にはいくつかの要因があります。
まず、診断基準の変更です。
国際的に広く使われるDSM-5-TRでは、ADHDの発症年齢が「7歳未満」から「12歳未満」に引き上げられ、大人に必要な症状の数も「6項目」から「5項目」に減りました。
この変更は診断から漏れていた人を救うためでしたが、同時に診断のハードルを下げ、誤って診断されやすい環境も生み出しました。
診断の手続きが十分でないことも問題です。
診療の忙しさや保険制度の仕組みの中で、ADHDのスクリーニング質問票(ASRSなど)がそのまま診断に使われてしまう場合があります。
本来スクリーニングは受診を促すための入口であり、診断を確定するものではありません。
感度が高いために「陽性」と出やすく、実際にはADHDではない人まで含んでしまう可能性があります。
さらに、大人の診断では自己申告に頼りすぎる傾向があります。
子ども時代を振り返るとき、人は現在の悩みや苦しみの影響を受け、正確な記憶ではなく歪んだ思い出を語ってしまうことがあります。
親や配偶者、学校の成績表や記録といった第三者の情報がなければ、誤った診断につながる危険があるのです。
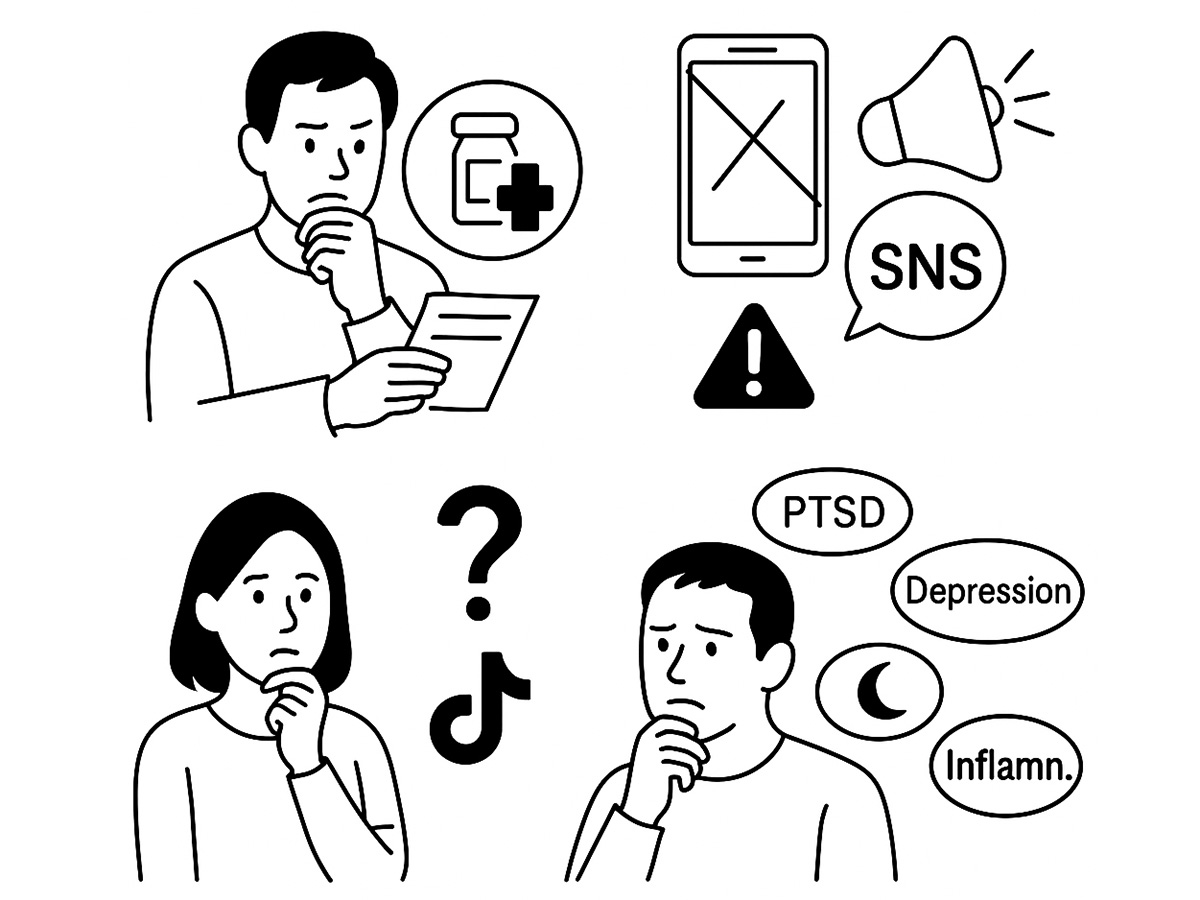
加えて、意図的に症状を誇張する場合もあります。
学業上の配慮を得るためや、薬を手に入れるために症状を作り出すケースです。
診断が広がりすぎると、こうした詐病を見抜くことが難しくなり、本当に支援が必要な人が取り残される恐れがあります。
現代特有の要因として、スマートフォンやSNSの影響もあります。
絶え間ない通知や動画は集中を分断し、誰でも注意が散漫になりやすくします。
こうした環境のなかで「自分はADHDではないか」と考える人が増え、TikTokなどに広まる不正確な情報が誤解を助長しています。
しかし、注意力の低下は必ずしもADHDだけによるものではありません。
不安障害やうつ病、PTSD、双極性障害、睡眠不足や睡眠時無呼吸、カフェインの取りすぎ、甲状腺の病気や慢性の炎症など、集中を妨げる要因は数多くあります。
大人になってから初めて注意の問題が現れるように見える場合、その背後にはこうした要因が隠れていることが少なくありません。

過剰診断を防ぐために求められるのは、診断を丁寧に行うことです。
DSM-5-TRの基準を正しく守り、子どもの頃から症状があったか、複数の場面で困難があるかを確認すること。
ほかの原因を除外すること。
自己申告に偏らず、必ず第三者からの情報を取り入れること。
スクリーニングは診断の代わりではないと理解すること。
そして、症状の数だけでなく、仕事や生活に具体的な困難があるかどうかを確かめることです。
よく語られる「ハイパーフォーカス」と呼ばれる没頭の傾向はADHDに関連して語られますが、診断基準そのものではありません。
これを診断の根拠とするのは誤りです。
アメリカでの議論は、日本に住む私たちにとっても重要な意味を持ちます。
集中力の問題は誰にとっても身近だからです。
睡眠不足やストレス、スマートフォンの使いすぎでも同じような症状は現れます。
本当にADHDなのかを見極めるには、子どもの頃からの経過や生活の中での困難を丁寧に振り返る必要があります。
診断が広がりすぎれば、不必要な薬の使用や副作用のリスクが増えるだけでなく、本当に支援が必要な人が正しい治療にたどり着けなくなる恐れがあります。
だからこそ、診断を慎重に行うことは本人にとっても社会にとっても欠かせない課題なのです。
(出典:healthcare DOI:10.3390/healthcare13182367)(画像:たーとるうぃず)
「診断が広がりすぎれば、不必要な薬の使用や副作用のリスクが増えるだけでなく、本当に支援が必要な人が正しい治療にたどり着けなくなる恐れがあります。」
支援が必要であるにもかかわらず支援を受けることができていない。
そうした人たちをこぼしてしまうことはなくさなければなりません。
(チャーリー)





























