
この記事が含む Q&A
- 大人のADHDは診断されにくいのですか?
- 不注意や実行機能の弱さは外から見えにくく、診断が遅れることがあります。
- ADHDの原因は一つだけですか?
- いいえ、遺伝的要因と環境的要因が複雑に絡み合って発症します。
- ADHDは「流行」だと誤解されやすいのですか?
- はい、診断基準の整備と情報流通によって可視化されただけで、流行ではありません。
近年、ADHD(注意欠如・多動症)と診断される人が急増し、とくに大人で顕著になっています。
イギリスでは2000年以降、診断件数が約20倍に跳ね上がり、大人の診断数は直近10年間で7倍に達しました。
さらに2021〜22年の1年間だけでADHD治療薬の処方は20%も伸び、ついに子どもより大人の処方量が上回りました。
世界全体の有病率は3〜5%と推定され、最低でも2億4千万人に達します。
それでも大人では依然として未診断の人が多数いて、「流行だ」「怠け者の言い訳だ」とする誤解が根強く残っています。
こうした誤解は、ADHDへの理解が十分に進んでいないことに起因します。
まず、ADHDの「原因」をひとつに絞ることはできません。
研究によれば、ADHDは複数の要因が複雑に絡み合って発現します。
ADHDの脳では、前頭前野や頭頂葉など自己制御や計画性に関わる領域の皮質が平均より薄いことが多い一方、脳内各部をつなぐ白質はやや増加する傾向が示唆されています。
白質の過剰は回路の「ノイズ」を招き、集中や制御を難しくします。
また、デフォルト状態(ぼんやり考えごとをする状態)と課題状態(ひとつの作業に専念する状態)の切り替えがうまくいかず、心がさまよいやすいのも特徴です。
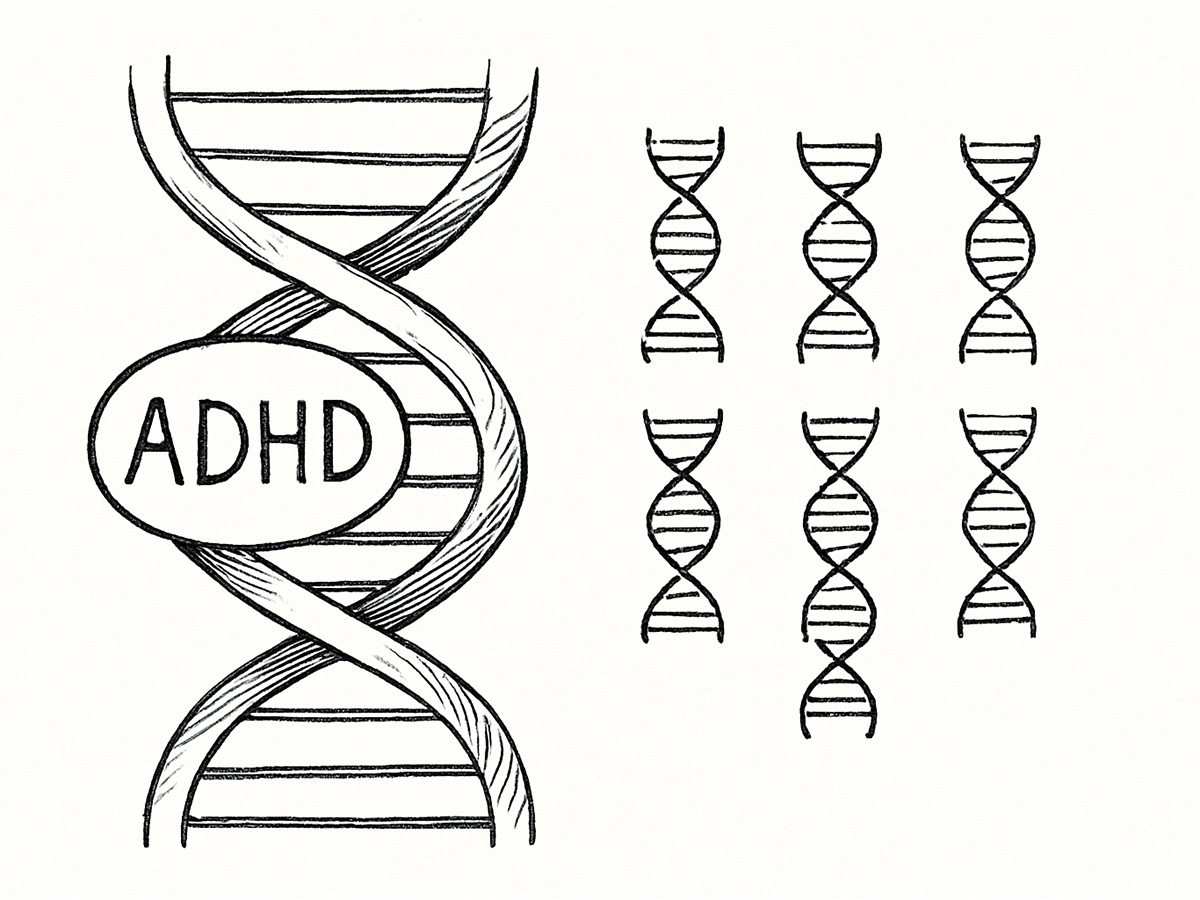
ADHDは高い遺伝率をもち、推定80%が遺伝的要因に関連します。
関与する遺伝子は現在までに少なくとも76種類が報告され、要因は1本の「ADHD遺伝子」に収まりません。
環境的要因も無関係ではありませんが、その多くは胎児期のアルコール曝露や出産時のトラブルなど「お腹の中」で起こるものです。つまり、「育て方」や本人の努力不足で起こるわけではありません。
ADHDは「発達障害」に分類され、子どものころに目立ちやすい多動が診断の入り口になるため「子どもの病気」というイメージが強く残っています。
多動は大人になるにつれ落ち着く場合が多いのですが、不注意や実行機能の弱さは持続しやすく、生活の質に大きく影響します。
しかし外からは見えにくいため、周囲も本人も気づきにくいのが実情です。
大人のADHDではうつ病・不安障害・依存症などが前景化しやすく、医療機関でもそちらが優先されてADHD診断が後回しになることが少なくありません。
作家で博物館勤務のダン・ミッチェルは、大人になってようやく診断された経験を振り返り「もし早く分かっていれば、逃した学習機会や人間関係はもっと少なかった」と語ります。
男女差の問題も深刻です。
ADHDはやんちゃな男の子の症状として語られることが多く、実際に臨床現場でも男児の診断が目立ちます。
診断基準が多動や衝動的行動に比重を置いているため、内向的で不注意型の女児は見逃されがちです。
研究者エリナッド・パロットは「目立たずに困っている子は“普通”とみなされる。誰かが椅子を投げるまでは問題にならない」と指摘します。
女性は未診断のまま自己肯定感を損ない、進学や就労の機会に制限を受けるケースが後を絶ちません。
ADHDに関する認識が進んだことで女性の診断例は増えていますが、「女の子には関係ない」という根深い思い込みの払拭には時間がかかります。
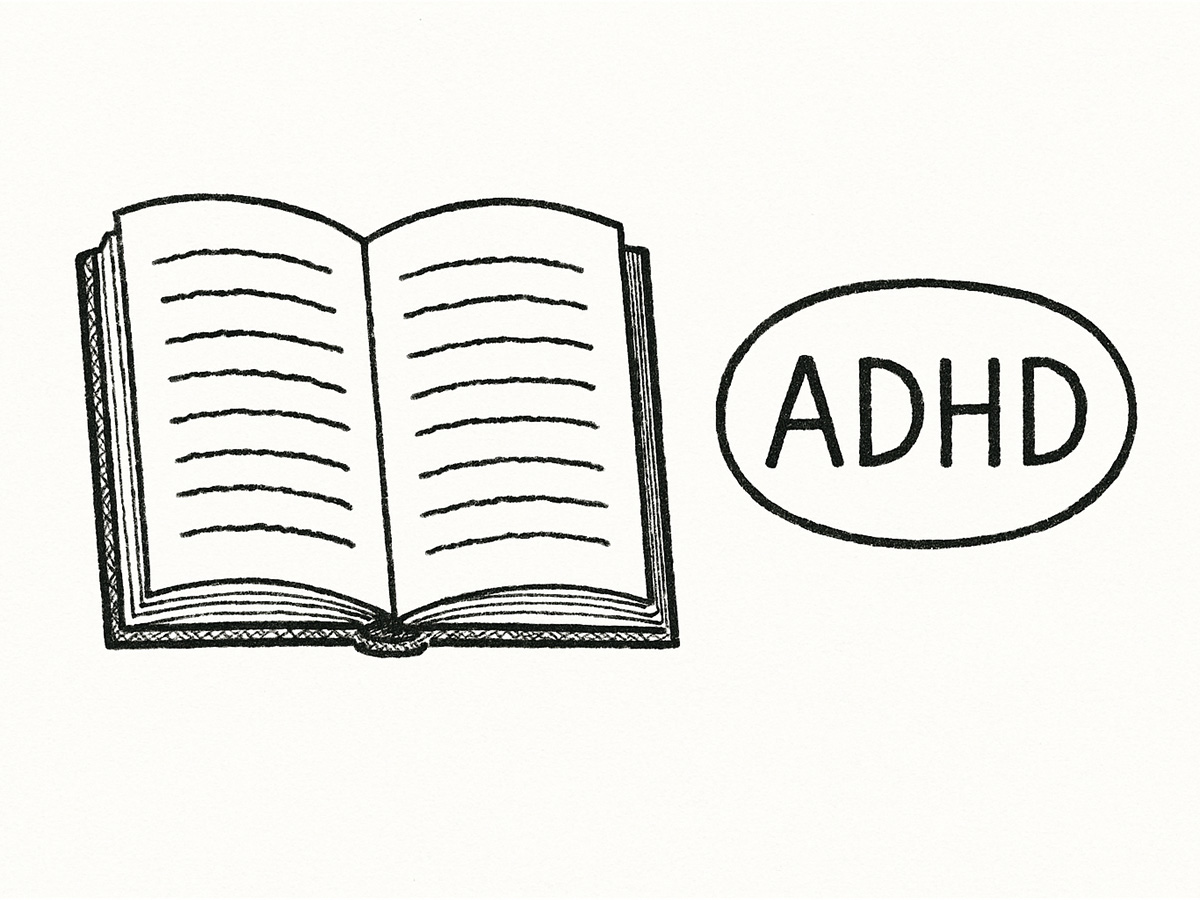
ADHDは「新しい病気」でも「現代の産物」でもありません。
症状は18世紀末の医学書にすでに記述があり、さらに昔から存在していたと考えられます。
私たちが今になって大人のADHDを「発見」している背景には、診断基準の整備と情報流通の急拡大があります。
スマートフォンやSNSはADHDそのものの原因ではありませんが、自分の困りごとに気づくきっかけや、同じ経験を持つ人とつながる場を提供し、医療へのアクセスを後押ししています。
カタ・ブラウンが著書『It’s Not a Bloody Trend』で強調したように、ADHDの増加は単なる流行ではなく、ようやく可視化された現実なのです。
一方、ADHDを「障害ではなく強み」と捉える声もあります。
実験では、ADHD傾向のある人が「探索的思考」に優れ、新しい刺激を探す能力で成果を上げる場合があると示唆されています。
情報が洪水のように飛び交う現代社会では、並列的に注意を配れるADHDの特性がメリットになる場面も考えられます。
ただし、それは特定の環境下に限った話で、ほとんどの状況では学業・就労・人間関係で困難が先立ちます。
治療面では、中枢神経刺激薬(アデロールやリタリンなど)が症状軽減に高い効果を示しています。
定型発達者が「集中力アップ」を目的に乱用しても効果は乏しく、むしろ副作用が問題になります。
薬は骨折した脚に松葉杖を与えるような役割で、骨折自体を治すわけではないと作家ニック・ペティグリューは例えます。
服薬に伴う偏見や罪悪感は根強いものの、適切な薬物療法と心理社会的支援の組み合わせが生活の質を大きく高めることは、多くの研究と当事者の証言が裏づけています。
しかし、診断そのものや薬物療法に対する「楽をしている」「甘えだ」といった否定的な評価は依然として存在し、それが当事者を二重に苦しめます。
コメディアンで元ソーシャルワーカーのアンジェラ・バーンズは自身のADHD経験を公表したところ「流行に乗っているだけ」と冷笑されたと語り、「30年間の苦労を軽視しないでほしい」と訴えました。
私たちがADHDを正しく理解し支援を整えることは、当事者の尊厳を守るだけでなく、社会全体の経済的損失を減らすうえでも不可欠です。
未診断・未治療のADHDによる経済的損失は莫大だと試算されています。
ミスや遅延、生産性低下、失業、医療費の増大は社会全体を圧迫します。
「流行」視や自己責任論では、この損失を補うどころか拡大する一方です。
したがって、診断と支援を早期に届けるインフラ整備、学校や職場での合理的配慮、そして偏見の解消が急務です。
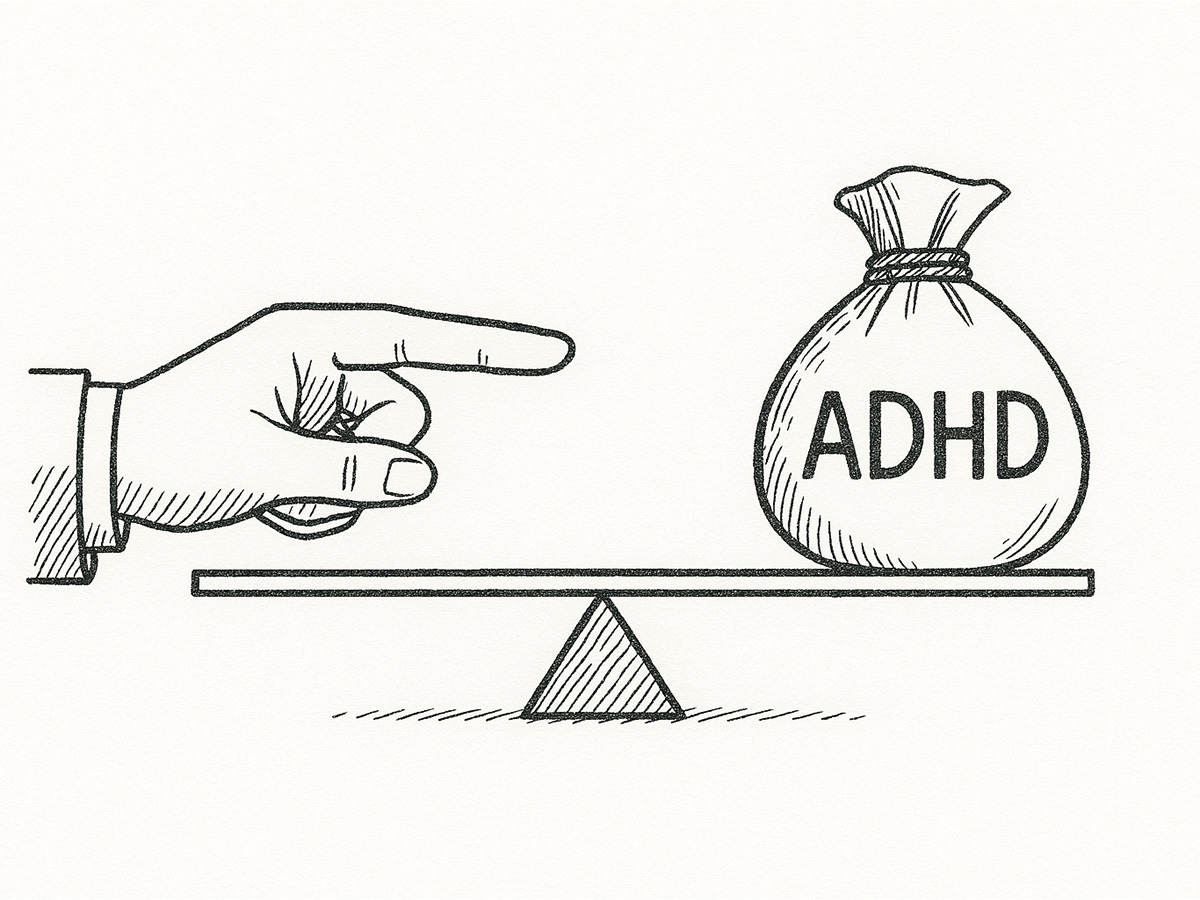
ADHDがスペクトラムであるように、当事者のニーズも多様です。
多動が落ち着いた大人でも、不注意やワーキングメモリの弱さは残ります。
女性や高学歴層、定職についている人も例外ではなく、支援策は一律では機能しません。
個々の強みと困難を丁寧に評価し、薬物療法・認知行動療法・コーチング・環境調整などを組み合わせる必要があります。
長期的には、学校教育や職場文化そのものが「典型的な脳」中心から脱却し、多様な認知特性を前提とした設計へ移行していくことが望まれます。
情報が溢れる現代においても、「ADHDはただの流行」という短絡的な見方が消えないのは残念です。
しかし、過去数十年で蓄積された科学的エビデンスと当事者の語りは、こうした偏見を覆すだけの力をもっています。
私たちは今、ADHDを正しく理解し、診断と支援を必要とする大人たちに手を差し伸べる転換点に立っています。
診断を受けた人が視界を晴らし、自分らしく歩むための杖を手にできるかどうか。その可能性は、社会全体がどれだけ偏見を手放し、柔軟に適応できるかにかかっています。
(出典:英BBC Science Focus)(画像:たーとるうぃず)
広く理解が進むことで、多くの方がもっと生きやすくなるはずです。
(チャーリー)





























