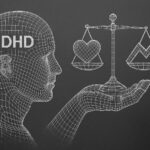この記事が含む Q&A
- なぜ血管は自閉症やADHDの理解に重要なのでしょうか?
- 血管は酸素や栄養を運ぶだけでなく神経の発達を導く道しるべとなり、神経の移動や脳の層構造・血流動態に深く関与します。
- 血管と神経の協力が乱れると、どんな影響が自閉症やADHDの特徴に現れるのでしょうか?
- 血管からの合図がニューロンの適切な位置づけを促し、血流の偏りや関門の機能低下が行動や発達に影響する可能性があります。
- 今後の研究が治療につながる可能性はありますか?
- 将来的には血管の役割を再現・調整する治療や再生医療の可能性が探られ、現行薬の血流・結合の整え方の理解にもつながると考えられます。
自閉症やADHDを持つ子どもや大人にとって、「なぜこうした特性が生まれるのか」という疑問は、多くの人にとって切実なテーマです。
保護者の方にとっては、わが子の行動の背景を少しでも理解したいという思いにつながるものでもあります。
ドイツの フランクフルト大学(Goethe University Frankfurt) の Acker-Palmer 教授らの研究グループ は、この問いに新しい視点を与える研究をまとめました。
研究グループは「血管」が自閉症やADHDの理解に欠かせない存在であることを強調しています。
血管は単に酸素や栄養を運ぶ通路ではなく、神経の発達を導くパートナーでもあるのです。
赤ちゃんの脳は、妊娠してすぐのころからつくられ始めます。
最初は「神経管」という細い管のような形から出発します。
その中には神経のもとになる細胞が並び、そこから新しい神経細胞が次々と生まれていきます。
その一部は「ニューロン」と呼ばれる、電気信号をやり取りする細胞になります。
ニューロンはそれぞれ決められた場所へと移動し、脳の表面にある「大脳皮質」という層を形づくります。
大脳皮質は、考える力や感情、行動のコントロールに関わるとても重要な場所です。
このとき、神経細胞の移動を助けるのが「放射状グリア」と呼ばれる細胞です。
放射状グリアは柱のように長く伸び、ニューロンはその上をよじ登るようにして外側へと向かいます。
こうしてニューロンが整然と並び、脳の六つの層ができあがっていきます。
もしこの移動がうまくいかないと、脳の層のバランスが乱れ、機能に影響が出ることがあります。
ここで忘れてはいけないのが血管の存在です。
血管は酸素や栄養を運ぶ通路であるだけではありません。
血管の内側を覆う「内皮細胞」は、神経細胞に合図を出し、「ここで止まるように」「ここから分かれるように」と発達を導いています。
さらに血管自体が道しるべになり、神経細胞の移動を助けています。
これはまるで新しい街の建設工事で、道路が先に整備され、その道に沿って人や物が動いていくようなものです。
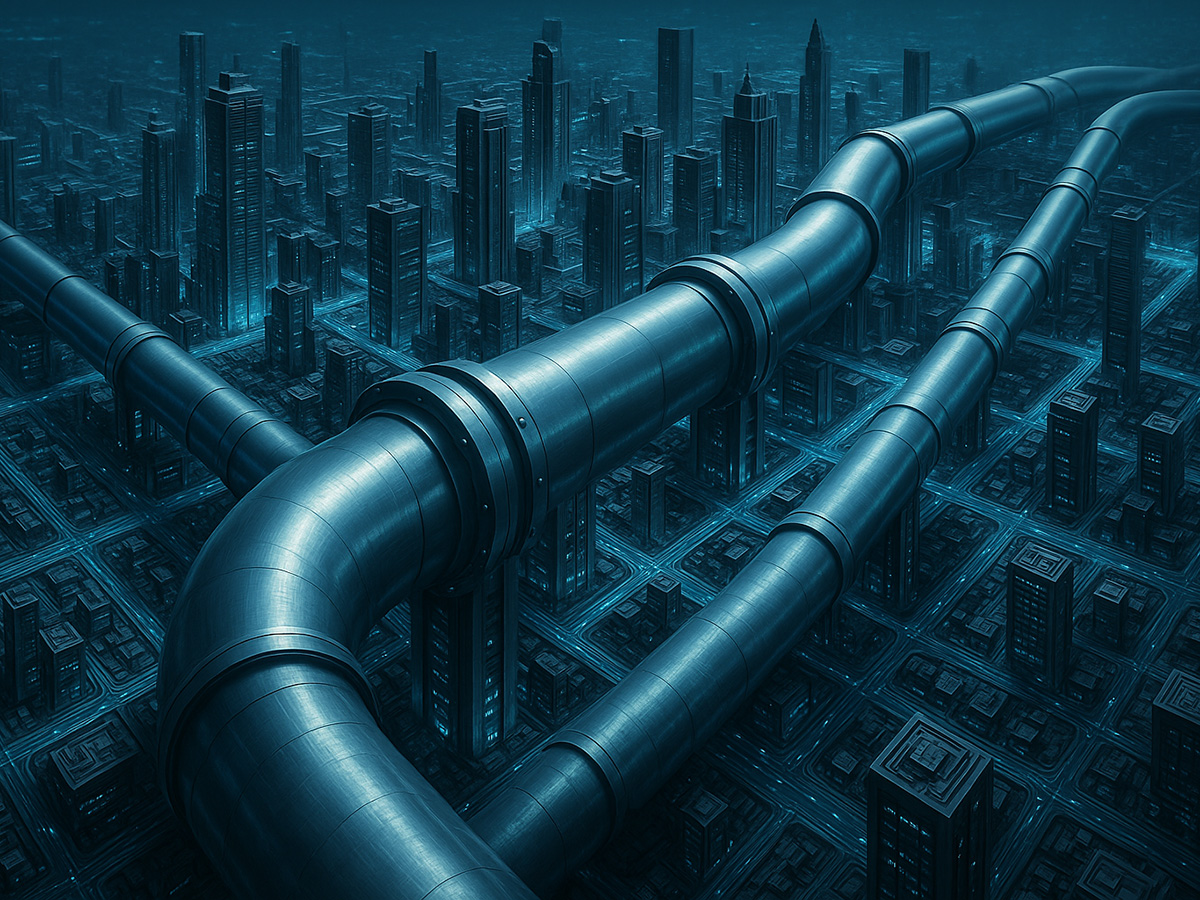
血管はまた「血液脳関門(けつえきのうかんもん)」と呼ばれる特別なバリアをつくります。
これは脳を守るための仕組みです。
血管の内側の細胞同士がぴったりとくっつき、必要なものだけを通す関門になっています。
たとえばブドウ糖は「GLUT1」という専用の入り口を通って運ばれますが、大きな分子や有害なものは通さないようにブロックされます。
胎児のころからこの関門はつくられ、妊娠12〜18週ごろには大人に近い状態になっています。
もしこの仕組みが弱まれば、脳は外からの影響を受けやすくなり、発達に影響することが考えられます。
神経の誕生のタイミングにも血管は深く関わっています。
脳の奥にある「増殖帯」という場所では、最初は酸素が少ない環境で神経のもとになる細胞が育っています。
そこで「VEGF(血管内皮増殖因子)」という合図が出され、血管が呼び寄せられます。
血管が近づき酸素が届くようになると、神経のもとがニューロンに変わり始めます。
つまり血管は、神経の誕生を「今だ」と知らせるスイッチの役割も果たしているのです。
ニューロンの移動にも血管の合図があります。
放射状グリアに沿って移動する細胞は、血管からのサインで正しい場所に止まります。
もしそのサインが乱れると、ニューロンが誤った場所にとどまり、脳の層構造が崩れてしまいます。
また、横方向に長い距離を移動する細胞は、血管がつくる通路を通って皮質に入ります。
血管がいわば「交通整理」をし、神経細胞が迷わないようにしているのです。

成長した後の脳でも、神経と血管の協力は欠かせません。
脳が働くとニューロンは大量のエネルギーを必要とします。
そのとき血管が反応し、血流を増やして酸素や栄養を届けます。
この仕組みは「神経血管カップリング」と呼ばれます。
脳の活動を画像としてとらえるfMRI(機能的MRI)は、この血流の変化を利用しています。
血管の反応があるからこそ、私たちは外から脳の働きを測ることができるのです。
こうした血管と神経の協力関係が乱れると、自閉症やADHDの特性と関わる可能性があることが示されています。
自閉症では、発達が進んでも脳の中で血管をつくる合図が高いまま残っていたり、血液脳関門の構造に変化があったりします。
また安静時の脳血流が偏っていることも報告されています。
さらに、栄養の出入りを調整する仕組みに異常があると、脳の中のバランスが崩れ、行動や発達に影響を及ぼす可能性が指摘されています。
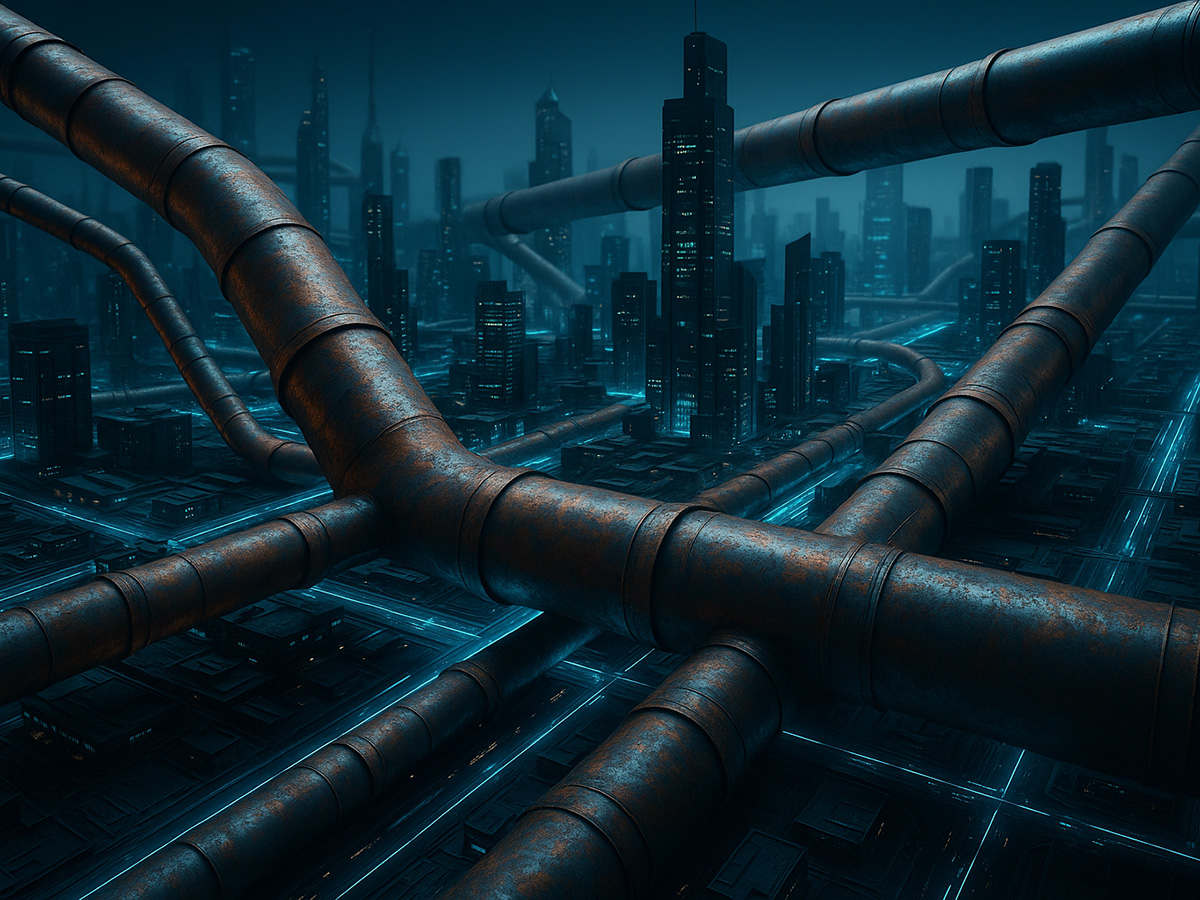
ADHDでは、血液脳関門がゆるむ兆候が動物の研究で見つかっています。
関門を支える成分が減り、逆にそれを壊す酵素が増えることでバリアが弱まるのです。
また、人の研究では、注意や行動をコントロールする前頭前野や線条体といった場所で、血流が少なかったり、つながり方が偏っていたりすることがわかっています。
ADHDの治療薬であるメチルフェニデートは、こうした血流やつながりを整える方向に作用していることが観察され、薬が効く仕組みを説明している可能性があります。
研究の中では統合失調症にも触れられていますが、ここでは背景として簡単に紹介します。
統合失調症は分類上は自閉症やADHDとは異なる病気ですが、血液脳関門や血流の異常が見られることから、脳の発達と血管の関係を理解するための比較対象として研究されています。
著者たちは最後に、まだ解けていない課題を指摘しています。
血管をつくる細胞は場所によって性質が違いますが、その違いがどうやって生まれ、神経の発達にどのように影響するのかはよくわかっていません。
また、子どもの脳で血管が持っていた「道案内の役割」を、大人の脳の治療や再生医療でどう再現するかも大きな課題です。
もしその仕組みを理解できれば、将来の治療に役立つ可能性があります。
まとめると、フランクフルト大学の研究グループが示したのは、「血管は単なる補給路ではない」ということです。
神経の誕生や移動、つながり方、そして活動に必要なエネルギー供給まで、すべてに血管が深く関わっています。
その連携が乱れれば、脳の配線や働きに影響し、行動や認知の特徴として現れる可能性があります。
自閉症やADHDの特性を理解するために、「血管と神経の対話」という視点は新しい手がかりになるのです。
研究はまだ始まったばかりですが、当事者やご家族にとっても「脳の中で何が起きているのか」を考える上で重要な示唆を与えてくれるでしょう。
(出典:Molecular Psychiatry )(画像:たーとるうぃず)
これまで、「血管」にフォーカスをあてた発達に関わる研究はあまり見たことがありません。
困っている方の困難が少しでも減ることにつながるよう、さらなる研究の進展に期待しています。
(チャーリー)