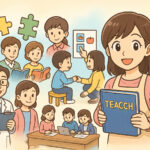この記事が含む Q&A
- 自閉症の人は物語を語る際、舞台設定を省く傾向があり、文脈に対する適応度が低いとされる?
- 舞台説明を意識させる工夫と、感情や理由を言語化する練習が支援に役立つ可能性がある。
- 研究の結果、自閉症の当事者ときょうだいは語り直しで舞台を説明しない割合が高く、対照群は舞台説明が多いという違いが見られた?
- 絵の有無で語り直しの質が下がる点は全グループで一致していた。
- 発達支援の現場では、「どこで・いつ」という舞台設定の意識付けや、感情・思考の因果説明を練習することが効果的かもしれない?
- そのほか、記憶を使って再話する課題の質向上には最初の語り方が重要とされる。
自閉症の人が物語を語るときにどのような特徴が現れるのかは、長年にわたって研究されてきました。
物語を語る力は、友だちとの会話や授業での発表、家庭でのやりとりなど、日常生活のさまざまな場面に関わります。
相手の気持ちを理解したり、自分の経験を整理して伝えたりするうえで欠かせないものだからです。
今回紹介するのは、アメリカのノースウェスタン大学を中心に、ニューヨーク大学ランゴン医療センター、セント・ジョンズ大学、カンザス大学が共同で行った研究です。
この研究は、自閉症の当事者だけでなく、そのきょうだいや親といった家族にも焦点を当てて、物語を語る力がどのように文脈の違いによって変わるのかを詳しく調べたものです。
研究者たちは、物語の語り方を「はじめの語り」と「語り直し」という二つの課題を通じて分析しました。
はじめの語りでは、参加者は「カエルが逃げてしまった少年と犬の物語」の絵本を見ながら、ページごとに話を組み立てていきます。
語り直しでは、10分ほど別の課題を挟んだあと、絵を見ないで思い出しながら物語を語るように求められました。
つまり、最初は絵の助けがある状態、次は記憶だけに頼る状態で話すという二つの状況を比べたのです。
さらに、はじめの語りのときには参加者の視線の動きを記録し、どこを見ているのかも分析しました。

この研究に参加したのは、自閉症の人54人、そのきょうだい41人、親156人、そして対照群として自閉症の家族歴がない子ども49人と親59人でした。
すべての参加者は10歳以上で、知能指数は80以上、英語を主な言語とし、自閉症の診断はADOS-2やADI-Rといった国際的に用いられる評価で確認されました。
結果として明らかになったのは、どのグループでも絵がない語り直しのほうが物語の質が下がるということでした。
とくに、自閉症の当事者ときょうだいは、物語の舞台設定を省く傾向が強く、語り直しでは自閉症の参加者の約30%、きょうだいの約22%が舞台の説明をしませんでした。
対照群ではほとんどが舞台を説明していたため、大きな違いが見えました。
舞台の説明がないと、聞き手は物語の背景がつかめず、理解が難しくなります。
物語の内容を詳しく見ると、自閉症の人やきょうだいは、登場人物の気持ちや考え、行動の因果関係について語ることが少ない傾向がありました。
対照群の子どもたちは、最初の語りでは感情について多く語り、語り直しでは人物の考えや意図について語る割合が増えました。
つまり、文脈に応じて柔軟に語り方を変えていたのです。
しかし自閉症の人やきょうだいは、文脈の変化によって語り方を大きく変えることはなく、どちらの課題でも似たスタイルのままでした。

研究者たちは、この特徴を「文脈感受性の低さ」と表現しています。
文脈感受性とは、状況や相手に応じて言葉や行動を切り替える力を指します。
興味深いのは、きょうだいのグループに独自の特徴が見られたことです。
きょうだいは、自閉症の当事者ほどではないにせよ、物語の舞台を省きやすい傾向がありましたが、一方で感情や思考の原因を説明する割合が高く、当事者とは違った強みを持っていました。
これは「広汎性自閉症表現型(ブロード・オーティズム・フェノタイプ)」と呼ばれる現象の一部と考えられます。
これは、自閉症の診断には至らないけれども、近親者に見られる特徴的な言語や認知の傾向のことです。

親のグループについては、全体的に対照群の親と大きな差はなく、ごく細かな違いにとどまりました。
たとえば、通常発達の子どもの親は行動の理由を多く説明する傾向があるのに対し、自閉症の子どもの親は気持ちや考えの理由を説明することがやや多いという違いが観察されました。
つまり、親の世代では物語の大きな構造は変わらず、説明の仕方に小さな差が見られる程度だったのです。
さらに重要なのは、「はじめの語り」での質が「語り直し」の質を強く予測していたことです。
最初に物語の要素をしっかり含め、感情や考え、因果関係を語れた人ほど、その後の語り直しでも高い質を保てました。
これは、自閉症の当事者にも当てはまっており、最初の段階で物語をどう語るかが、その後の記憶からの再生に大きな影響を与えることを示しています。
一方で、研究者たちが期待していた「視線の動きと語り直しの質の関係」は見られませんでした。
最初の語りのときにどこを見ていたかは、後の語り直しの質にはつながらなかったのです。
これは、記憶を使って再び物語を語るという課題が、視線のパターンだけでは説明できない複雑な働きを含んでいるためだと考えられます。
今回の研究からは、自閉症の人とそのきょうだいに共通する特徴が浮かび上がりました。
文脈による影響をあまり受けず、舞台を省きやすいという点です。
ただし、きょうだいには感情や思考の因果説明という強みがあり、親世代では対照群とほとんど変わらない語りをしていました。
これは、発達段階や年齢によって物語スキルの現れ方が変化することを示しています。

この成果は、支援の現場でも役立ちます。
たとえば、学校や家庭での会話や作文の練習では、「どこで」「いつ」という舞台設定を意識させる工夫をすることで、物語が理解しやすくなるかもしれません。
また、感情や思考の理由を言葉にする練習を取り入れることで、自分や他者の気持ちをより明確にできる支援につながる可能性があります。
研究者たちは、今後はより自然な会話の中での語りや、発達の流れを追う長期的な研究が必要だとしています。
今回の研究は限られた条件での実験でしたが、それでも自閉症やその家族の語りの特徴を理解するうえで重要な一歩となりました。
自閉症の人が物語をどのように組み立て、どのように他者に伝えるのかを理解することは、日常生活でのつながりや支援を考えるうえで大切です。
(出典:Frontiers in Psychiatry DOI: 10.3389/fpsyt.2025.1588429)(画像:たーとるうぃず)
「学校や家庭での会話や作文の練習では、「どこで」「いつ」という舞台設定を意識させる工夫をすることで、物語が理解しやすくなるかもしれません」
苦手な子は多そうです。これは役立ちそうですね。
(チャーリー)