
この記事が含む Q&A
- ADHDの特徴は何がリズムとして現れると指摘されている?
- 情報処理の時間的なリズムに現れるとされる。
- 研究の成果で、薬の服用有無を区別できた精度はどの程度だったか?
- 約91.3%の精度で区別が可能だった。
- この研究の限界として挙げられている点は?
- 対象が若い大人のみ、課題が単語認識に限定、薬服用データのサンプル偏りなどがある。
ADHD(注意欠如・多動症)は、子どもの頃の学習や生活だけでなく、大人になってからの仕事や人間関係にも影響を与えることが知られています。
集中が続きにくい、気が散りやすい、段取りが難しいなど、本人にとっても周囲にとっても負担が大きくなることがあります。
その一方で、ADHDには創造性や発想の柔軟さといった強みがあることも指摘されています。
この多面的な特性を理解するために、世界中の研究者が脳や行動の仕組みを調べ続けています。
今回紹介するのは、カナダのモントリオール大学を中心とした研究チームが行った最新の研究です。
この研究では、ADHDの大人とそうでない大人とで「ものの見え方のリズム」に違いがあるかどうかを探りました。
人が何かを見て理解するとき、脳は一定のリズムで情報を処理していると考えられています。
そのリズムは目に見えるわけではありませんが、刺激の与え方を工夫すれば外から推測することができます。
研究チームは、そうした「視覚処理の時間的な揺らぎ」を0.2秒という短い時間の中で計測し、ADHDの特性を明らかにしようとしました。

この研究の着想の背景には、脳の活動が「波」として働いているという考えがあります。
脳の電気活動はアルファ波やシータ波といった周波数ごとの振動を示し、それが注意や集中と深く関わっていることが知られています。
ADHDの人は、この脳波のリズムに特徴的な違いがあると報告されてきました。
しかし従来の研究は脳波を直接測定するもので、日常的なタスクに結びつけるのは難しいところがありました。
今回の研究は、課題中の「見え方の揺らぎ」からそのリズムを逆算するという、ユニークなアプローチをとっています。
参加者は、ADHDと診断された若者23人と、診断されていない若者26人、合計49人でした。
全員が正常な視力を持ち、課題はパソコンの画面に5文字の単語を0.2秒間だけ提示するものでした。
ポイントは、その0.2秒の間に文字の「見えやすさ(信号対雑音比)」をフレームごとに変化させることです。
見えにくくなったり、はっきり見えたりを細かく繰り返す映像を見せることで、参加者の脳がどのタイミングで効率よく情報を取り込んでいるかが推測できる仕組みになっています。
課題の難易度は、正答率がおよそ50%に保たれるように自動調整されました。
これは、単純に「ADHDの人は点数が低い」といった成績差を測るのではなく、答えに至るまでの脳のリズムに注目するためです。
研究チームは、正解や不正解のデータと提示された見えやすさの変動を対応づけ、「分類画像」と呼ばれる時間×周波数の地図を作成しました。
この地図には、どのタイミング・どの周波数帯で処理効率が高まるかが描き出されます。

結果として、両グループの分類画像は一見すると似ていましたが、差を詳しく解析すると低周波数帯に明確な違いが現れました。
とくに10ヘルツ付近の周波数で、ADHDの人は処理効率の振動の仕方が異なっていました。
この特徴を機械学習にかけたところ、ADHDかどうかを91.8%の精度で見分けることができました。
つまり、わずか0.2秒の視覚処理のリズムに、ADHDの特性を反映した“型”が存在する可能性が示されたのです。
さらに研究チームは、ADHDの人を「薬を日常的に服用している人」と「服用していない人」に分けて分析しました。
ADHDの治療薬は脳内の神経伝達物質に作用し、注意や集中を改善するとされていますが、その影響が情報処理のリズムにどう表れるかははっきりしていませんでした。
結果として、この区別も91.3%の精度で可能でした。
とくに20〜30ヘルツの周波数帯で差が出ており、薬を飲んでいる人と飲んでいない人では視覚処理の波形が異なっていたのです。
この結果は、薬の長期使用が脳の働き方にある種の“型”を与えている可能性を示しています。
ただし、非服用群の人数が少なく、学習データが十分でない点は限界として挙げられています。

この研究からわかる大事なポイントは三つあります。
第一に、ADHDの特性は「点数」や「能力の高さ」ではなく、「情報処理の時間的なリズム」に現れる可能性があることです。
第二に、そのリズムは個人ごとの差を超えて共通性があり、機械学習によって安定して抽出できることが示されたことです。
第三に、薬の服用という生活上の要因もこのリズムに影響し、それを外部から測定できる可能性があるという点です。
もちろん、この研究には限界があります。
対象は若い大人に限られており、子どもや高齢者でも同じような結果が得られるかは不明です。
また、課題は単語認識に限定されており、顔や物体、複雑な場面を扱ったときに同じ違いが見られるかどうかは検証されていません。
さらに、薬の使用有無に関してはサンプルの偏りがあり、今後は大規模な研究が必要とされます。
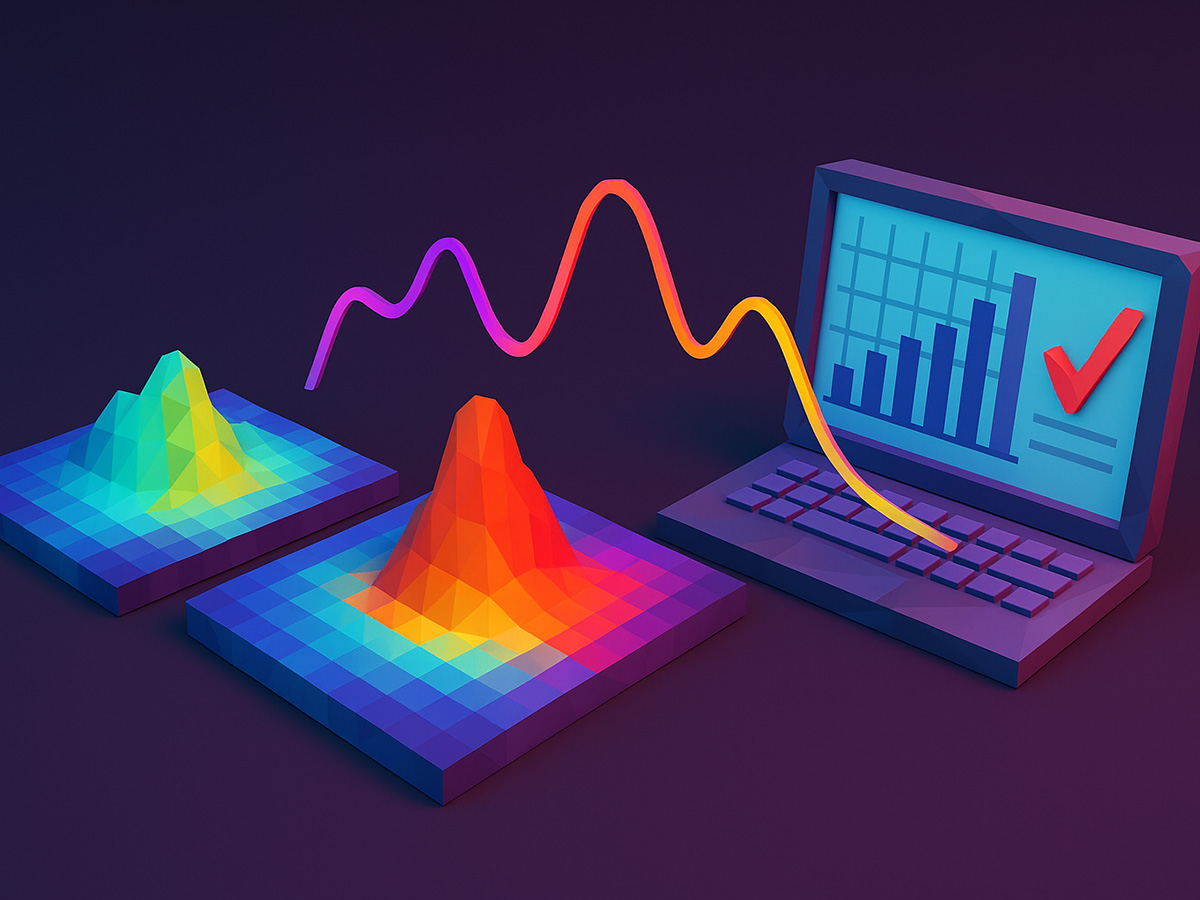
それでも、今回の成果はADHD研究にとって重要です。
ADHDは「一人ひとり違う」と言われることが多く、診断や支援の難しさの一因となっています。
今回の研究が示すように、ほんの0.2秒の中に共通する“時間的な型”が存在するなら、将来的には診断や支援の新しい補助指標になり得るかもしれません。
たとえば、視覚課題を通してADHDらしさを数値化できれば、診断の一助になる可能性があります。
また、薬の効果を客観的にモニタリングする方法としても期待が持てます。
モントリオール大学の研究チームは、今後さらに大規模な調査を行い、他の課題や年齢層でも同様の特徴が出るかを検証する必要があると述べています。
この研究はまだ出発点にすぎませんが、ADHDの理解に新しい視点を与えるものです。
注意や集中の難しさを単なる「弱さ」と捉えるのではなく、脳が情報を処理するリズムの違いとして理解することが、支援や社会の理解を進める手がかりになるかもしれません。
(出典:PLOS One DOI: 10.1371/journal.pone.0310605)(画像:たーとるうぃず)
「脳波のリズムに特徴的な違いがある」
なんですね。
困難をかかえる人の困難の軽減につながるように活用されていくことを願います。
(チャーリー)





























