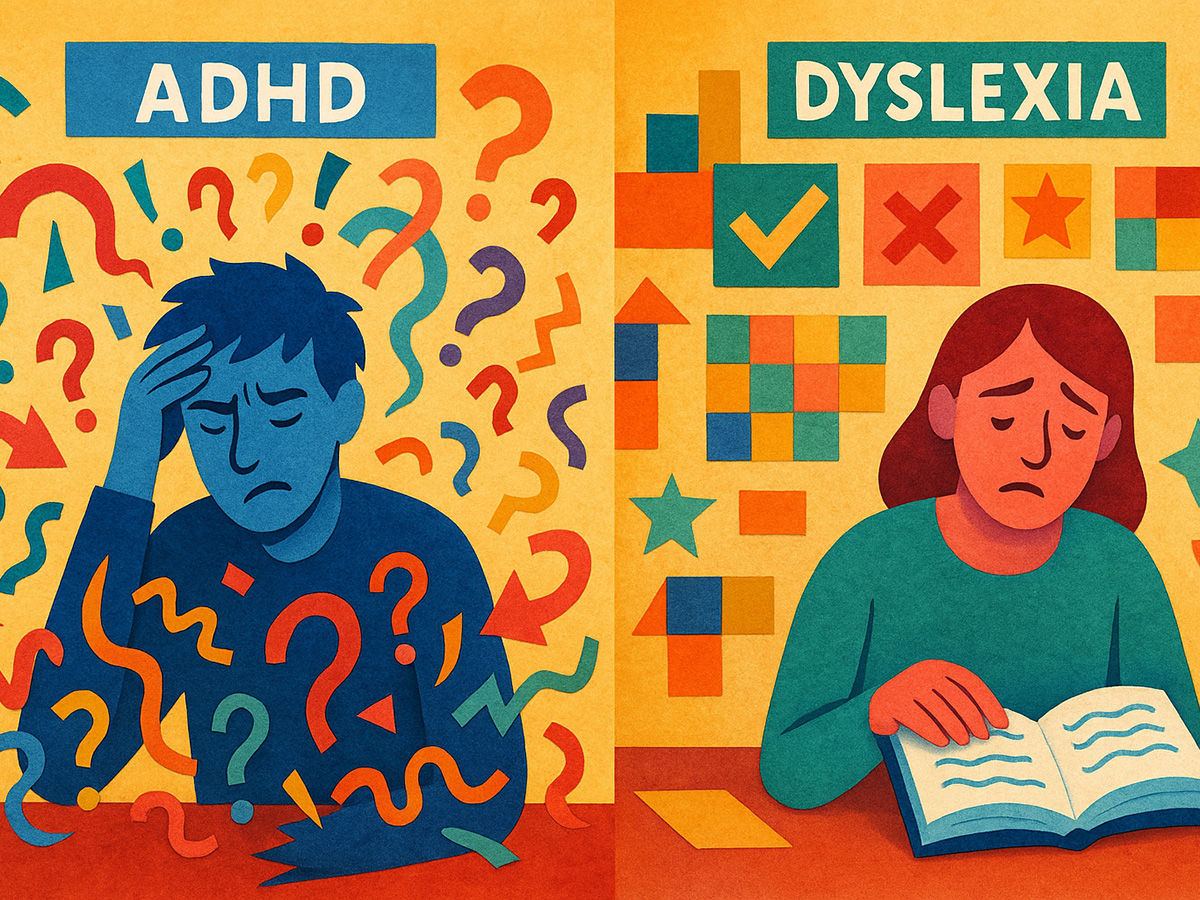
この記事が含む Q&A
- ADHDをもつ人は、「自分で重要な情報を見つけるのが難しい」ことが研究で示されていますか?
- はい、指示なしの課題で成績が低くなる傾向が確認されています。
- ディスレクシアの人の学習における特徴は何ですか?
- 「情報の忘れやすさ」が高く、学んだ内容を維持する力が弱い傾向があります。
- それぞれの特性に基づいた支援方法にはどんなものがありますか?
- ADHDには「注目すべきポイントを明示」、ディスレクシアには「繰り返し確認」を促す工夫が有効と考えられます。
私たちは日々の暮らしの中で、知らず知らずのうちに学びを繰り返しています。
新しい料理の作り方を覚えたり、道順を身につけたりするのも学習のひとつです。
しかし、ADHD(注意欠如・多動症)やディスレクシア(読み書きの困難)といった発達性神経疾患を持つ人々には、学ぶ過程で特徴的な困難があることが知られています。
npj science of learningに掲載された今回の研究では、ADHDとディスレクシアのある人たちが、複雑な学習環境でどう行動し、どのような違いを見せるかを調べました。
実験では、色・形・模様の3つの特徴をもつ図形から、報酬につながる特徴を見つける課題に取り組んでもらいました。
報酬が何によって決まるかは明示されておらず、参加者は自分で探る必要がありました。
課題には2つのバージョンがあります。
1つは「指示あり」の課題で、どの特徴(色や形など)に注目すべきかが最初に伝えられます。
もう1つは「指示なし」で、自分で手がかりを見つけなければなりません。

結果として、ADHDとディスレクシアのある人たちは、どちらの課題でも障害のない人たちよりも成績が低い傾向がありました。
ただし、全員が偶然ではなく、ある程度規則を見抜いて学習できていました。
つまり、「学べない」のではなく「学び方に特徴がある」ということです。
ADHDのある人は、「指示なし」の課題で障害のない人たちより明らかに成績が低く、自分で重要な情報を見つけるのが難しいことが示されました。
一方で「指示あり」の課題では差が小さく、情報が与えられると学習は比較的うまく進みました。
ディスレクシアのある人は、どちらの課題でも成績が低く、とくに「覚えたことを維持する力」が弱い傾向が見られました。
学んだばかりの情報がすぐに忘れられてしまうため、複雑な規則を定着させるのが難しいのです。
このような違いは、計算モデルを用いた分析によってさらに明らかになりました。
研究チームは「強化学習(ごほうびによって行動が変わる仕組み)」と「ベイズ推論(過去の情報と新しい情報を統合して最適化する方法)」を組み合わせたモデルで、各グループの学習の仕組みを数値的に捉えました。
ADHDのある人は、より正確な学習戦略であるベイズ推論をあまり使わず、直前のごほうびだけに反応する「強化学習型」の学び方に偏っていました。これは「考えて行動する」よりも「反射的に動く」傾向があることを示しています。
ディスレクシアのある人は、学習した内容が急速に忘れられていく「高い減衰率」が特徴でした。
つまり、過去の経験が現在の判断にほとんど影響しないため、規則性を長く保つのが難しいのです。
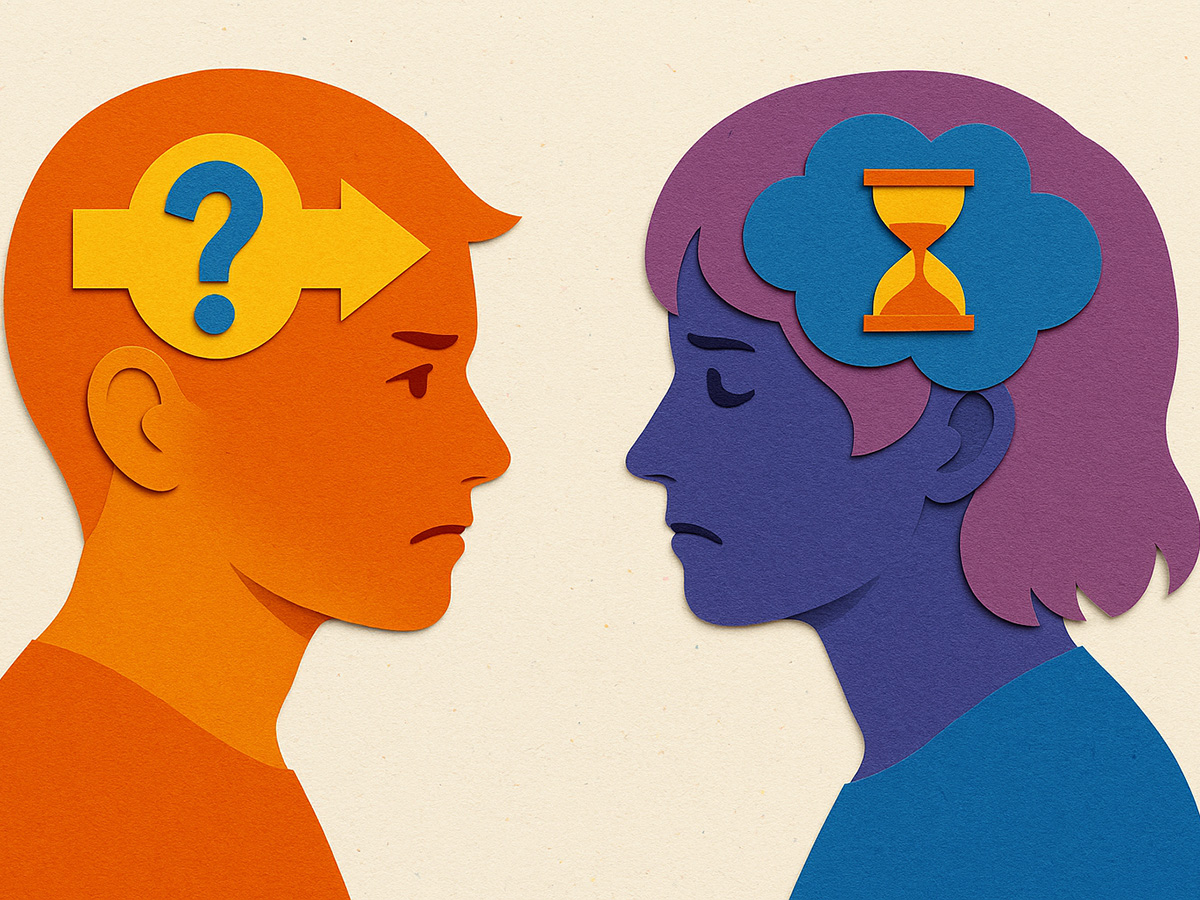
こうした違いは、ただの「成績の差」では見えにくいものです。
表面的には同じような結果でも、学習の中で起きているプロセスはまったく異なっている可能性があります。
たとえばADHDの人は、「どの特徴に注目するかを決める力」に課題があるかもしれません。
ディスレクシアの人は、「学んだ内容を長く保つ力」が弱いのかもしれません。
これらはどちらも「集中力がない」「やる気がない」といった見方では説明できません。
研究では、ADHDグループでは「ベイズ推論の重み」が著しく低く、ディスレクシアグループでは「情報の忘れやすさ」が高いことがわかりました。
これらは、それぞれの困難さの“計算上のしるし”として使える可能性があります。
参加者の知能や年齢、視覚・聴覚などはすべて正常で、ADHDやディスレクシア以外の神経疾患はありませんでした。
検査の結果、ADHDの人たちは注意力テストでのみ有意差がありました。
ディスレクシアの人たちは読み書きの正確さやスピード、音の操作、短期記憶で明確な困難が見られました。

これまでの研究は、「どの特徴に注目すればよいか」を最初から教えてくれるような「単純な課題」が中心でした。
しかし、現実の生活ではそんな親切な指示はまずありません。
この研究が扱ったような「自分で判断する」「複数の手がかりから選ぶ」状況こそ、実社会に近いものです。
たとえば、新しい職場では「誰に相談すればいいか」「どの仕事が評価されるか」など、自分で学ばなければならない情報が山ほどあります。
そうした場面で、ADHDやディスレクシアの人たちは、見えにくい困難に直面しているかもしれません。
ただし、こうした困難には「別の力がある」側面もあります。
ディスレクシアの人は、すぐに忘れる分、新しい状況への適応力が高いという研究もあります。
ADHDの人は、直感的な判断を求められる場面で素早く対応できるかもしれません。

研究チームは、こうした違いを活かした個別の支援が必要だと述べています。
たとえば、ADHDの人には「どこに注目すればよいか」を明示するような工夫、ディスレクシアの人には「繰り返し確認する」仕組みなどが効果的かもしれません。
この研究では、「できる・できない」ではなく、「なぜ、どうしてそうなるのか」を解明することが目指されました。
その結果として、ADHDとディスレクシアでは、学びの過程が異なることが明確になったのです。
今後は、こうした計算論的な理解をもとに、それぞれの特性に合った学習支援や環境づくりが期待されます。
同じように見える「つまずき」の背景には、異なる理由がある――それを理解することが、よりよい社会への第一歩になるでしょう。
(出典:Nature science of leraning DOI: 10.1038/s41539-025-00323-4)(画像:たーとるうぃず)
「ADHDの人には「どこに注目すればよいか」を明示するような工夫、ディスレクシアの人には「繰り返し確認する」仕組みなどが効果的かもしれません。」
こうした研究によって、支援がより効果的になっていきます。期待しています。
(チャーリー)





























