
この記事が含む Q&A
- ADHD傾向がある人は、睡眠の問題を抱えやすいですか?
- はい、特に不眠の重症度が高いほど、生活満足度が低下しやすいことがわかっています。
- 不眠が生活の質に与える影響は何ですか?
- 不眠は、集中力や気分の安定に影響し、人生への満足感を低下させる要因となります。
- ADHDの人が睡眠障害を改善する方法はありますか?
- 認知行動療法(CBT-I)や生活リズムの調整が効果的とされています。
注意欠如・多動性障害(ADHD)の特徴をもつ人は、そうでない人と比べて、気分が落ち込みやすかったり、生活に満足しにくいと感じたりすることが多いです。
しかし、その理由については、まだはっきりとはわかっていません。
たとえば、眠れない夜が続いたり、生活リズムが乱れたりすることが、どれほどADHD傾向の人のこころや生活の質に影響しているのかは、十分に解明されていませんでした。
今回の研究は、イギリスのサウサンプトン大学、オランダ神経科学研究所などの複数の大学・研究所からなる国際研究チームが、オランダで行われた大規模な睡眠調査をもとに、ADHD傾向をもつ人の睡眠や生活リズムの乱れが、抑うつや生活の質の低下とどのように関係しているかを調べました。
その結果、ADHD傾向が強い人は、眠りの問題を抱えやすく、とくに「不眠」が強いほど、生活への満足感が低くなる傾向が明らかになりました。

調査には、平均年齢が約52歳の成人1,364人が参加しました。
参加者の4分の3が女性でした。
インターネットで行われた調査では、ADHD傾向、気分の落ち込み、生活満足度、不眠や睡眠の質、体内時計のタイプ(朝型・夜型)、平日と週末の睡眠リズムの違いなど、さまざまな項目について質問に答えてもらいました。
分析の結果、ADHD傾向が強い人ほど、次のような特徴が見られました。
- 気分の落ち込みが強い
- 生活の満足度が低い
- 不眠の症状が強い
- 睡眠の質が低いと感じる
- 夜型傾向がやや強い
しかし、ADHD傾向が直接的に気分の落ち込みを強めるとは言い切れませんでした。
つまり、眠りや生活リズムの乱れが、その関係をつなげているかどうか調べたところ、明確な証拠はありませんでした。
一方、生活の満足度については、「不眠」の重症度だけがADHD傾向と生活の質の関係を説明できることがわかりました。

研究者たちは、「不眠の重さ」がADHD傾向の人の生活の満足感の低さを、部分的に説明していると考えています。
眠れない夜が続くと、日中に集中しづらくなったり、気持ちが不安定になったり、人間関係や仕事もうまくいきにくくなったりします。
こうしたことが積み重なり、「自分の人生に満足できない」と感じやすくなるのかもしれません。
この研究では、生活の質を測るために、「生活満足度尺度(サティスファクション・ウィズ・ライフ・スケール)」と「カントリルの階段(カントリル・ラダー)」という2つの方法が使われました。
「生活満足度尺度」とは、自分の人生にどれくらい満足しているかを、いくつかの質問でたずねるものです。
たとえば、「自分の人生にとても満足している」や「これまでの人生をもう一度やり直せるなら、ほとんど何も変えたくない」といった問いに対して、「まったくそう思わない」から「とてもそう思う」まで5段階で答えます。この5つの質問の合計点が高いほど、その人が「自分の人生に満足している」と評価されます。
この尺度は、ポジティブな気持ちだけでなく、人生全体についての納得感や満足感を、客観的に数字で表すためによく使われるものです。

「カントリルの階段」は、もう少し直感的な方法です。
これは、「あなたの人生を10段階のはしごに例えると、今どの段にいると思いますか?」というふうに聞くものです。
10が「これ以上ないくらい最高の人生」、0が「最悪の状態」となっていて、今の自分がどこにいるかを自分自身で選びます。
また、「理想の将来」や「最悪のシナリオ」もイメージして、その違いを比べながら、自分の今の立ち位置を考えます。
このスケールは、答える人の主観的な感覚を大切にし、「なんとなく幸せ」「今は苦しいけど将来は良くなる気がする」といった気持ちも反映できるのが特徴です。
どちらも「生活の質」や「幸福感」を評価するために、世界中でよく使われている心理学的な質問票です。
今回の研究では、この2つの方法を組み合わせて、ADHD傾向のある人がどれくらい「人生に満足しているか」「自分の人生をどう感じているか」を丁寧に調べました。
その結果、どちらの尺度でも、「不眠」がADHD傾向と生活の質の関係をつなぐ重要な要素であることが確かめられました。
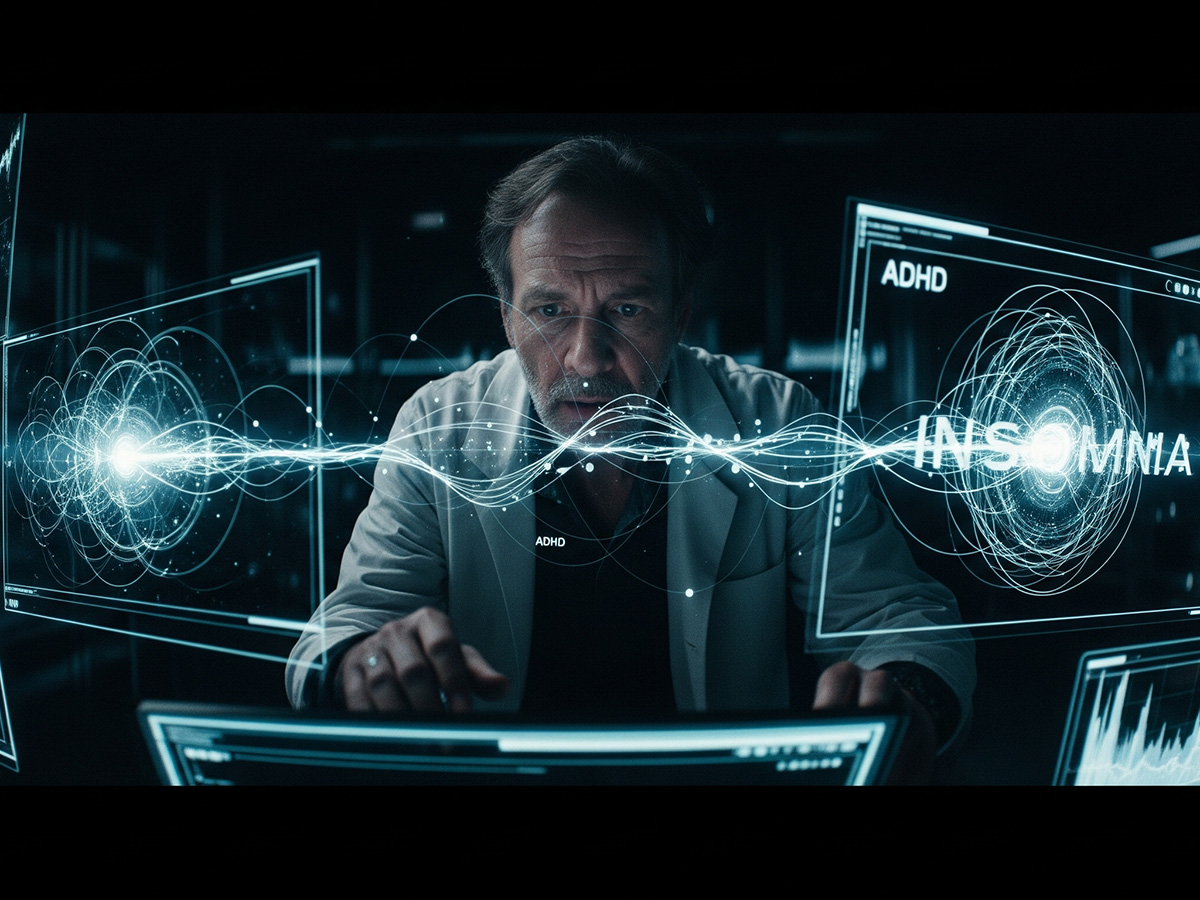
一方で、気分の落ち込みについては、ADHD傾向との間に関係があったものの、眠りや生活リズムの乱れがそのつながりを説明できるほど強い影響を持つとは言えませんでした。
年齢層の違いや、重度の抑うつの人が少なかったことなどが、この結果に影響している可能性もあります。
一般的に、ADHDのある人の3〜4割ほどは、一生のうちに一度は重い抑うつを経験するといわれています。
これは、一般の人よりも明らかに高い割合です。
また、最近の研究では、ADHD傾向の強い人は、遺伝的にも抑うつになりやすいことが示唆されています。
さらに、ADHD傾向のある人は、睡眠の問題を抱えるリスクも高いです。
たとえば、夜遅くまで眠れず、朝起きるのが苦手な「夜型」や「不眠」の症状が多くみられます。
もともと、ADHDのある人は睡眠障害を抱えやすいことが知られており、たとえばスウェーデンで行われた全国規模の調査では、「ADHDのある人は、一般の人と比べて6倍から16倍も睡眠障害と診断されるリスクが高い」と報告されています。
とくに不眠のリスクはとても高く、睡眠薬の処方も多いです。

一方で、「夜型傾向」はADHD傾向とやや関係があるものの、それほど強くはありませんでした。
これは、日々の生活で目覚まし時計などに頼ることが影響している可能性があります。
また、平日と週末で睡眠パターンが変わる「社会的時差」も、ADHD傾向や生活の満足度、気分の落ち込みとの関係は見つかりませんでした。
この研究の意義は、中高年層のADHD傾向のある人について、「不眠の重さ」が生活の満足感を下げる重要な要因であることを明確にしたことです。
これまでの研究は、子どもや若い人が中心でしたが、中高年に関する知見は少なかったため、今回の発見はとても大きな意味を持っています。
さらに、不眠は「改善が可能な問題」であるという点も大切です。
薬を使わずに不眠を改善する方法として「認知行動療法(CBT-I)」があり、これは睡眠の質を高める効果が証明されています。
最近では、認知行動療法と生活リズムの調整を組み合わせる方法も研究されており、ADHDのある人にも効果が期待されています。
もちろん、この研究にはいくつかの限界もあります。
主に中高年の白人女性が対象だったため、すべての人にそのまま当てはまるとは限りません。
また、調査はアンケート形式で、実際の睡眠を計測したわけではありません。
さらに、一度きりの調査だったため、因果関係まではわかりません。
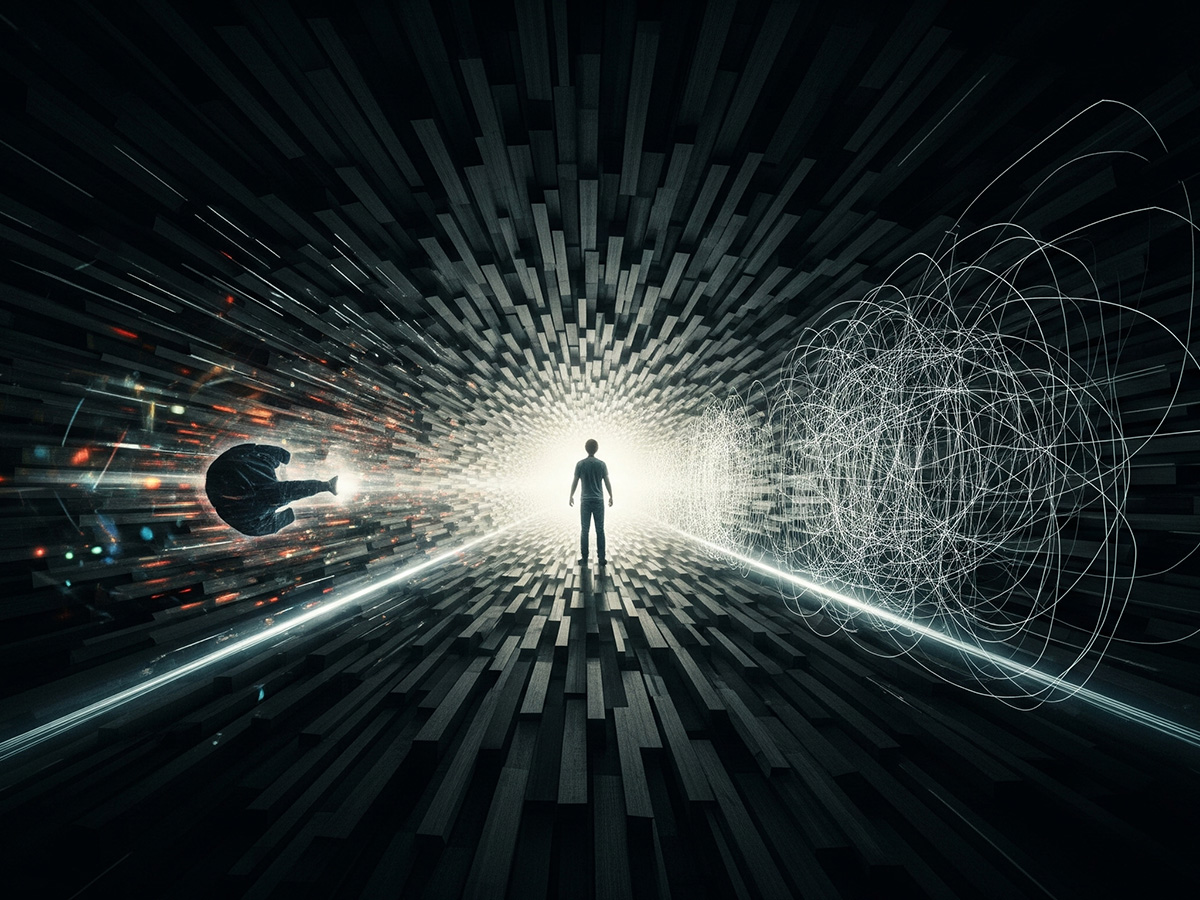
それでも、
「ADHD傾向のある人の支援には、『不眠』への対応がとても重要だ」
というメッセージは、今後の臨床や研究にとって大切なヒントです。
もし気分がすぐれなかったり、生活に満足できないと感じたりするとき、その背景に「眠れない夜」があるかもしれません。
眠りの質を少しでも高めることで、毎日が少しずつ前向きに変わっていく可能性があります。
これからは、より多様な人々を対象に、長期間にわたる調査や客観的な睡眠の計測なども取り入れながら、ADHD傾向・睡眠・こころの健康のつながりを明らかにしていくことが求められます。
その成果は、ADHD傾向のある人が、自分らしく生きやすくなるための大切なヒントになるでしょう。
(出典:BMJ Mental Health DOI: 10.1136/bmjment-2025-301625)(画像:たーとるうぃず)
「不眠」など、睡眠に関わる問題は、自閉症の人でも多くあります。
生活全般に影響を与えるのは、誰しも想像できるはずです。
(チャーリー)





























