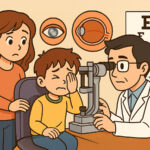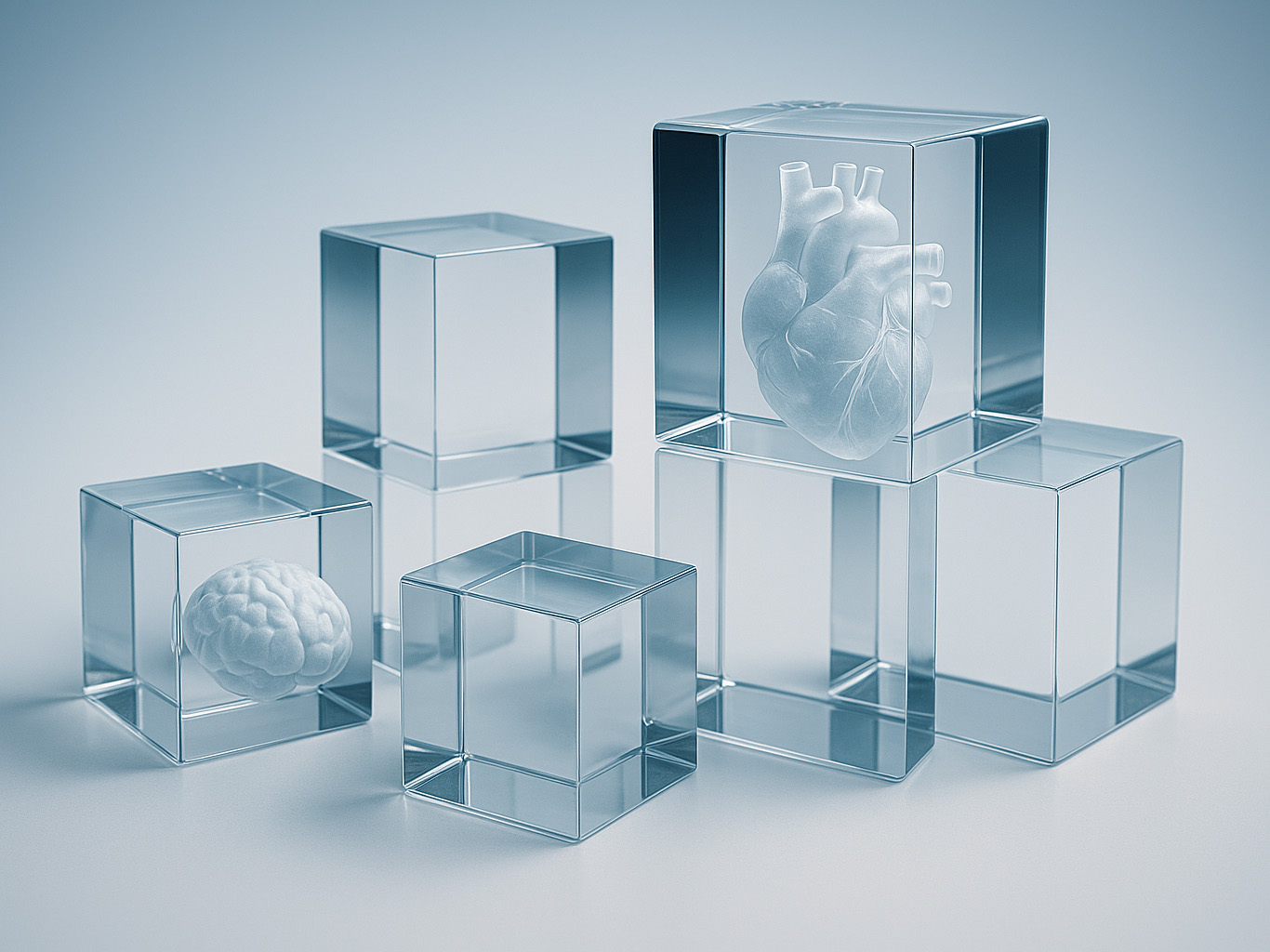
この記事が含む Q&A
- ADHDの遺伝的傾向は、心臓や血管の疾患リスクと因果関係があるのでしょうか?
- 研究により、ADHDの遺伝的傾向は冠動脈疾患や心不全、脳卒中のリスクを高めることが示されました。
- 自閉スペクトラム症(ASD)と血管疾患の関係について、何か明らかになっていることはありますか?
- ASDの遺伝的傾向は心房細動や心不全のリスク上昇と因果関係が示唆されています。
- これらの研究はどの人種や民族に適用できるのでしょうか?
- ほとんどのデータはヨーロッパ系の研究に基づいており、他の人種や民族への適用には追加の研究が必要です。
注意欠如・多動症(ADHD)や自閉スペクトラム症(ASD)と心臓や血管の病気とのあいだには、目には見えにくいけれど深い関係があるのではないか――。
そんな問いに対し、最先端の遺伝学的手法で答えようとする研究が進められています。
今回の研究は、ポーランドにある2つの医科大学、ビアウィストク医科大学とウッチ医科大学らによる研究チームによって行われました。
彼らは、発達障害と心血管疾患のあいだにある因果関係を、メンデルランダム化という手法を用いて包括的に検証しました。
ADHDやASDは、脳の発達に関わる神経発達症の代表的なものです。
全世界では、ADHDが約1億4,000万人、ASDが約6,000万人の人に影響を与えているとされています。
子どもの頃から診断されることが多いこれらの症状は、行動や感情、社会との関わりにおいて一生にわたって影響を及ぼすことがあります。
そして最近では、それだけでなく、身体の健康とくに心臓や血管に関する病気との関連が注目されるようになっています。
たとえばADHDのある人では、生活習慣病や睡眠不足、ストレス、向精神薬の使用などが重なり、心臓病のリスクが高まるのではないかという指摘があります。
ASDのある人についても、同様の健康リスクが考えられています。
けれども、そうした関係が「本当に因果関係にあるのか」、つまりADHDやASDが直接的に心疾患のリスクを高めるのか、それとも他の要因によって一緒に現れているだけなのかは、これまでの観察研究でははっきりしていませんでした。
そこでこの研究では、因果関係を調べるための新しい方法として、メンデルランダム化(Mendelian Randomization, MR)という遺伝学的な分析法を用いています。
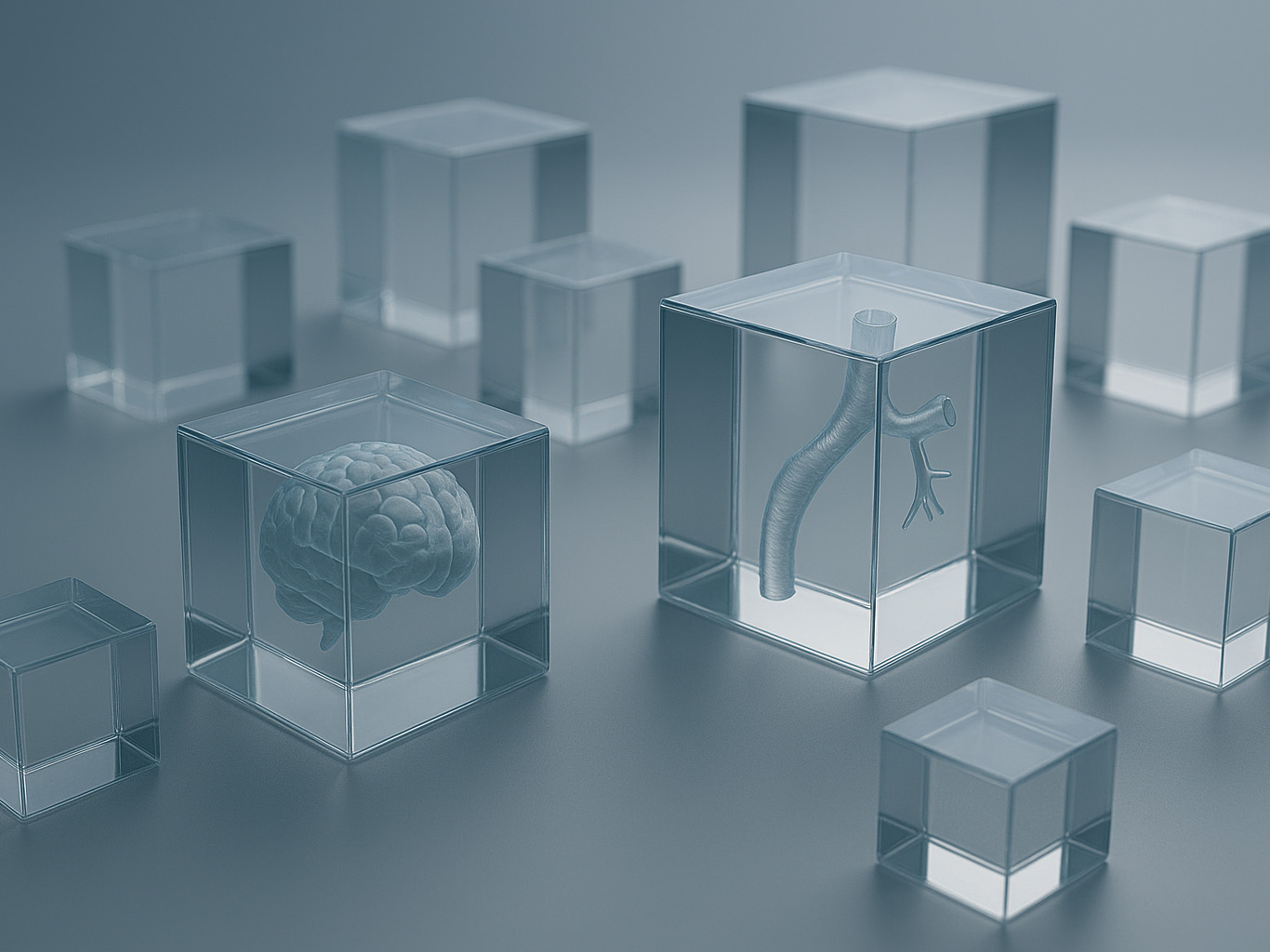
「メンデルランダム化(MR)」という手法は、少し特殊な統計的アプローチです。
この方法では、親から子に受け継がれる「遺伝的なばらつき」を自然な「実験」として利用します。
たとえば、ある人がADHDになりやすい遺伝的傾向をもっているとき、その傾向があるかないかは生まれつきの「くじ引き」のようにランダムに決まります。
そして、何万人もの人たちの遺伝情報をもとに、「ADHDの遺伝的傾向がある人は、心臓病になりやすいかどうか?」を調べることで、因果関係があるのかを統計的に推定するのです。
これは、人間を実際にランダムにグループ分けして長期間追いかける「臨床試験」に近い考え方です。
ただし、MRでは実際の治療や介入はせず、遺伝的な違いを利用して因果関係を明らかにしようとします。
たとえば、
* 「ADHDになりやすい遺伝子をもつ人は、心不全になりやすい」
という関係が見つかれば、それは「ADHDの傾向が心不全のリスクを高める可能性がある」と考えることができるのです。
このように、メンデルランダム化は、観察研究では見分けにくい「本当の原因と結果」の関係を、より信頼できる形で明らかにするための強力な道具となっています。
今回の研究では、過去に発表されたMR研究の中から、ADHDとASDと心血管疾患との関係を調べた14本の研究を系統的にまとめました。
対象とされた心血管疾患には、冠動脈疾患(心筋梗塞など)、心不全、脳卒中(複数のタイプを含む)、心房細動、高血圧、先天性心疾患などが含まれています。
分析対象となった遺伝データの多くは、ヨーロッパ系の大規模なゲノム研究から得られており、代表的なものにPGC(精神疾患ゲノムコンソーシアム)やUKバイオバンク、MEGASTROKEなどがあります。
注目すべき結果として、ADHDに関連する遺伝的傾向をもつ人では、冠動脈疾患、心不全、脳卒中のリスクが明確に高くなっていることが示されました。
またASDについても、心房細動と心不全のリスク上昇との因果関係が示唆されました。
これらはいずれも統計的に有意な関連であり、観察研究で報告されていた関係を裏づける結果といえます。
一方で、高血圧に関しては、ADHDともASDとも明確な因果関係は見られませんでした。
心筋梗塞についても、はっきりした関連はありませんでした。
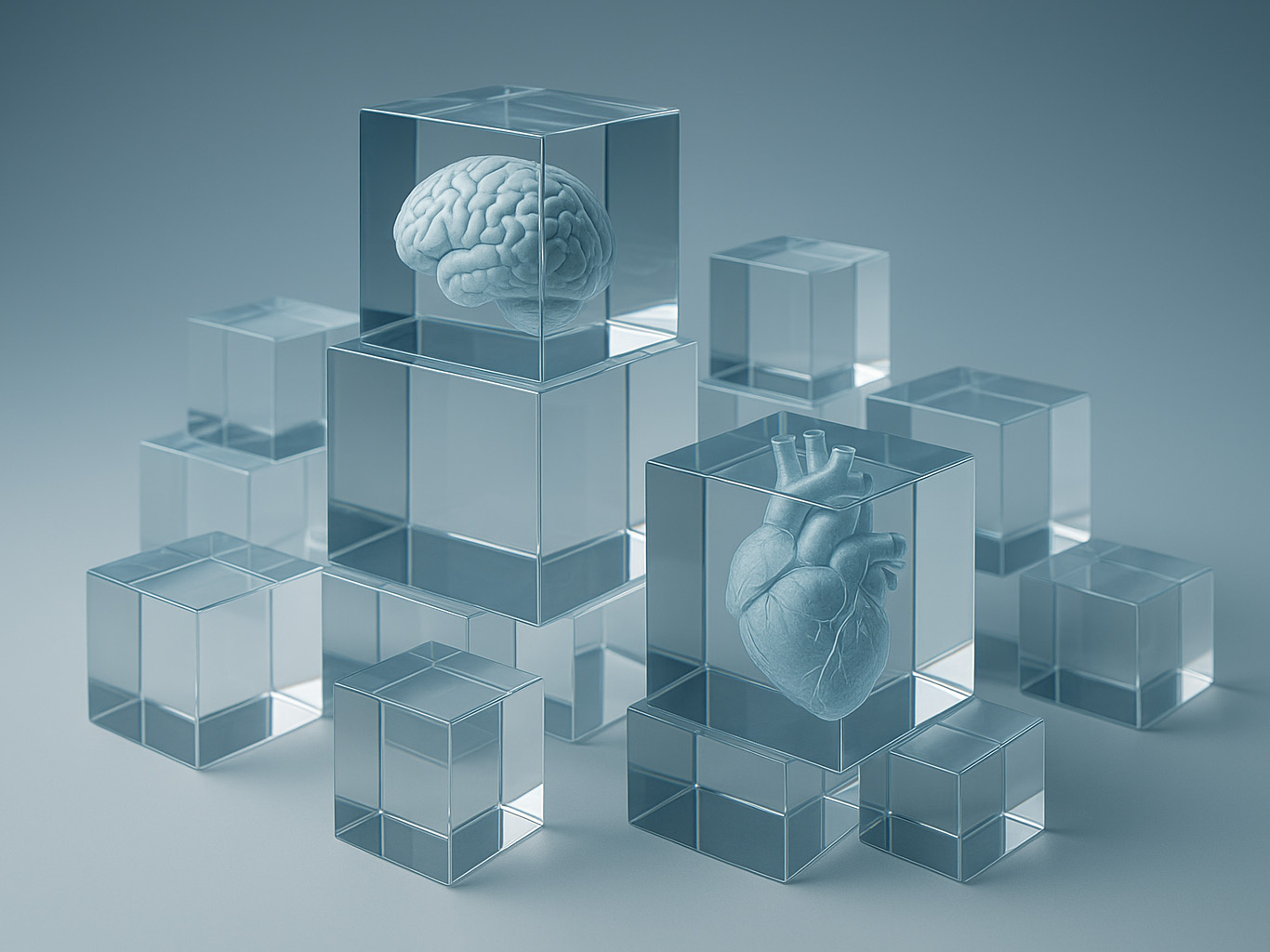
さらに、心房細動がADHDのリスクを高めるという逆方向の因果関係も、一部の研究で示されました。
これは、心血管疾患が精神の発達に影響を与える可能性を示唆しており、注目すべき点です。
なぜこのような関係があるのでしょうか。
そのメカニズムはまだ完全にはわかっていませんが、いくつかの仮説が考えられています。
たとえば、ADHDやASDでは、脳のストレス反応や炎症反応が強くなっており、それが心臓や血管の働きにも影響を与えている可能性があります。
具体的には、HPA軸と呼ばれるストレス応答系の過活動、免疫系の乱れ、血管内皮の機能障害、炎症性サイトカインの増加などが関わっているとされています。
また、生活習慣の面でも、ADHDの人では運動不足や喫煙、不規則な食事、肥満などが心疾患のリスクを高めていることが知られています。
最近のMR研究では、ADHDに関連する遺伝的傾向と肥満、喫煙とのあいだにも因果関係があることが示されています。
ASDにおいても、身体活動量が少ないことが遺伝的傾向として関連づけられています。
つまり、遺伝的な影響と生活習慣の影響が重なりあって、心臓や血管の病気が起こりやすくなっていると考えられます。
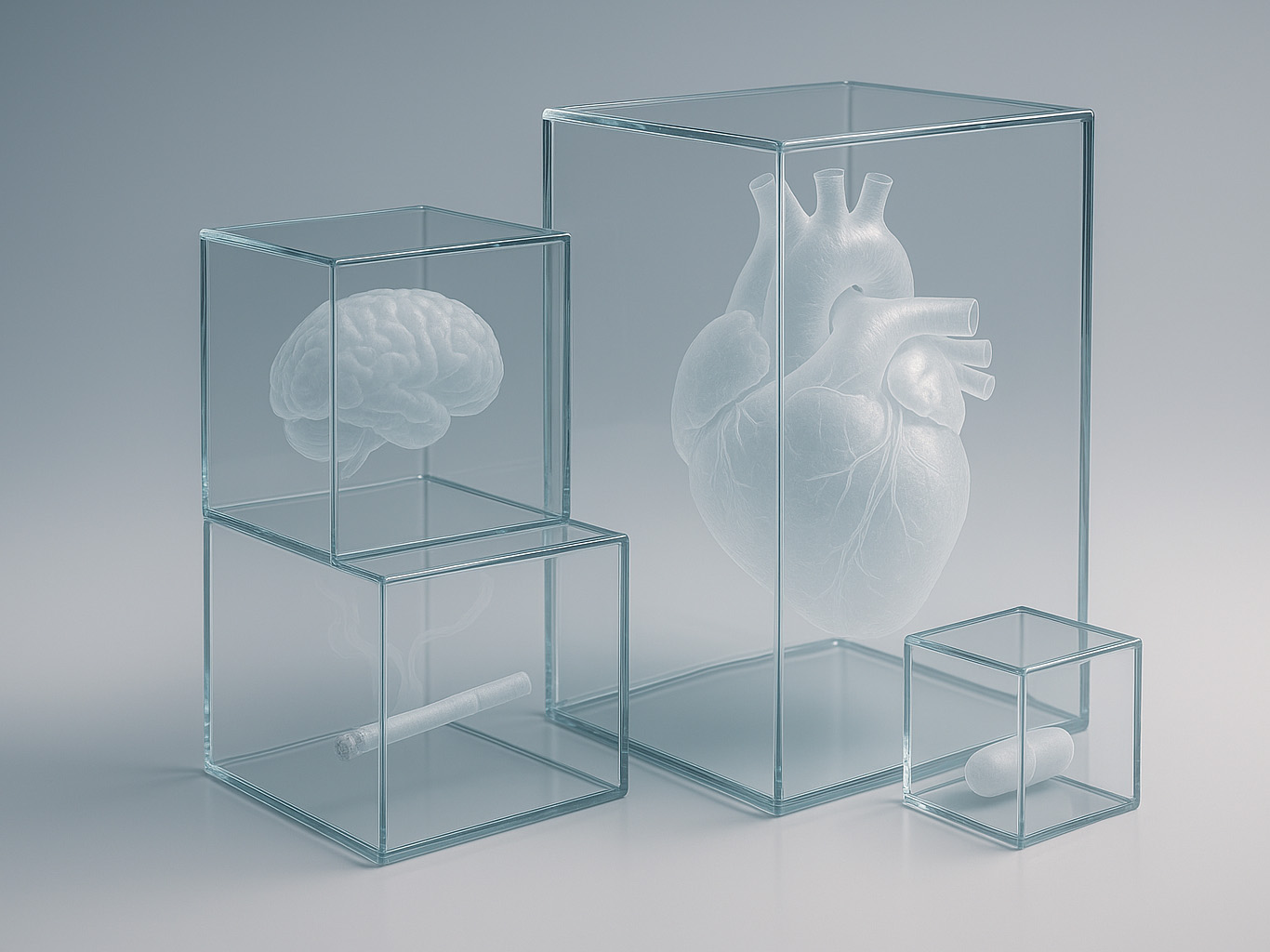
ただし、注意すべき点もあります。
今回の研究で用いられたデータの多くは、ヨーロッパ系の人々を対象にしており、他の人種・民族にこの結果がどこまで当てはまるのかは、今後の研究が必要です。
また、心疾患と神経発達症の双方向の関係、つまり「心疾患のリスクがADHDやASDの発症に影響を与える」という方向については、まだ十分なデータがそろっていません。
それでも、今回の系統的レビューとメタアナリシスの結果は、ADHDやASDのある人において、心血管疾患のリスクを早期に評価し、必要に応じて予防や治療を行うことの重要性を示唆しています。
心の問題と体の問題は、決して別々にあるわけではありません。
発達の特性が、心臓の健康にも深く関わっているかもしれないという視点は、今後の医療において欠かせないものになっていくでしょう。
医療者だけでなく、本人や家族、そして社会全体がこの関係性を理解し、支援につなげていくことが求められています。
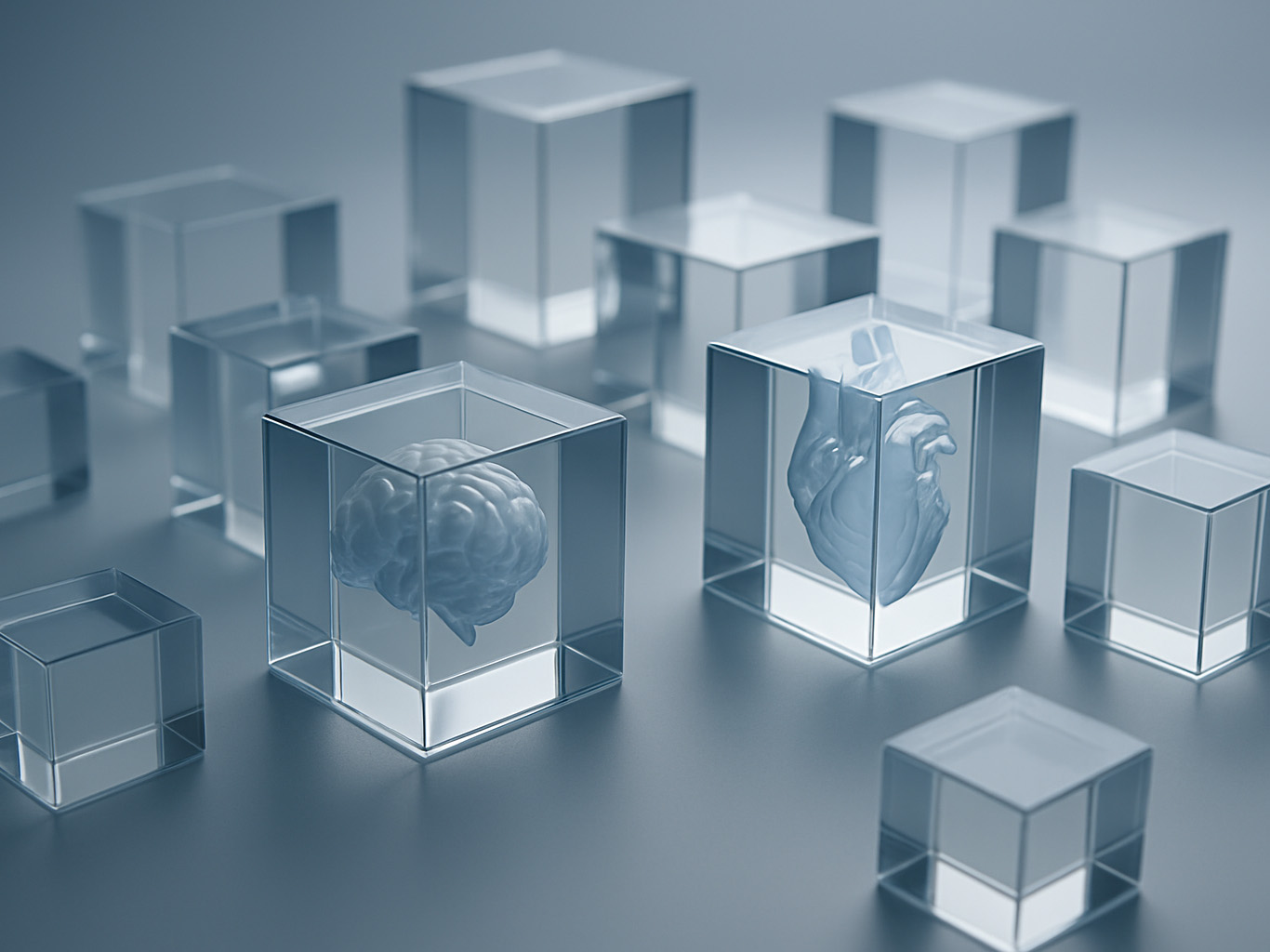
これからの研究では、ADHDやASDの重症度や症状のばらつき、年齢や性別、治療薬の影響などにも目を向けながら、より詳細なメカニズム解明が進められることが期待されます。
また、心疾患側から見たときに、どのような特徴のある人が神経発達症を発症しやすいのかといった研究も進められる必要があります。
心と体のあいだにある遺伝の橋を探るこのような研究は、発達障害と身体疾患の「垣根」を越えて、人の健康をより深く理解するための手がかりを与えてくれるものです。
そしてそれは、本人の生活の質を高めるだけでなく、社会全体の健康を守る上でも大きな意味を持っています。
(出典:cells)DOI: 10.3390/cells14151180(画像:たーとるうぃず)
発達障害、ストレス、心臓疾患、これらの関連については、これまでにも指摘されてきました。
正しく、広く理解され、さらなる困難が防げるように願います。
(チャーリー)