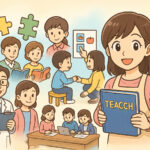この記事が含む Q&A
- 自閉症の社会性は「欠けている」のではなく「独自のスタイル」という理解で合っていますか?
- はい、社会性は文脈やスタイルの違いとして捉えるべきだと説明されています。
- 視線の使い方や表情の読み取りは個人差が大きいとのことですが、日常で相手と適切にコミュニケーションするヒントはありますか?
- 相手の見る目的や注目のタイミングを尊重し、対話のリズムを合わせることが大切です。
- 介入やトレーニングの効果は持続が環境や個人差で異なるとありますが、実践的なサポートのポイントは?
- 個々の感じ方と環境に合わせた継続的な支援と、当事者の経験を研究や実践に取り入れることが重要です。
自閉症という言葉を聞くと、「人との関わりが苦手」という印象を持つ人が多いかもしれません。
しかし、今回の研究が示したのは、「苦手」というよりも「感じ方や考え方のちがい」です。
人と関わるときの感情の動き、表情の見え方、声の聞こえ方、目線の使い方。
それらがすべて少しずつ異なり、一人ひとりの中に独自のパターンがあるというのです。
この論文は、カナダのウエスタン大学、スウェーデンのカロリンスカ研究所、オランダのアムステルダム自由大学による国際共同研究チームがまとめたものです。
自閉症の「社会的知覚」と「社会的認知」を、これまでよりも現実的で個別的な視点から捉えなおしています。
研究チームは、実験室だけでなく、実際の人と人とのやり取りに近い環境でのデータを重視し、「社会性」を“できる・できない”で評価するのではなく、“どんなスタイルで関わっているのか”として理解しようとしています。
論文は、5つのテーマに分けて最新の研究成果を紹介しています。
それぞれのテーマから、「自閉症における社会性の多様な姿」が浮かび上がります。
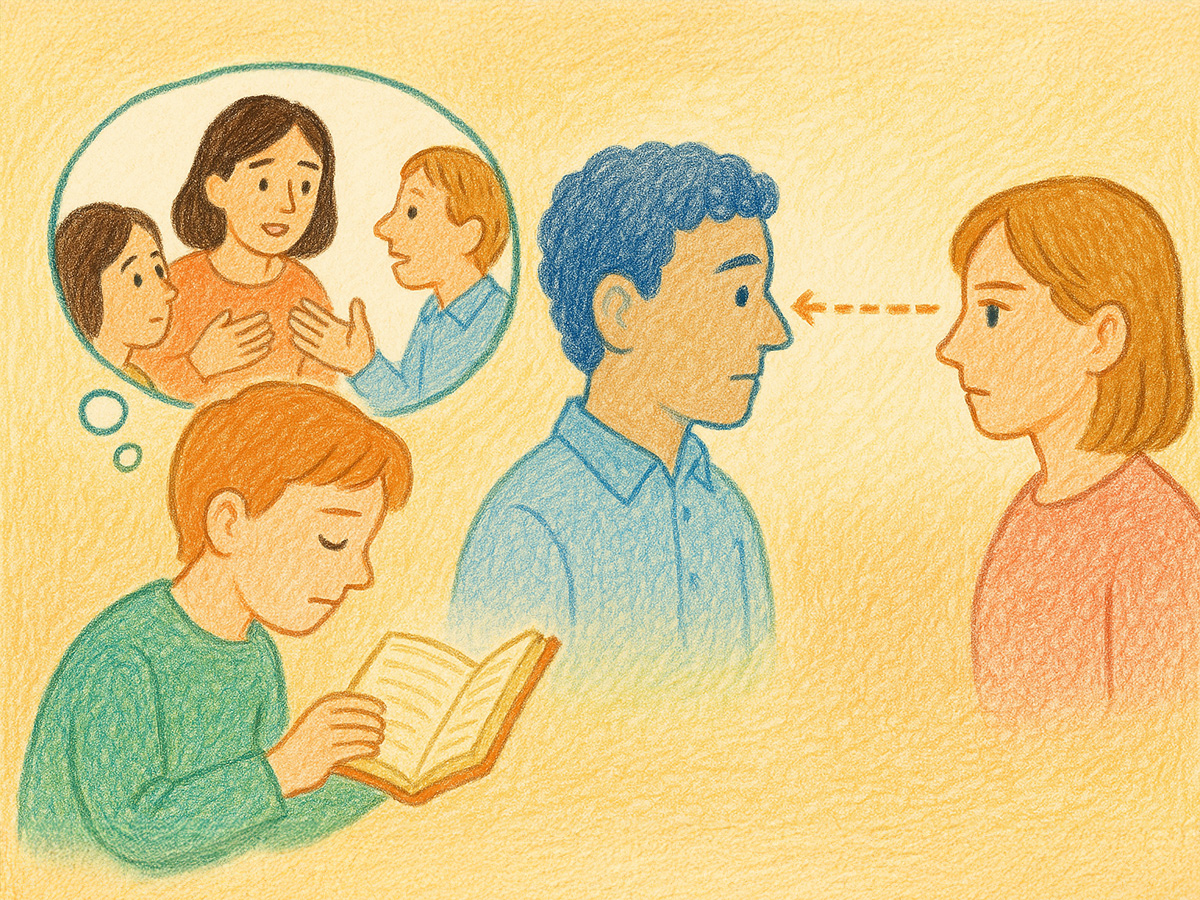
① 社会的認知(ソーシャル・コグニション)
最初のテーマは「社会的認知」です。
これは、人の気持ちや考えを読み取ったり、他人の立場で考えたりする力を意味します。
ある研究では、文章を読んで登場人物の気持ちを想像する課題で、自閉症の成人は一般の成人よりも「共感(エンパシー)」が低く、感情の反応も控えめでした。
しかし、その「感情反応の強さ」が、共感の度合いを左右していることが分かりました。
つまり、感情の感じ方そのものが、社会的理解の基盤になっているのです。
また、自閉症傾向の高い人は、社会的な意味を含む物語を思い出したり、解釈することが難しい傾向を示しました。
さらに、顔の処理に関する研究では、同じ顔を見ても、脳の反応のタイミングや場所が男女で異なっていました。
これは、性別によって社会的情報の処理スタイルが異なる可能性を示しています。
一方で、評価される場面では、自閉症の母親たちが「暗黙の心の読み取り(メンタライジング)」をうまく行うことができたという報告もありました。
ただし、この能力の高さは必ずしも心の健康につながっていないことが示されています。
また、社会的スキルを高めるトレーニングを分析した研究では、全体的に効果はあるものの、その効果が持続するかどうかは、年齢や症状の強さ、実施の環境によって異なっていました。
このテーマが伝えているのは、「社会的認知の違いは、欠けているのではなく、文脈によって変わる」ということです。

② 社会的知覚(ソーシャル・パーセプション)
2つ目のテーマは「社会的知覚」です。
これは、他人の表情や声、動きなどから感情を感じ取る力を指します。
自閉症の成人は、怒り・喜び・悲しみといった感情を表す動きのスピードを、非常に正確に頭の中で再現していました。
しかし、その知識を実際の感情判断に使う度合いが少なかったのです。
つまり、「感じる力」はあるのに、「使い方」が異なっているのです。
また、心拍の音を手がかりに自分や他人の感情を判断する課題では、自閉症傾向の高い人は心拍情報をあまり利用しませんでした。
体の内側の感覚と外の情報を組み合わせるバランスが違っていると考えられます。
表情をまねる反応(顔のミミクリ)は保たれていても、その感情をどう解釈するかが異なるという結果もありました。
つまり、「表情を感じる力」と「意味づける力」が分離している可能性があります。
さらに、視線の使い方をゲームで練習する介入研究では、トレーニングを受けた自閉症の青年たちは、相手の目線から情報をうまく読み取れるようになりました。
ただし、顔を見つめる時間自体はどちらのグループも同じように増えており、「どのくらい見るか」よりも「どう見るか」が大切であることを示しています。
聴覚面でも違いがあります。
自閉症の人は、他人と同じくらい笑う頻度がありますが、「本物の笑い」と「作り笑い」を区別するのが難しい傾向がありました。
また、音の中で言葉を聞き取る課題では、非自閉症の女性では自閉症傾向の高さと聞き取りの難しさには関係がなく、注意の向け方が特性によって異なることが示されました。

③ 視線の使い方(アイ・ゲイズ)
3つ目のテーマは「視線の使い方」です。
視線は、相手とのコミュニケーションの中心にある行動ですが、自閉症の人ではそのリズムや目的が独自です。
2人で話すときの視線を追跡した研究では、話す側と聞く側の役割によって、視線の動き方が異なっていました。
また、アイコンタクトを使って共同作業を行う課題では、相手の意図を読み取るのが難しい傾向がありました。
ただし、「見ていないから理解していない」のではなく、「見る目的」や「注目するタイミング」が違っていたのです。
このテーマが教えてくれるのは、「目を合わせる/合わせない」という表面的な違いの背後に、情報の処理スタイルの違いがあるということです。

④ 感情と覚醒(アラウザル)の調整
4つ目のテーマは「感情と覚醒の調整」です。
以前は、自閉症の人は感情が乏しいと考えられていました。
しかし近年の研究は、感情を「感じない」のではなく、「感じ方や表し方がちがう」ことを明らかにしています。
若い自閉症の成人を対象に、「恥ずかしさ」を感じたときの心の調整を調べた研究では、最初に感じる恥ずかしさの強さは一般の人よりも低い傾向がありました。
しかし、「考え方を変える(再評価)」という方法を使うと、両方のグループが同じように気持ちを落ち着かせることができました。
ただし、自閉症の人は「中立的な解釈」を選ぶ傾向があり、「前向き」な解釈をすることは少なかったのです。
また、相手の瞳孔の変化に対する反応(瞳孔感染)を調べた研究では、自閉症傾向の高い人ほど、その反応が異なっていました。
これは、他人の感情に対する無反応ではなく、感情反応のメカニズムそのものが違っていることを示しています。

⑤ 他者との同期(インターパーソナル・シンクロニー)
最後のテーマは「他者との同期」です。
人と話すとき、笑うタイミングが合ったり、体の動きが自然にそろったりすると、安心感や親しみが生まれます。
このような動きや表情の「リズムの一致」を「同期」と呼びます。
自閉症の人にもこの同期はありますが、そのリズムが独特であることがわかっています。
ある研究では、脳の左右の働き方(ラテラリティ)の違いが、この同期の特徴に関係していました。
また、模倣課題を行っているとき、他人に見られている状況では、自閉症の人の脳の「上側頭溝(視覚と運動を統合する領域)」がより強く反応していました。
さらに、実際の診断面接の映像から、人の動きの同期を解析し、そのデータだけで自閉症の有無をある程度識別できるという報告もあります。
これは、将来的に診断支援技術として活用される可能性を示すものです。
研究チームは、これらの知見をまとめて次のように述べています。
「自閉症の社会的な理解を、“欠けた能力”としてではなく、“多様なあり方”としてとらえる時代が来ている。」
今後は、AIや機械学習を用いたリアルタイム分析、複数人の脳活動を同時に測定する“ハイパースキャニング”などの新技術が、より自然な社会的理解を明らかにしていくでしょう。
そして何より大切なのは、当事者の経験そのものを研究に取り入れていくことです。

違いを欠点と見なすのではなく、独自のスタイルとして理解する。
社会の中で、お互いのリズムを合わせ、違いを尊重していく。
「自閉症の人は社会的でない」のではありません。
「社会との関わり方が違う」ということです。
・感情を感じる力はあるけれど、その表し方や使い方がちがう。
・視線を合わせるタイミングや目的が、人によって異なる。
・体の中の感覚や外の刺激をどう組み合わせるかが独自。
・相手とのリズムや動きの合わせ方が、自然にではなく意識的に行われることもある。
つまり、自閉症の人たちは、「社会を感じ取るセンサーの設定」がそれぞれ少しずつ違っているのです。
その設定の違いが、「苦手」に見えるときもあれば、「独特な強み」として発揮されるときもあります。
社会性とは、みんな同じように感じ、同じように反応することではありません。
お互いの感じ方のちがいを理解し、そのリズムを合わせていくこと。
それこそが、本当の意味での“社会性”なのだと、この研究は教えてくれます。
(出典:Nature Scientific Reports DOI: 10.1038/s41598-025-26432-z)(画像:たーとるうぃず)
違うことが当たり前で、それを前提に、相手を尊重する。
なので違っていると思われても安全で、隠す必要はない。
それが健全な組織、社会、人類だと私は思います。
発達障害の「困難」は社会が生んでいる?神経認知ミスマッチ理論
(チャーリー)