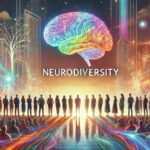この記事が含む Q&A
- ニューロダイバーシティは動物にも適用できるのでしょうか?
- 動物にも脳の働きの多様性があり、表に現れる行動から理解することが大切です。
- 犬の衝動性とADHDの特徴にはどのような関係があるのですか?
- セロトニンとドーパミンといった脳内物質のバランスが関係する可能性が指摘されています。
- 自閉症研究における動物モデルの役割は何ですか?
- 遺伝子や特徴の影響を調べ、脳と行動のしくみを理解する手がかりになります。
犬と暮らしていると、「この子はちょっと“ADHDみたい”だな」と感じる瞬間があります。
たとえば、こちらが呼ぶ前に全力で走り出したり、気持ちがゆれやすかったり、あるいは不安から敏感になりすぎてしまったり。
そんな姿に、どこか親しみを覚える人も少なくありません。
人の世界では、最近「ニューロダイバーシティ(神経の多様性)」という考え方が広く知られるようになり、自閉症やADHDなどの診断を受ける人も増えています。
そして研究者たちは、私たち人間だけでなく、動物たちのあいだにも“脳の働きの多様性”が存在するのではないかと注目し始めています。
動物と一緒に暮らしたことがある人なら、性格や行動の「個性」がとても豊かであることを知っています。
では、動物も“ニューロダイバージェント(神経の働きが多様なタイプの個体)”と言えるのでしょうか。
そしてもしそうなら、私たちは動物たちをどのように理解し、どのように支えていけばよいのでしょうか。
ニューロダイバーシティとは、脳のつくりや働きの違いによって、行動や感じ方に幅があることを示す考え方です。
人では、脳の構造や化学物質のバランスが影響するとされています。
しかし、動物の場合、人のように主観を言葉で伝えることができません。
そのため「世界をどう感じているか」を直接知ることはできず、私たちは表に現れる行動から理解するしかありません。
たとえば「衝動的な犬だ」と人が感じても、それはその犬の“品種としての普通さ”かもしれません。
猫が群れずに単独で行動することも、ただその種の自然な振るまいです。
ラベルを貼る前に、その動物の特性を知ることが大切だと研究は教えてくれます。

それでも、多くの動物で“人のニューロダイバージェンスと似た特徴”が見られることも分かってきています。
犬、ラット、マウス、サルなど、さまざまな動物で遺伝子の違いや行動パターンの違いが報告されています。
たとえば、社交性の強い行動に関係する遺伝子の特徴が、犬の中にも見つかっています。
犬の「衝動性」は、セロトニンやドーパミンという脳内物質の低さと関係することも知られています。
セロトニンは“気持ちを安定させる”働きがあり、ドーパミンは“注意を向けること”を助ける物質です。
これらがうまく調整できないと衝動性が強まり、人のADHDで見られる特徴と重なる部分があります。
もしかすると、私たち人間が長い歴史のなかで「一緒に暮らしやすい動物」を選んできたことが、こうした脳の特徴を持つ動物を残すことにつながっているのかもしれません。
研究者たちは、自閉症の生物学的な理解を深めるために「動物モデル」を作っています。
これは、特定の遺伝子や特徴を持つ動物を使い、脳や行動のしくみを調べる方法です。
現実の動物たちの多様さを完全に表すものではありませんが、神経の働きの土台を理解する手がかりになります。
たとえば、ビーグル犬の一部には「Shank3(シャンク3)」という人の自閉症にも関係する遺伝子の変化が見つかっています。
その犬たちは、人に対してあまり近づきたがらない傾向があります。
脳の中を詳しく調べると、注意に関わる領域で細胞どうしの“情報のやりとり”が少なくなっていました。
さらに、人と犬のあいだには「ニューラル・カップリング(脳活動が一時的に同期する現象)」が生まれることがわかっています。
2024年の研究では、人と犬が目を合わせると脳の活動パターンが似てくることが確認されています。
しかし、Shank3の変化を持つ犬では、この結びつきが弱くなる傾向があり、自然な対話や絆が生まれにくいと考えられています。
ただし、行動には環境の影響も大きく関わります。
子犬のころに人と十分な交流が持てなかった場合も、人への興味が弱くなることがあります。
遺伝か、環境か、その両方かを見分けることは簡単ではありません。

興味深いことに、この犬の研究は人の自閉症に関する新しいヒントも示しました。
Shank3変化を持つ犬に少量のLSDという物質を投与したところ、数日間、人への注意が高まり、ニューラル・カップリングが増えたというのです。
もちろんLSDには法的・倫理的問題がありますが、「脳がどのように情報をやりとりしているのか」という理解には役立つ可能性があります。
こうした動物研究は、人の診断方法にも影響を与えつつあります。
たとえば犬のADHDのような特徴を判断するため、研究者は犬の動きをカメラで記録し、機械学習で分析する方法を試しています。
2021年の研究では、人が評価した診断と、機械による分析が81%一致しました。
これは、人の診断でも「もっと客観的な方法」が広がる可能性を示唆しています。
人のADHD診断に“目の動き”の測定が使われている例と似ています。
犬や猫では、困難な行動が生活の質を下げてしまうことがあります。
2024年の研究では、4万3千匹以上の犬のデータのうち、99%が何らかの行動上の問題を示していました。
分離不安、恐怖、過敏さ、こだわり行動――これらは人のニューロダイバージェンスと重なる側面もあります。
こうした行動が理解されないまま続くと、飼い主も疲れてしまい、最悪の場合は手放す決断につながってしまうこともあります。
けれど、動物たちがもつ“脳の多様性”を知ることで、私たちはより適切な関わり方を選べるかもしれません。
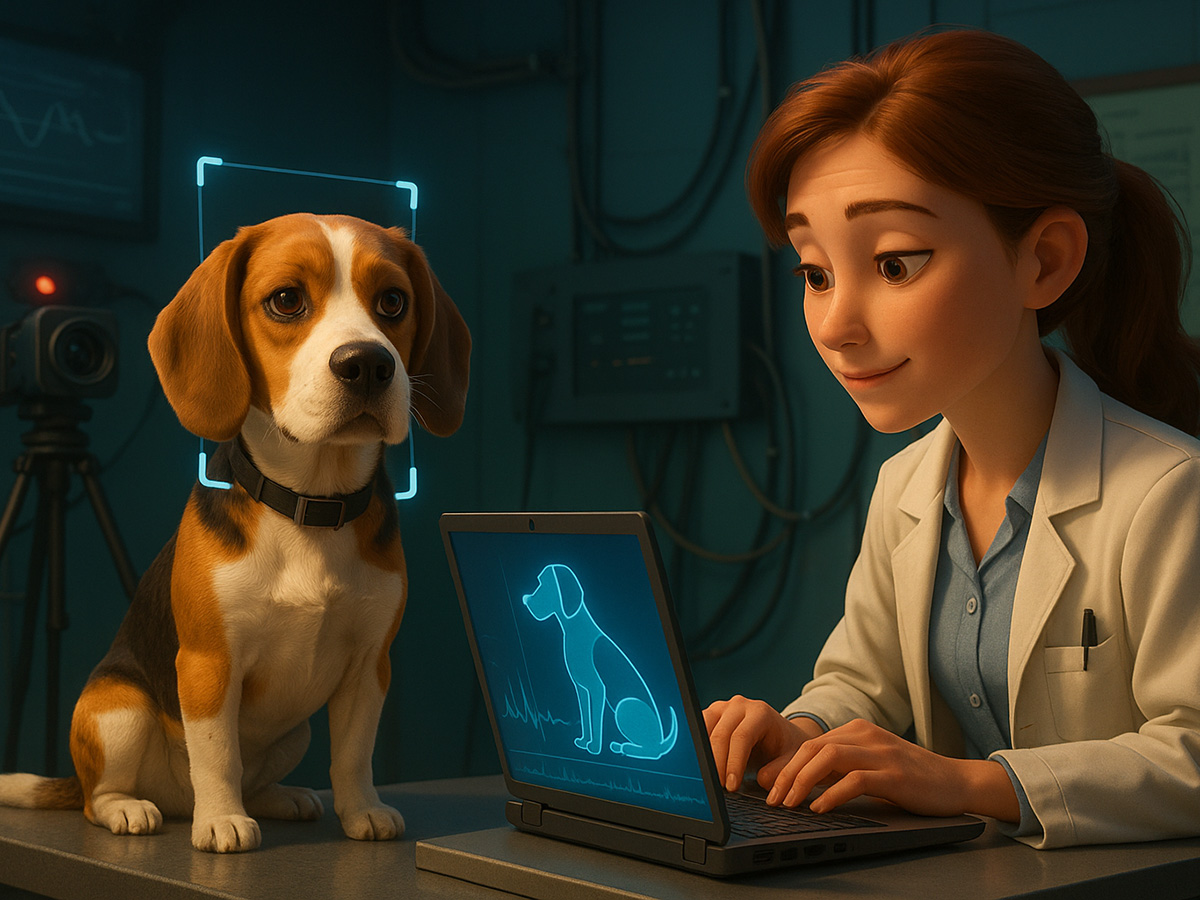
私たち人間と同じように、動物たちも世界をそれぞれの方法で感じています。
性格の違いもあれば、脳のつくりや化学物質のバランスの違いもあります。
自閉症のある子どもが、特性に合わせた環境や関わり方で力を発揮できるように、動物たちの特性にも合わせた“より優しい支え方”を考えていくことができるはずです。
私たちの隣にいる動物たちが、どんなふうに世界を見ているのか。
その違いを理解しようとすることは、互いに安心して過ごせる関係をつくるための大切な一歩です。
(出典:THE CONVERSATION DOI: 10.64628/AB.qrkpw6tmt)(画像:たーとるうぃず)
行動を「問題」として捉える前に、そこにある感覚や脳の違いに気づくこと。
その視点が広がれば、当事者も家族も、そして周りで支える人も少し生きやすくなるはずです。
(チャーリー)