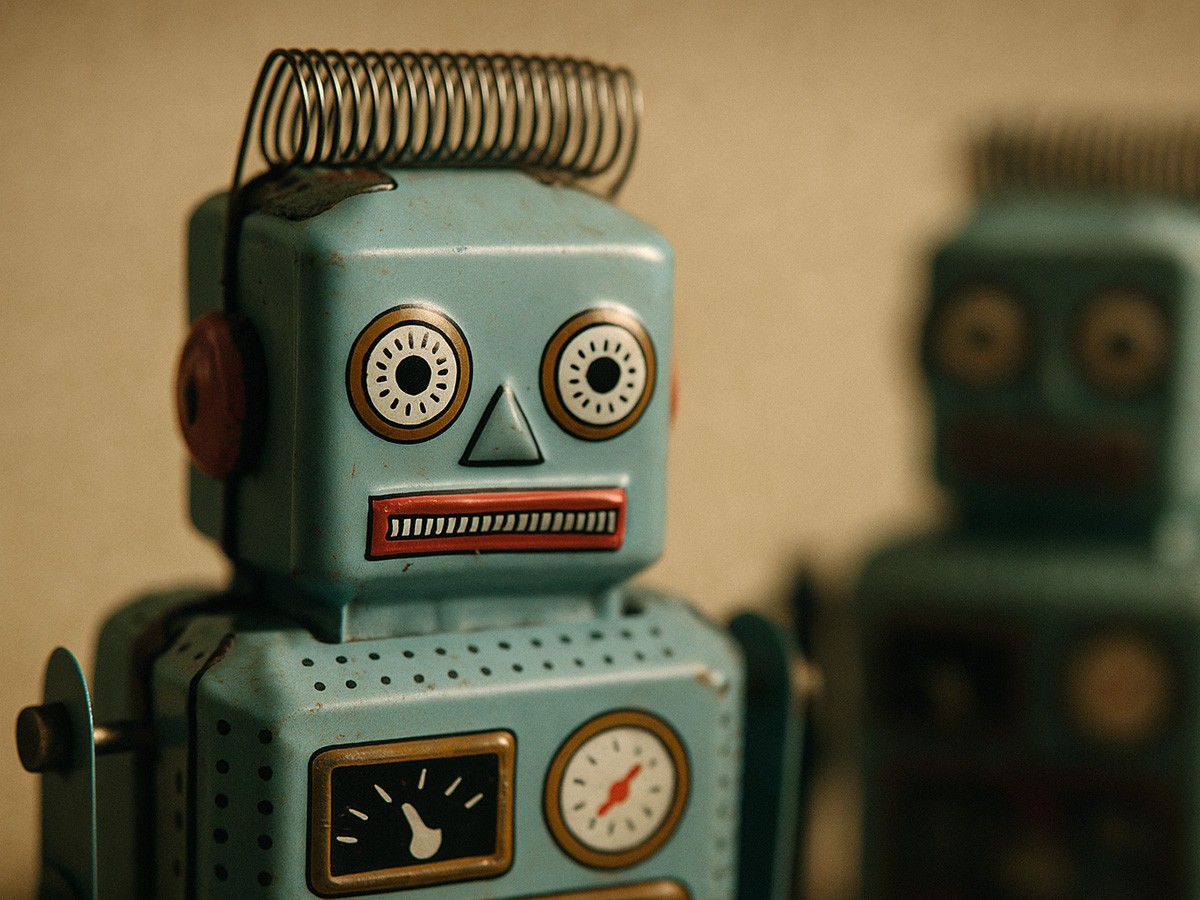
この記事が含む Q&A
- 自閉症のある人にとって視線を合わせることは自然ですか、それとも負担になりますか?
- 負担であり強い刺激として感じる人が多く、視線を合わせることは意識的な努力が必要とされます。
- 視線が合わない場合でも会話は成り立ちますか?
- はい、視線を外していても相手を大切に思う気持ちは変わらず、別の方法で対話を続けられます。
- 社会は視線以外のコミュニケーション形態を受け入れるべきですか?
- はい、視線には正解が一つではなく、相手の感じ方を尊重し共存の姿勢が望ましいと述べられています。
私たちは会話をするとき、自然と相手の目を見ます。
多くの人にとってそれは無意識に行われる動作であり、言葉と同じほどに重要なコミュニケーションの土台だと感じられています。
しかしその一方で、目を見るという行為が強い刺激となり、心や体が緊張してしまう人たちがいます。
それが自閉症のある大人の一部です。
この研究は、視線というごく小さな動作に隠れている「感じ方の違い」をていねいにすくい上げようとしたものです。
そしてその結果は、ただ自閉症の特性を説明するものではなく、人が互いに向き合うときに必要な想像力と優しさを明らかにしています。
オランダのユトレヒト大学医療センター、精神医療ネットワークの Dimence Groep、パルナッシア精神医学研究所、NHL Stenden University of Applied Sciencesの四つの機関が協力し、日常生活の中で視線をどのように感じているのかを確認するために研究が行われました。
参加者は30名です。
自閉症と診断されている大人が15名、診断されていない大人が15名。年齢や性別、教育背景が偏らないようにバランスが取られ、誰か一人の体験だけが特別な重みを持たないように配慮されています。
研究の中心となったのは「話を聞くこと」です。
参加者一人ひとりに対し、研究者は約45分から1時間ほどかけて対話を行いました。
そこで交わされるのは実験的な課題や数値を測るものではなく、その人の内側から出てくる言葉です。
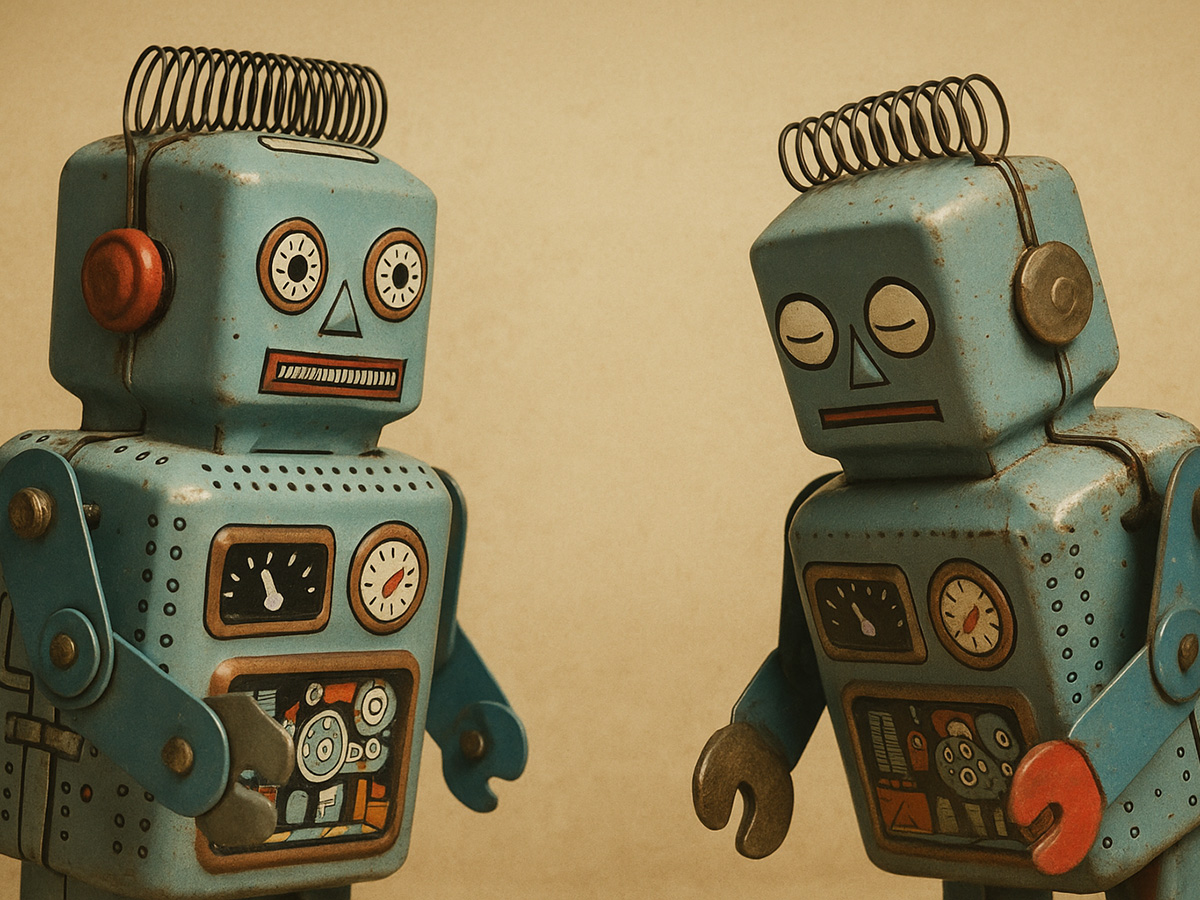
「視線が合うとき何を感じますか?」「目を見ることは自然ですか、それとも努力が必要ですか?」といった問いかけに対し、参加者たちは自分の言葉でゆっくりと語りました。
研究者たちはその発言を録音し、文字に起こし、繰り返し読み返しながら意味を整理していきました。
ここから浮かび上がってきたのは、自閉症のある人とない人の間にある大きな違いと、不意に現れる似ている点です。
まず、自閉症のある参加者の多くは、視線を合わせることが「強い刺激」であると語りました。
それは痛みではなくとも、刺さるような感覚、相手に中身を覗かれてしまうような感覚だと表現されています。
なかには「見られている」というだけで頭がいっぱいになり、話の内容が追えなくなると語る人もいました。
この「中身を覗かれる感じ」は、ただ恥ずかしいというだけではなく、自分の弱さを見抜かれてしまうような不安とも結びついています。
相手の目を見ようとすると、自分の内側がそのまま露出してしまう気がしてしまうのです。
さらに多くの参加者が、自分が視線を合わせているとき「無意識」ではないと語りました。
視線を合わせる時間、目をそらすタイミング、相手がしゃべっている間は見るけれど自分が考えるときは目線を外す、といった操作がすべて意識のうえで行われています。
つまり、視線を合わせることは自動的な動作ではなく、一つひとつ手順を踏まなければ成り立たない行為でした。
言い換えると、目を見ることは筋肉ではなく頭を使う動作であり、それが自然に行えないからこそ、社会的場面では負担になります。
一方、自閉症ではない参加者にとって、視線はほとんど労力を必要としない動作でした。
「相手を見る」ということは、話す・聞くと同じレベルで自動的に行われており、そこに神経を使うことはほぼありません。
「意識的に視線を管理している」と答えた人はほとんどいませんでした。
彼らにとって視線は、相手の感情や雰囲気を知る手がかりであり、安心するための材料でもありました。
つまり、同じ「目を見る」という行為が、自閉症のある人には負担であり、自閉症のない人には自然であるという大きな差が存在します。
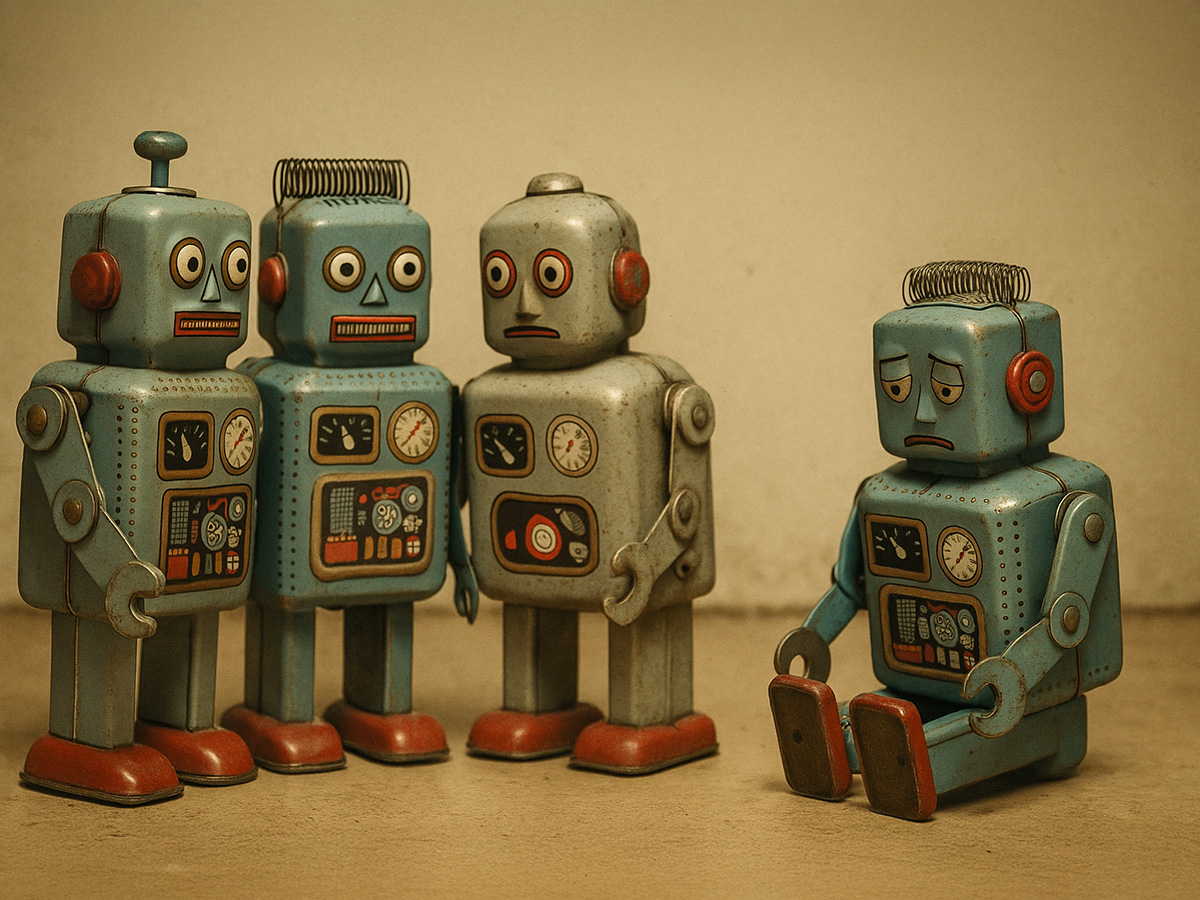
しかし、研究は二つの群の違いだけを示すものではありません。
似ている点もありました。
たとえば、自閉症のない参加者の一部も視線をプレッシャーに感じると語りました。
長く見られると落ち着かない、人と話すときずっと視線を保つ必要はないと感じる、といった声です。
つまり視線への感覚は連続的であり、自閉症があるかないかで完全に二分されるわけではないということです。
また、自閉症のある参加者の中にも、家族や信頼している相手となら視線を合わせてもつらくないと答える人がいました。
相手との関係が安定しているとき、視線はむしろ安心の証にもなるのです。
自閉症のある参加者の発言で特に印象的だったのは、「努力して視線を合わせているのに、それが周囲には伝わらない」という声でした。
当たり前にできると思われている動作が実は重労働であり、それを頑張って実行しているのに、それが評価されるどころか「もっとちゃんと相手を見なさい」と指摘されることがあります。
この齟齬は、他者の世界が見えにくい社会では起こりやすいものです。
研究はその乖離そのものを浮き彫りにしています。
目が合わないという事実だけでは、努力も負担も読み取れません。
けれど、当事者の言葉を聞くことで「見ていないのではなく、見ようとしている」が理解できるようになります。
視線を合わせることがつらい理由のひとつに、「情報が入りすぎる」という感覚があります。
目を見ると、相手の目の色、動き、表情、周囲の光まで同時に押し寄せ、その処理が追いつかなくなると語った参加者が複数いました。
視線は感覚刺激の入口であり、そこから流れ込む情報量は自閉症のある人にとって多すぎることがあります。
だからこそ、視線を外すことは逃げではなく整理のための行動なのです。
会話に集中するために視線を落とす、これはむしろコミュニケーションを続けるための調整行為です。
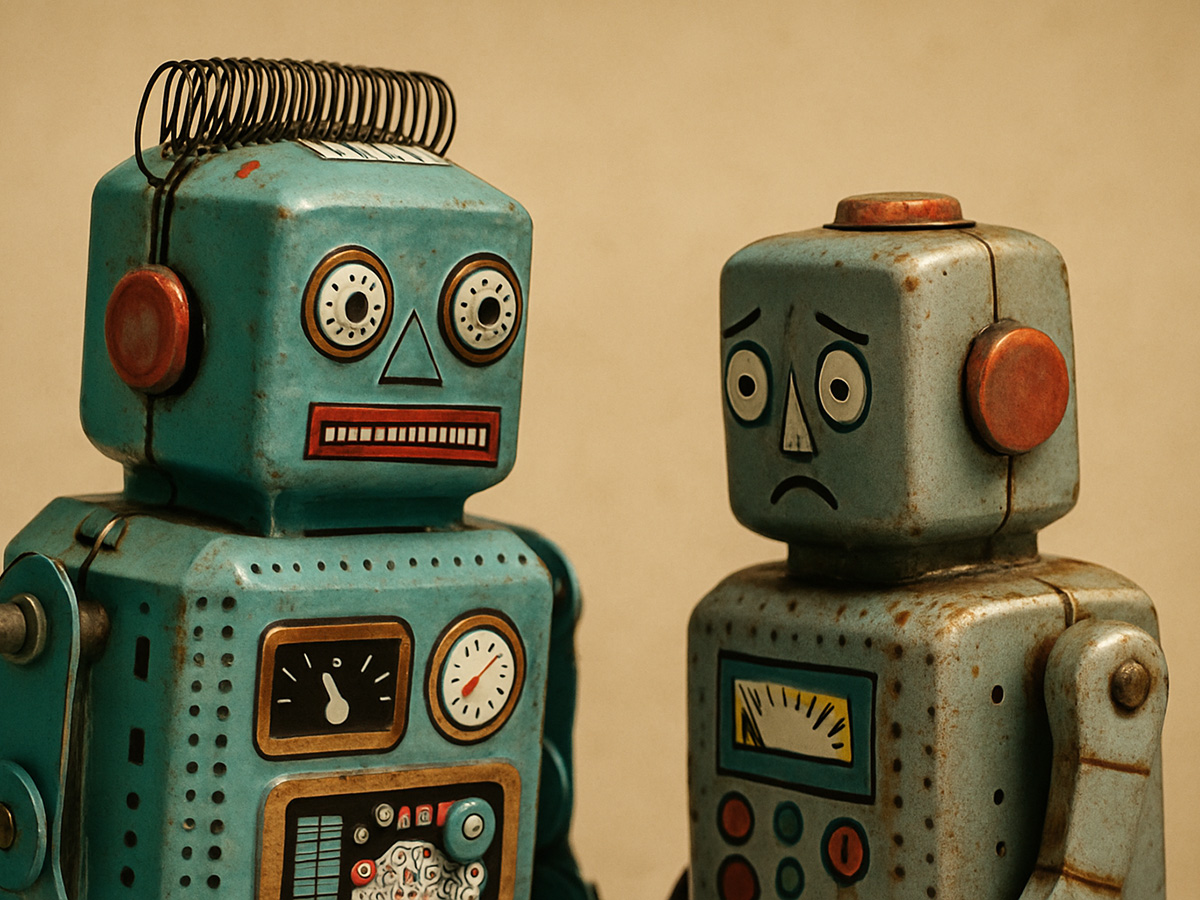
研究の終盤で明らかになったのは、自閉症のある多くの参加者が、「視線のやり方を変えたい」とは思っていなかったことです。
むしろ求めていたのは、社会側がさまざまな形のコミュニケーションを受け入れてほしいという願いでした。
視線が少なくても会話は進みます。
視線を外す時間があっても相手を大切に思っていることは変わりません。
「目を見る=礼儀」という一つの型が絶対ではないことを、この研究は示しています。
研究者らは「視線には正解がひとつではない」と書いています。
視線を合わせない人は無関心なのではなく、その形こそが会話を続けるための工夫なのです。
頭を下げながら真剣に聞く人もいます。
手元を見つめながら考えを整理する人もいます。
相手の表情ではなく声の質に注意を向ける人もいます。
どの方法も間違いではありません。
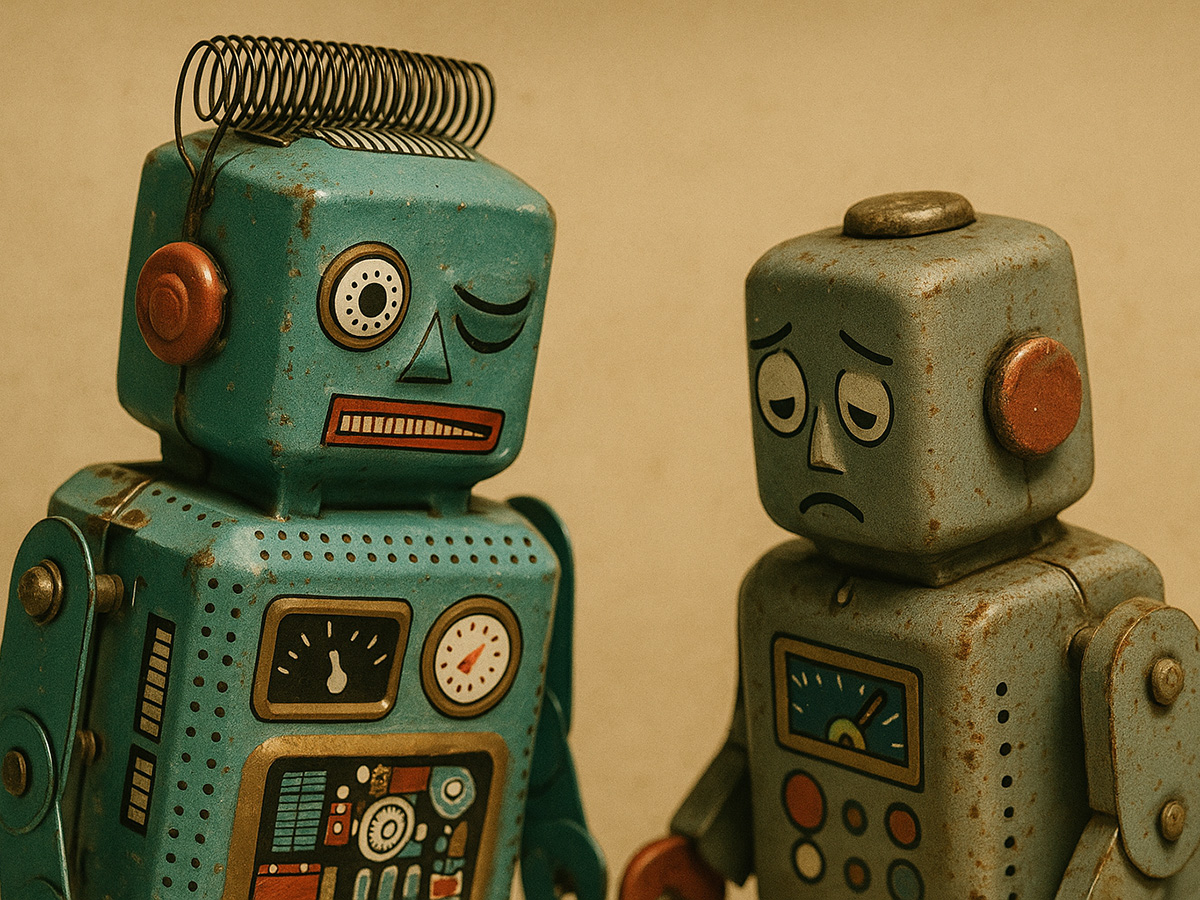
私たちがこの研究から学べることは、「違いを欠如と呼ばない」という姿勢です。
視線が少ないからといって「関心がない」と決めつけず、そこにある努力や感じ方を尊重すること。
それは支援ではなく共存の姿勢です。
目を見られない子どもや大人がいても、それを問題にする必要はありません。
そこにあるかもしれない不安や刺激の強さを想像し、無理をさせず、その人のペースを受け入れることで対話はずっと豊かになります。
もし未来の社会が「視線は絶対でなくていい」と合意できたなら、コミュニケーションはもっとやわらかく、歓迎的なものになるでしょう。
視線を合わせなくても、話を聞けます。
視線を外していても、関わりを持てます。
この研究は、目を見ることの意味を一度ほぐし、そこに隠されてきた努力と痛みと優しさを広げて見せてくれます。
そして「あなたの見方はあなたのままでいい」というメッセージを静かに伝えています。
(出典:Journal of Neurodevelopmental Disorders DOI: 10.1186/s11689-025-09663-z)(画像:たーとるうぃず)
少なくとも日本では、そもそもそこまでアイコンタクトを求められないと思うのですが、無理をして行う必要はないと私も思います。
(チャーリー)





























